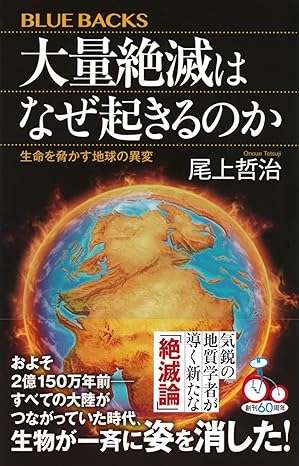刀鍛冶となるため男として過ごす少女・美禰と、伊勢に流された徳川の若き殿様・松平忠輝の運命の恋の物語を描く、鷹井伶著の長編時代小説『わたしのお殿さま』(KADOKAWA)。時は江戸、紀伊半島の中心部に位置する霊峰を仰ぎ見る地に暮らす、美禰。女人禁制の鍛冶場で、刀鍛冶の名匠である祖父・月国の後継者となるため、鋒国(みねくに)という名を頂き、男を装うように育てられています。その地へ流罪となってやってきたのは、徳川家康の六男・松平忠輝。父の死後3カ月足らずで腹違いの兄である将軍秀忠によって配流にされてしまいます。七月七日、里で行われている七夕の神事を眺めていた美禰。そこに突如、獰猛な熊があらわれて──。神の地・伊勢で巡り会う、運命に翻弄される美禰と忠輝。ふたりの恋の行方は?
※本記事は鷹井 伶著の書籍『わたしのお殿さま』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。
二
陽の光がなだらかな波に反射してやけに眩しい。
潮の香りを胸いっぱいに吸い込みながら、松平忠輝は大きく伸びをした。
眼下に広がるのは、紺碧の海、そして伊勢の湊――上方と江戸を往来する廻船が必ず寄港することから、船宿や問屋が建ち並ぶ賑やかな湊の風景だ。
白い帆いっぱいに風を受けた船が行き交うさまを眺めていると、自分が罪人として流されてきたことが、夢か幻のようだ。しかし、それが現実であることは、後ろに控える厳めしい顔つきの公儀の遣いたちが証明している。
忠輝は徳川家康の六男としてこの世に生を受けた。
母は於久(茶阿の方)。元は鋳物師の女房だったが、その美貌は抜きん出ていて、彼女に横恋慕した代官が夫を殺害し、我が物にしようとした。於久は逃げ、ちょうど鷹狩り中の家康一行に助けられる形で奥勤めに入った。側室となってからは忠輝の他に弟・松千代(夭逝)を産んでいる。
忠輝は、関ケ原の戦いの時は九歳で戦に出ることはなかった。だが、やがて仙台の雄・独眼竜として怖れられていた伊達政宗の姫を娶り、大坂の陣では豊臣家の滅亡を見届けた。
歳は二十五。越後高田七十五万石の藩主として立派に築城までやり遂げ、まだまだこれから世のためになさねばならないことが数多くあると信じてきた。それなのに、父・家康の死後、わずか三カ月足らずで城地を全て召し上げられ、配流になると誰が想像しただろう。
しかもそれを命じたのは腹違いとはいえ、兄の二代将軍秀忠なのである。
私にそこまでされるほどの落ち度があったか――。
忠輝は幾度も自分に問いかけてみたが、答えは出なかった。
ただ、己の信じるままに突き進んできた。命令に背き、父や兄の面目を潰すことになっても厭わなかった。そうした方が、民のため、世の中のためになるのだと信じていたからだ。
それほどまでに、私が怖いのか――。
忠輝は秀忠の小太り顔を思い起こした。十三歳も年上の兄である。
父・家康の三男にあたる秀忠は外見こそ父に似ているが、肝の据わり方は全く似ていない。敵であっても受け止める度量の広さも、人の思いに心を寄せる優しさも、他の追随を許さない大胆さも、残念ながら、この兄から感じたことがない。
忠輝の生まれる前の話だが、長兄の信康が織田信長の命を受け自刃し果てた時、次兄の秀康は秀吉の養子となっていて、秀忠の元に嫡男の座が転がり込んだらしい。それでも家督を継ぐにあたってはすんなり決まったわけではなく、秀康と秀忠、そしてその下の兄、忠吉の間でちょっとした小競り合いがあったと耳にしている。
不可思議なのは、秀康も忠吉も、さらには忠輝のすぐ上の兄・信吉もみな、戦ではなく病で死んでしまっていることだ。
そして私。いや、いくら何でもそれは考えすぎというものか――。
「殿......」
横に控えていた岩本競兵衛が静かな声で出立を促してきた。
幼い頃からいつも側にいてくれる、ありがたい家来だ。これからのことを考えると心配でならないはずだが、態度には一切出さず、これまで通り、側で支え続けようとしてくれている。
今、忠輝に付き従ってくれているのは、この競兵衛を含め十名ほどの家来のみだ。そのほとんどが忠輝同様二十半ばの若さ、中には前髪が取れたばかりの者もいる。みな一騎当千のツワモノで、このまま終わらせるには惜しい者たちばかりだ。
もちろん、忠輝にしてもここで終わる気はない。
流人の身で何ができるか――。
不安がないといえば噓になる。全ての後ろ盾を失って奈落に突き落とされたと、嘆くのが普通なのかもしれない。だが、忠輝はそう思いたくはなかった。
流されたと思うから辛い。強がりでもよいから、羽ばたくための時を与えられたと捉えればよいではないか。
それに、この伊勢は神の地だ。
森羅万象、全ての穢れは心がけ次第で洗い清められるという。それが本当なら、この地で全てを清め、生まれ変わればよい。
「......能天気な奴め」
ふっと父の声が耳に蘇った。愚かだと笑われたと感じたこともあったが、今となってはただただ懐かしい。あの時、この上もなく優しい目をしておられた――。
「殿......」
競兵衛は少し困ったような顔をしている。
「参ろう」
心配するなと、忠輝はわざと明るく微笑んでみせた。