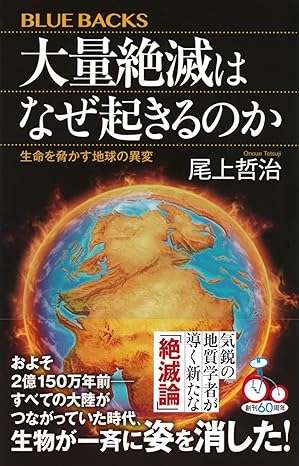刀鍛冶となるため男として過ごす少女・美禰と、伊勢に流された徳川の若き殿様・松平忠輝の運命の恋の物語を描く、鷹井伶著の長編時代小説『わたしのお殿さま』(KADOKAWA)。時は江戸、紀伊半島の中心部に位置する霊峰を仰ぎ見る地に暮らす、美禰。女人禁制の鍛冶場で、刀鍛冶の名匠である祖父・月国の後継者となるため、鋒国(みねくに)という名を頂き、男を装うように育てられています。その地へ流罪となってやってきたのは、徳川家康の六男・松平忠輝。父の死後3カ月足らずで腹違いの兄である将軍秀忠によって配流にされてしまいます。七月七日、里で行われている七夕の神事を眺めていた美禰。そこに突如、獰猛な熊があらわれて──。神の地・伊勢で巡り会う、運命に翻弄される美禰と忠輝。ふたりの恋の行方は?
※本記事は鷹井 伶著の書籍『わたしのお殿さま』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。
「......片付け、終わりました」
鋒国は、先に母家にもどっていた月国に向かって、土間からそう声をかけた。
「うむ」
囲炉裏端の上座に座り、茶をすすっていた月国は小さく頷くと、自分の前に置かれた膳に手を伸ばした。質素な御膳だが、焼いた川魚と細かく刻んだ野菜の入った粥が美味しそうな湯気をあげている。
「ほんま、お疲れさんやったねぇ」
賑やかな声を上げ、鋒国の髪に後ろからそっと手をやったのは、おつか。月国の末妹で、鋒国にとっては大叔母にあたる。
「先にお風呂に入るか、それともご飯がええか」
汗を流したいのは山々だったが、おつかがそう望んでいるような気がして、「飯にする」と、鋒国は答えた。
「そう言うと思った」
おつかが嬉しそうに応じたのを見ながら、鋒国は月国の向かいに腰を下ろした。
「それで、どない? 今度のもええ具合にできたんか」
膳を持ってきたおつかは、名刀の出来をまるで畑の大根か葱のように尋ねた。
おつかの歳は四十半ば。月国とは腹違いの妹である。月国の父・矩国(鋒国の曽祖父)は最初の妻との間に月国をもうけたが、その後死別。しばらくして、里の女との間に三人の女の子をもうけた。その一番末がおつかだ。
還暦近い月国とは一回り以上離れているせいか、肌の張りも声の調子も若々しい。若い頃には嫁いで夫も子もいたが、訳あって今は独り身だ。早くに父母を亡くした鋒国にとって、いわば育ての母である。
無口な月国とは対照的に大変なおしゃべり好きで、おつかが一人いるだけで、この家は賑やかだ。
鋒国はちらりと目を上座にやった。あぐらをかき、椀を手にした月国は、さっきから黙々と顔色一つ変えず、粥を口に運んでいる。出来具合をいちいち尋ねる必要があるかと言わんばかりだ。だが、おつかは全くお構いなしだ。
「なぁってば」
と、焦れったそうなおつかを見て、鋒国が代わりに「あぁ」と頷いてみせた。
「ほんなら、あにさん、都に行くんはいつ?」
おつかは、月国のことを昔からあにさんと呼ぶ。
「......来月の七日に発ちはるんやと」
と、今度も鋒国が代わりに答えた。月国は宮中からも信頼篤く、その刀は主に皇子や皇女の守刀になっている。今回の一振りもまた、宮中からの依頼品で、拵えを済ませた後、月国自らが持参する手筈になっていた。
「七日って、ひと月しかないやん。甚さんとこ、大変やないの」
甚さんというのは、刀の拵え一切を手掛ける奈良屋甚右衛門のことである。
刀匠が打った刀はこの後、専門の研師、刀身彫刻師、鞘師、塗師、刀身の根元を固定する鎺を作る白銀師、鍔や目貫など金細工を作る金工師、握り手の柄に装飾的な紐巻きを施す柄巻師......と様々な人の手を経て仕上がる。甚右衛門はそういった細工職人たちの元締めであり、錺細工一切を請け負い、手広く商売をしていた。
「......出来るって言うたんやから、出来る」
「どうせまた無理言うたんでしょ。あにさんはごり押しの名人やからな」
おつかがやれやれと肩をすくめた。そのとき、表で「いらっしゃいますか」と若い男の声がした。
「はい」と鋒国が腰を上げるのと、月国が「おお、こっちや」と声を出したのが同時になった。月国はよそ様に対してはきちんと返事をする。
戸口から顔を見せたのは、奈良屋甚右衛門の息子・魁であった。
「早いな」
「お約束ですから」
魁が如才なく微笑むと、月国は応じるように頷き、床の間に目をやった。打ちあがったばかりの刀は三宝に載せ、白布を被せ、床の間に置くのが決まりだ。
鋒国は一礼すると、刀を取ってくるため床の間に向かった。
魁は鋒国と同い年の十六歳。物心ついたころからよく遊んでくれる兄のような存在だ。鋒国が女であることに気づいているはずだが、余計なことは何も言わない。
魁は今、父の跡を継ぐために修業中だ。こうして刀の受け渡しや細工職人たちの間の調整役をし、時にはそれぞれの作業の手伝いもするようだ。
ほっそりとした体軀をしていて力仕事は苦手のようだが頭の回転は速いし、手先も器用で、人当りもよい。去年ぐらいから背丈もぐんぐん伸び、顔つきも急に大人びてきた。顎や額に吹き出物を出しているのは若さの証拠だが、それ以外は誰の目から見ても、奈良屋の跡継ぎにふさわしい存在になりつつあった。
「また、背が伸びたのと違う?」
おつかが魁の肩に軽く手を伸ばした。おつかの背は魁の肩あたりまでもない。
「何を食べたらそんなに伸びるんやって、よう言われますわ」
と、これまた、如才なく魁は応じた。
「どうぞ」
鋒国が刀を取ってくると、魁は「ありがとうございます」と、律儀に押し戴いてから、持参した白木の箱に納めた。そういうさまも、すっかり板についている。
「......大変やったやろ」
魁はそう囁いてから、鋒国を見た。心配していると言いたげな目だ。そういうときの魁は昔から変わらない。
「いや、別に」
と、鋒国は答えた。素っ気ない返事になってしまったが、実際、刀が出来上がった瞬間は高揚感もあり、疲れは感じない。
「そっか。そうやったらええけどな」
魁はちょっと笑顔を見せてから、月国に挨拶をした。
「......ほな、失礼します」
「ああ、頼むで」
「はい」
魁は月国に一礼してから、すぐに踵を返した。
「なんや、粥の一杯も食べていけばええのに」
おつかがつまらなそうな声をあげたが、魁は「また今度」と手を上げ、飛び出していった。
「......おばはんと食べても嬉しぃないんやろ」
ぼそっと月国が呟つぶやく。
「誰がおばはんやって」
むっとしたおつかの目の前に、月国はぬーっと椀を差し出した。
「さぁ、誰やろ」
「はぁ、じいさんに言われたないわ。もうぉ」
口では怒りながらも、おつかは月国の椀を受け取り、甲斐甲斐しくお代わりをつけはじめた。
「芋、多めにな」
「わかってるわ」
軽い口喧嘩のような、じゃれ合いのようなやり取りが続く。これもこの兄妹が仲の良い証拠だ。
微笑ましく感じながら、鋒国は自分の粥をすすり始めた。