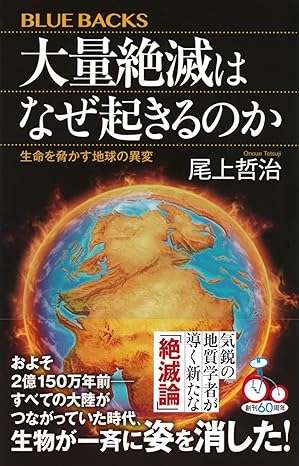刀鍛冶となるため男として過ごす少女・美禰と、伊勢に流された徳川の若き殿様・松平忠輝の運命の恋の物語を描く、鷹井伶著の長編時代小説『わたしのお殿さま』(KADOKAWA)。時は江戸、紀伊半島の中心部に位置する霊峰を仰ぎ見る地に暮らす、美禰。女人禁制の鍛冶場で、刀鍛冶の名匠である祖父・月国の後継者となるため、鋒国(みねくに)という名を頂き、男を装うように育てられています。その地へ流罪となってやってきたのは、徳川家康の六男・松平忠輝。父の死後3カ月足らずで腹違いの兄である将軍秀忠によって配流にされてしまいます。七月七日、里で行われている七夕の神事を眺めていた美禰。そこに突如、獰猛な熊があらわれて──。神の地・伊勢で巡り会う、運命に翻弄される美禰と忠輝。ふたりの恋の行方は?
※本記事は鷹井 伶著の書籍『わたしのお殿さま』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。
三
今朝早く、約束通り仕上がった刀を献上するために、月国は独り、都へ出かけて行った。
月国が留守にしていても、鋒国の日常に変わりはない。
日の出前から起き出して、滝行を済ませてから、鍛冶場の神棚に水を供える。それから、朝食を食べ、ふもとの村へ米や野菜を買いに行くというおつかを見送ってから、炭切りを始めた。
炭切りは刀匠の仕事としては基本中の基本だ。専用の包丁を使い、燃料に使う炭を一寸(約三センチ)四方程度の大きさに切っていく。使うのは燃えやすく温度が上がりやすい松炭で、軽い炭なので粉もできやすく、衣はもちろん、顔も手指も爪もすぐに真っ黒になってしまう。しかし、これを嫌がっていては仕事にはならない。余計な考え事をしていると、それが炭に伝わるのか、断面が乱れてしまう。
特に苛々しながら切った炭は炎が怒ると言って、月国は嫌う。
不思議なことに、心を落ち着かせて和らいだ気持ちで切っているときの炭は、鉄に優しい炎を作るというのである。
この日もいつもどおり、鍛冶場の前で無心になって炭を切り続けていると、額から汗が滴り落ちて、目に入った。七月に入ってから急に暑さが増した気がする。
「あぁ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ」
賑やかに言いながら、おつかがふもとの村から帰ってきた。
「お帰り。何がえらいこっちゃなんや。また熊でも出たんか」
鋒国は、つい先日、滝の側に大きな熊がいたとおつかが騒いでいたことを思い出した。
「違う。今度は鬼や。鬼が伊勢に流されて来たんやて」
「鬼......化け物が出たってことか」
「ううん、違う違う。公方さまの弟君で、名は松平忠輝っていうお方」
公方さまとは徳川幕府二代将軍・徳川秀忠のことである。
おつかは人差し指で、自分の目を大げさにぐいっと釣り目にした。
「こ〜んな目ぇして、鼻も天狗みたいで、そいで口は耳まで裂けてるって」
おつかは身をぶるぶる震わせてみせた。
「けど、公方さまのお身内ってことは、どこかの殿さまやろ」
「さぁ、よう知らんけど、ともかく、生まれた時から鬼っ子って呼ばれてはって、なんや争いごとが好きで、乱暴狼藉が過ぎたって」
「それでお取り潰しになったってことか」
「いや、そうやのうて......ちょっと待って」
と、おつかはちょっと記憶を辿る素振りをみせた。
「ああ、そうそう。大坂の陣のときに、戦うのは嫌やって出てけぇへんかったって。それでお取り潰しになったとか」
この辺りの村の者はみな大坂・豊臣贔屓であった。大坂城が落城したことを悲しむ者は多く、表立って言わないまでも、徳川の方が悪いと思っている。
「なんや、おかしいな」
と、鋒国は呟いた。
「何が?」
「そやかて......その鬼っ子さまは徳川方やけど、大坂を攻めへんかったんやろ。そしたら、悪いお人ではなく、よいお人やし、争いごとが好きっていうのも違う気がする」
「あれ、ほんまやな」
と、おつかも首を傾げた。
「けどなぁ......。まぁ、ともかく、九鬼の殿さまもどない扱ってええか、困ってはるんやって」
九鬼の殿さま――九鬼家といえば、戦国最強と呼ばれる水軍を率いた武門の雄で、織田信長、豊臣秀吉に仕えてきた名門だ。ただ、当代の九鬼守隆は関ケ原の戦いにおいて東軍(徳川方)に付くことを選び、その功労により、志摩鳥羽藩五万六千石の藩主となっていた。
おつかの話だけでは、結局松平忠輝という殿さまに何があったかはわからなかったし、本当に鬼なのか、それとも良い人なのかもわからない。
しかし、いずれにせよ、鋒国にとっては、あまり関わりのない話に思えた。
「ふ〜ん」
鋒国は興味なさげに応じてから、炭に手をやった。すると、おつかがその手から、炭切り包丁を取り上げた。
「まぁまぁ、今日ぐらいはええやないの。もうたくさん切ったでしょ。はよ、着替えて行かんと」
「行くってどこへ」
不思議そうな鋒国に、おつかはやれやれと笑ってみせた。
「今夜は七夕さんや。お祭り見ておいで」
「七夕さん......」
この辺りの里では、七夕には氏神さまで祭りがある。だが、鋒国は月国から男として生きよと命じられた六歳のときから、村人との付き合いがあまりなく、当然、祭りにも参加したことがなかった。
「世の中のことも少しは知らんとあかん。あにさんもいてへんし、今日ぐらいは羽伸ばし。さ、はよ顔洗って」
おつかは、ためらう鋒国を追い立てるように立たせた。