人生の良し悪しは生まれた時点で決まっている? 今やすっかり浸透した「親ガチャ」という言葉。『親ガチャの哲学』(新潮新書)はこの言葉に正面から向き合い、言葉が生まれた背景に切り込みます。人生の不平等さ、理不尽さ、それらを背負ってまで生きる価値とは? 生の真理を突き詰めた本書から、「生まれてこないほうがよかった」という思想「反出生主義」のエピソードを紹介します。
※本記事は戸谷洋志著の書籍『親ガチャの哲学』(新潮社)から一部抜粋・編集しました。
食後のケーキを食べられなかったから
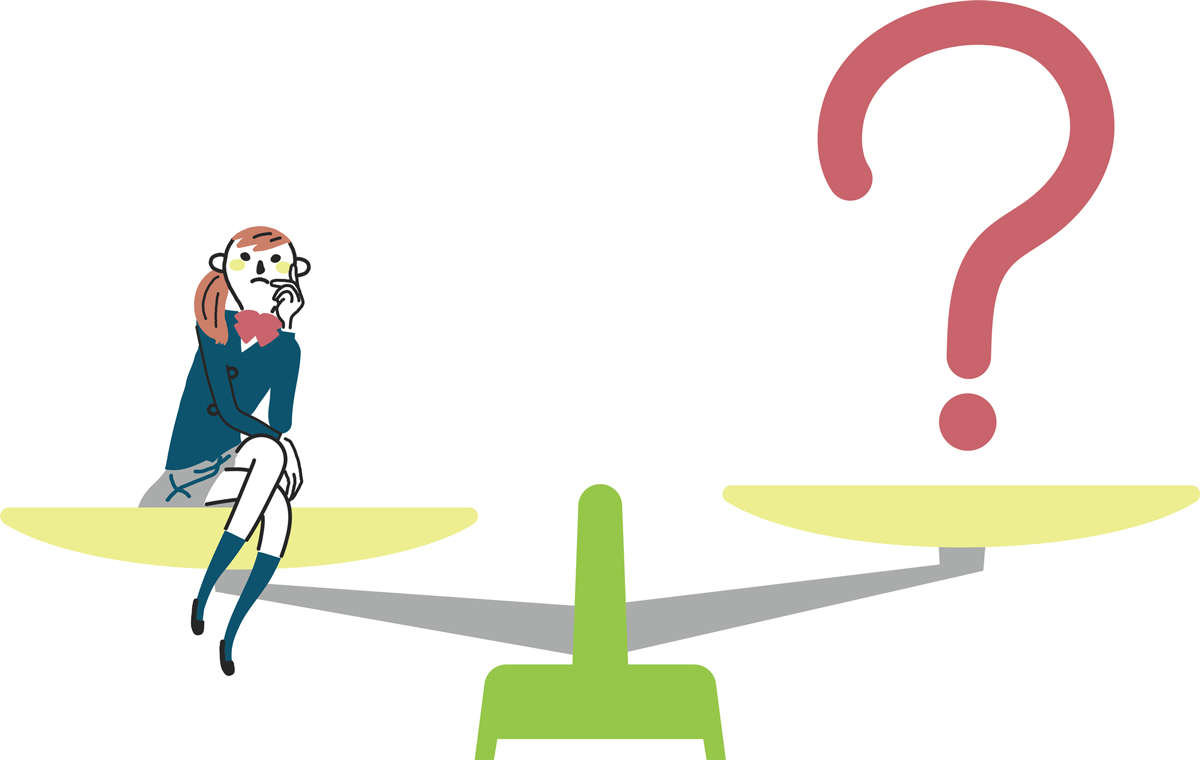
反出生主義などというと、なんだかとてつもなく感傷的で、ペシミスティック(悲観的)な思想であると思われるかも知れません。しかし、実際には、それはあくまでも論理的に導かれた思想です。
提唱者である南アフリカの哲学者・デイヴィッド・ベネターは、まず、快楽があることを「よい」こととして、苦痛があることを「悪い」こととして位置づけます。たとえば、食後に甘いケーキを食べることは、快楽を得られることだから「よい」ことです。それに対して、食後に腹痛に襲われることは、苦痛に見舞われることだから「悪い」ことであると言えます。
快楽があることは「よい」、そして苦痛があることは「悪い」――ではその反対はどうなるでしょうか。つまり、快楽がないこと、苦痛がないことは、それぞれどのような価値を持つでしょうか。
普通に考えれば、価値は反転し、快楽がないことは「悪い」、そして苦痛がないことは「よい」ということになりそうです。ところが、ベネターはそうは考えません。たしかに苦痛がないことは「よい」ことですが、しかし快楽がないことは、「悪くない」とベネターは言うのです。これが彼の反出生主義を考える上での最大のポイントになります。
快楽がないのが「悪い」ではない理由
苦痛がないことが「よい」のは、考えてみれば分かることです。たとえば、食後に腹痛に襲われている「私」が、胃薬を飲んで痛みを和らげたとしましょう。このとき、苦痛がなくなったため、それは「私」にとって「よい」ことです。しかし、快楽がないことはどうでしょうか。たとえば「私」が、何かの事情で食後にケーキを食べなかったとしましょう。これは「私」にとって「悪い」ことでしょうか。おそらく、そうとは言い切れないはずです。
もしも食後にケーキを食べないことが「私」にとって「悪い」ことであるとしたら、それは、「私」がものすごくケーキを楽しみにしていて、それを食べられないことによる絶望が生じるときでしょう。そのとき「私」は、快楽がないことを嘆いているのではなく、絶望という苦痛を嘆いているのです。
しかし、快楽がないことが、いつでも苦痛になるとは限りません。たとえば筆者は、甘いものよりも塩辛いもののほうが好きなので、別に食後にケーキを食べなくても苦痛ではありません。かといって、嫌いなわけではないので、もしケーキを食べたら「ああ美味しいな」、と思います。つまり快楽は感じます。このような人にとって、食後にケーキを食べられないことは、快楽はないけど苦痛もない、という状態のはずです。
では、このように快楽がない状態――特に甘い物が好きではない人が、食後にケーキを食べられない状態――は、「よい」ことでしょうか、「悪い」ことでしょうか。普通に考えれば、どちらでもない、ということになるでしょう。
つまり、苦痛がないことは「よい」が、快楽がないことは「悪くない」のです。この意味で、快楽と苦痛は非対称的な関係にあると、ベネターは主張します。そして、この性質に基づいて、彼はなぜ人間は生まれてこないほうがよいのかを説明するのです。






