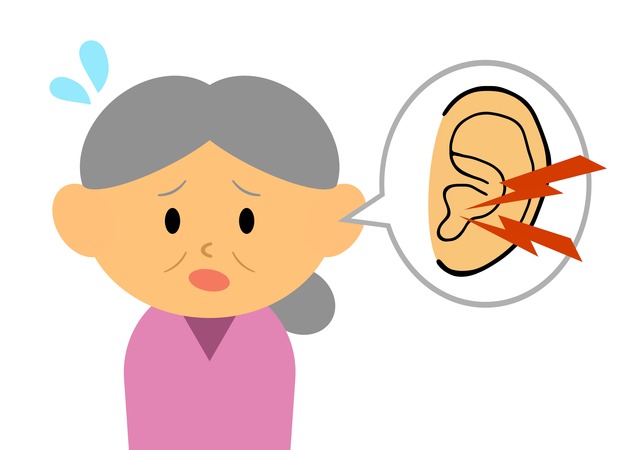「難聴で相手の話が聞き取りにくい」「めまいがつらくて気分までふさぎこんでしまう」など、難聴やめまいに悩む人はどの年齢にもいて、悪化すると生活に支障が出ることがあります。「急に耳が聞こえなくなった」という場合は、すぐに受診したほうがいいことも。難聴やめまいなどの症状や治療法、受診の目安、日ごろの注意点などについて、聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科学教授の肥塚泉先生に聞きました。
 前の記事「感音難聴の原因の一つは、加齢や大きな音を聞くことによる「耳の疲れ」/難聴・めまい(3)」はこちら。
前の記事「感音難聴の原因の一つは、加齢や大きな音を聞くことによる「耳の疲れ」/難聴・めまい(3)」はこちら。
●「突発性難聴」は「ウイルス感染」や「耳の血流障害」が原因だと考えられる
「突発性難聴」はどの年代の人にも発症し、若い人や働き盛りの人に比較的多くみられる難聴です。原因はいまだに解明されていないのですが、「ウイルス感染」や「耳の血流障害」などが原因ではないかと考えられています。過労など肉体ストレスによる免疫低下や睡眠不足が蓄積すると発症しやすいようです。片耳が急に聞こえなくなりますが、耳が詰まったような感じや耳鳴り、めまいなどを伴うこともあります。
発症したらなるべく早く受診することが必要です。時間が経てば経つほど有毛細胞や蝸牛神経などが壊れて元に戻らなくなってしまうからです。発症から2週間以内に治療を開始すると治る可能性が上がりますが、2週間以上経過すると回復が難しくなります。安静を保つために1週間程度入院し、薬物療法としてステロイド薬や血流を改善する血管拡張薬などを使用。聴力が回復するまでには約1カ月かかります。
「人の体のほとんどの臓器は、血流が滞らないように動脈が2系統または3系統など、複数通っているのですが、内耳には動脈が1系統しかありません。さらに疲労があると交感神経が興奮して、内耳の動脈のような細い動脈は収縮して『血流障害』を起こし、蝸牛の有毛細胞に十分な栄養を届けられなくなります。このようなことが原因で突発性難聴を発症する人もいます。日ごろからなるべく休息をとり、疲労をためない生活を心がけます」と肥塚先生。
●「ストレス」から発症する「急性低音障害型感音難聴」も若い人に多い
強い「ストレス」を受けたときに発症しやすいのが「急性低音障害型感音難聴」です。20歳代や30歳代に多く、男性より女性の方が発症しやすいようです。片方の耳の低い音が聞こえにくくなるのが特徴ですが、耳鳴りや耳が詰まった感じがして受診し、この病気だと判明することが少なくありません。「急性低音障害型感音難聴」は蝸牛内部のリンパ液が過剰になるために起こります。
「原因はまだはっきり分かっていないのですが、強いストレスが引き金になっているといわれています。ストレスを受けて蝸牛の中のリンパ液が過剰になり、有毛細胞の働きが悪くなるために起こると考えられています。人間関係や仕事のトラブルで働き盛りの人が発症したり、親に『勉強しなさい』と強く言われ続けている子どもが発症したりするケースがよくあります。なるべく早めに受診します。治療では内耳の血流を改善する薬や過剰になったリンパ液を減量することを目的に利尿薬であるイソソルビドを服用します」と肥塚先生。
●良性腫瘍の「聴神経腫瘍」もある
片耳だけに難聴や耳鳴りが起こるときには、良性腫瘍である「聴神経腫瘍」が原因になっていることがあります。「検査技術が発達していなかった時代には、腫瘍が小脳や脳幹を圧迫し、これらの障害による症状が出るほど大きくなってからでないと発見されませんでした。
いまはMRIで調べられるため、腫瘍がごく小さいうちに見つかることがほとんどです。悪性の『がん』ではないので、治療では手術を行う場合と手術しないで経過観察をする場合があります。すぐに手術をしないときは1年または2年ごとにMRIを撮り、腫瘍の成長曲線を見ていきます」と肥塚先生。
●難聴の疑いがあるときは耳鼻咽喉科を受診
「耳の聞こえが悪いと感じたら、なるべく早く耳鼻咽喉科を受診します。特に、急に聞こえなくなったときは、突発性難聴などの可能性がありますので、すぐに受診してください」と肥塚先生。
耳鼻咽喉科ではまず問診と耳の診察が行われます。問診では「いまどんな症状なのか」「いつから聞こえにくいか」「耳鳴りやめまいなどの症状があるか」などを聞かれます。次は聴力検査です。防音設備のある検査室でヘッドホンをつけて、オージオメータという検査機器から出てくる数種類の音が聞き取れるかどうかを測定。オージオメータから「ピー」という高い音や、「プー」という低い音などが出るので、聞こえたらボタンを押します。この測定で聞こえの程度や、どの種類の音が聞こえにくいかなどを調べます。検査結果は「オージオグラム」というグラフで表され、その結果と症状に応じた治療が行われます。
次の記事「難聴は認知症を招く?補聴器を上手に取り入れると認知症予防につながる/難聴・めまい(5)」はこちら。
取材・文/松澤ゆかり