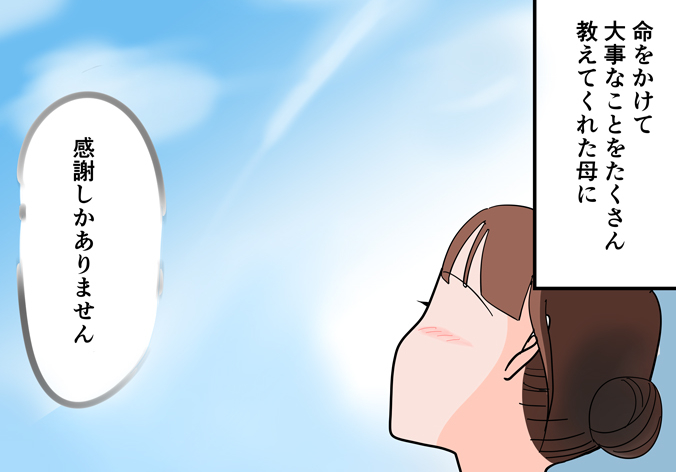親の介護で疲弊する子、こじれる関係...。さまざまな問題を抱える家庭での介護ですが、認知症を患った実父の介護の中で、専門とするアドラー心理学に「親との対人関係上の問題について、解決の糸口を見いだせる」と哲学者・岸見一郎さんは感じたそうです。今回は、そんな岸見さんの著書『先に亡くなる親といい関係を築くためのアドラー心理学』(文響社)から、哲学者が介護者の目線で気づいたことをご紹介します。
【前回】介護の審査で罪悪感。「何でもわかる言うたらアカンのやな」って言ってたのに.../先に亡くなる親とアドラー心理学
【最初から読む】年のせいだと思っていた物忘れは、父に訪れた認知症の現れだった

親が意識から離れない
父が元気で一人で問題なく暮らしていると思っていた時は、私のほうから父に電話をすることはあまりありませんでした。
父のことが意識に上ることもありませんでした。
ところが、父が介護を必要とするようになってからは事態は一変し、父のことを常に意識していなければならなくなり、そのことが介護をつらいものにさせました。
昼間はもっぱら私が行って食事の世話などをするのですが、夜は一人でした。
食後、父が寝るのを確認した上で帰るわけですが、問題はいつもそれから後、朝までの間に起こりました。
私が行くのは大体早い時で七時半、遅くとも八時でしたが、父はそれよりも早い時間に起きていたのです。
父はエアコンの設定が自分ではできないようになったので、ある日、コントローラーに手が届かないようにして帰ったところ、夜中に寒くなったとテーブルに乗って高い所にあったコンセントを抜いてしまったことがありました。
テーブルに乗るなどとんでもない話で、昼間あれほど転倒しないように注意していたことがまったく意味がないと思いました。
また、夜中にあちらこちらの引き出しを開け、中からいろいろなものを取り出したりしました。
それをそのままにしたまま再び寝てしまいました。
しかし、そのようなことも私が父のところへ行く頃には何も覚えていませんでした。
こんなことがたびたびあるので、今頃、何をしているだろうかと夜帰ってからもいつも気になってしかたがありませんでした。
朝行くと、大抵、まだ寝ていました。
一度一人で起きて着替えをして、もう一度寝るのです。
テレビは大音量でついたままでした。
父のところへ行ってすぐにテレビの音が父の部屋から聞こえると安心なのですが、玄関の戸を開けてもいつものようにテレビの音が聞こえずひっそりとしていると、父の部屋の戸を開けるのが怖かったです。
熟睡していると息をしているか心配になったものです。
胸が動いているのを確認するとほっとしましたが、この時の緊張感が耐え難いもので、休みの日に妻が朝一緒にきてくれると、心配が半減するような思いでした。
父が想定していなかったことをあれこれしていた時、私はイライラし、どうしてこんなことをするのかと怒りを感じたこともしばしばありました。
しかし、そのことを後から持ち出しても何も覚えていないわけですから、意味はありませんでした。
朝、必ず父のところへ行かなければならないということも大変です。
私が行かなければ父は食事ができないので、今日は疲れているからといって行かないというわけにはいきません。
夏の暑い日も冬の寒い日も、お盆も正月も父には関係がありません。
私も同じように休みだからといってくつろぐこともできませんでした。
アラームをかけないで寝たいといつも思っていました。
ヘルパーさんらに任せて帰宅できる時には、疲れをとるために寝ることがありましたが、アラームをセットして一時間後には起きなければならないのはつらかったです。
親と同居している人は、夜中にトイレに立つ音がするだけで目が覚めるといいます。
私の場合は、夜は父を一人にできたので、いつ何時、危険な目にあうかわからないと思うと気が休まることはありませんでしたが、父がトイレに立つ気配で目を覚ますということがなかったのはありがたかったです。
しかし、施設への入所が決まってすぐに、父は腰椎圧迫骨折で入院することになりました。
夜中に転倒したのです。
決して、骨折することがないようにと神経質なまでに気をつけていたかいがなかった思いがしたものでした。