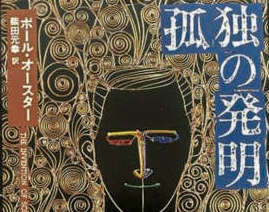定期誌『毎日が発見』の人気連載、哲学者の岸見一郎さんの「生活の哲学」。今回のテーマは「『この人』を愛する」です。

人類を愛せるか
『カラマーゾフの兄弟』の中でゾシマ長老が、ある人の言葉としてこんなことをいっている。
「自分は人類を愛しているけれど、われながら自分に呆れている。それというのも、人類全体を愛するようになればなるほど、個々の人間、つまりひとりひとりの個人に対する愛情が薄れてゆくからだ」(ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』原卓也訳)
人類のためなら十字架に架けられてもいいが、近くにいる人はちょっとのことで憎んでしまう。
「個々の人を憎めば憎むほど、人類全体に対するわたしの愛はますます熱烈になってゆくのだ。と、その人は言うんですな」
はたして、この人のように「人類全体」は愛しているけれども、「個々の人間」は愛せないということはあるのだろうか。
人類を愛しているということと、個人への愛情が薄れることには因果関係はない。この人は個人を愛せないけれど人類は愛しているからと、人類を愛していることを個人を愛せないことの弁解にしているわけではない。それどころか、「個々の人を憎む」とまでいっている。人類への愛が増すので個人への愛が薄れるというのではなく、個人を愛さないために、さらには個人を憎むために人類を愛するのである。
アノニムな人へ愛・憎しみ・怒り
「人類」への愛と「個人」への憎しみが対置されているとわかりにくいが、これが「国家」への愛(愛国心)と「個人」への憎しみであれば、問題の所在が明らかになる。
戦争の場合、敵国に向けての憎しみや怒りが必要である。戦争の相手国に宣戦布告した途端に、相手国に敵意を感じることはない。だから、「鬼畜米英」というキャンペーンが必要だった。
そこまでしないと、国に対して怒りや憎しみを感じることはできないということである。本当に、アメリカ人やイギリス人を鬼畜だと信じ、憎しみを感じた人がいるとは思えないのだが、繰り返し、その言葉を聞かされ、アメリカ人やイギリス人に憎しみや怒りを感じた人がいるかもしれない。そうだとしても「個人」に対して感じたのではない。
怒りや憎しみが向かう先はその国に属するアノニム(無名)な人であり、特定の個人ではない。先に見た人類全体は愛しているけれども個々の人は憎むという人も、実際のところは、アノニムな人にその憎しみは向けられている。
ヘイトスピーチやヘイトクライムの場合も、その憎しみ(ヘイト)の対象は特定の個人ではない。ある国の人全般を憎むことは本来できない。
長崎に原爆が投下された時、その爆圧観測をする観測用ゾンデ(※1)の中に降伏勧告書が入っていた。その最後に、次のように記されていたと林京子(※2)が書いている。
「日本国がただちに降伏しなければそのときは原爆の雨が怒りのうちにますます激しくなるであろう」
一体、誰の誰への怒りなのか。
「殆どの私たちには、なぜ怒られるのか理由さえつかめず...」
「浦上には人間が住んでいた。人間の臭みに満ち満ちた、人間らしい街だった。そして、十万人に近い人間があの土地で死んだ。そこにいあわせた私たちが、どんな悪い罪を犯したというのだろう」(『祭りの場・ギヤマン ビードロ』)
実際にはアノニムな人に向けられたものでしかない憎しみや怒りを掻き立てるためには、敵国への怒りや憎しみを増長させるのではなく、自国への愛、愛国心を増長させるという方法もある。
ゾシマ長老が引くある人は「個々の人を憎めば憎むほど、人類全体に対するわたしの愛はますます熱烈になってゆくのだ」といったが、個人を憎んだから人類全体への愛が熱烈になったのではなく、個人を憎むために人類全体を熱烈に愛したのだ。戦争時には、愛国心がアノニムな敵国の人への憎しみや怒りを掻き立てるために使われる。
本来、愛も憎しみも怒りも目の前にいる人にしか向けられない。目の前にいるこの人を愛し、怒りを感じ、憎むのである。この個人間に起き、各人が自発的に誰かに対して持つ感情が個人を超えたものに適用される時、個人は利用される。
鈴木貫太郎首相が戦時中「国民個人の生命は問題にあらず。我国体を護持せねばならぬ」といったと渡辺一夫(※3)が日記の中に書いている(『敗戦日記』)。愛国心、そして敵国への憎悪心を持った国民は、国家のために戦っているはずなのに、実際に政府は国民個人の生命など少しも問題にしていないのである。都会という都会が焼き払われ、住民が皆殺されるか山に追い払われた時、「我が親愛なる国体何処にありや?」(前掲書)と渡辺は日記に記している。
※1 マイクや発信機を備えた観測機器。
※2 1930~2017年。小説家、随筆家。
※3 1901~1975年。フランス文学者、評論家。
アノニムでない個人に向き合う
実体のないアノニムな人や国家、さらに人類に愛を向けてはいけないのである。それと同時に、愛は特定の人にだけ向けられるのではないことを知っていなければならない。
電車の中で困っている人を見たら、相手が誰かに関係なく救いの手を差し伸べようとするだろう。その人の中にどこの国の人であるかに関係なく、ヒューマニティ(humanity)、自分と同じ人間性を見るからだ。
ヒューマニティは「人類」という意味もあるが、誰であっても助けようと思う相手は決してアノニムな人ではない。アドラーが次のようにいっている。
「中国のどこかで子どもが殴られている時、われわれが責められるべきだ。この世界でわれわれと関係がないことは何一つもない」(Phyllis Bottome, Alfred Adler)
この少年は目の前にはいないが、決してアノニムな人ではない。少年が殴られたことを我が身のこととして感じられるのは、自分と他者に共通するもの、人間性を分有しているからである。その時、フロム(※4)の言葉でいえば「私はあなた」になる(The Heart of Man)。これがアノニムな人を対象としない真の人類愛である。
※ 4 エーリッヒ・フロム(1900~1980年)。社会心理学者、精神分析学者。