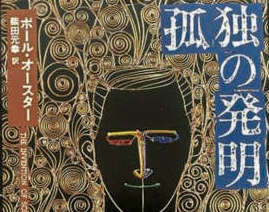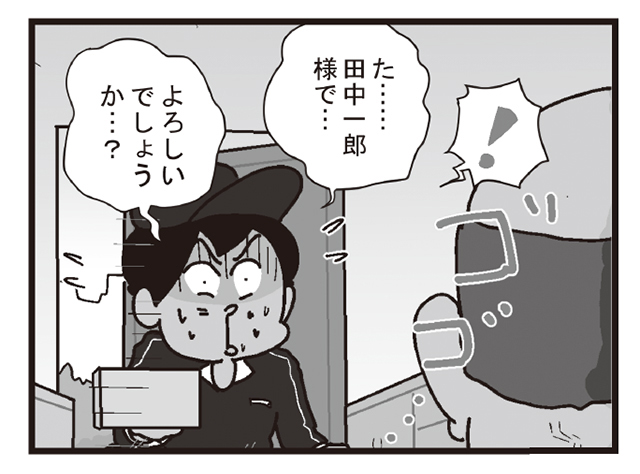定期誌『毎日が発見』の人気連載、哲学者の岸見一郎さんの「生活の哲学」。今回のテーマは「対人関係の中での決断」です。

なぜ決断が難しいか
自分の身に何かつらいことや苦しいことが降りかかってきた時に、嵐が過ぎ去るのを待つように何もしないでいれば、多くの場合、事態はいっそう悪くなる。
自分で決めなくても、他の人が決める。放ってはおけないからだ。他の人が決めたために自分の望むようにならなかったとしたら、自分で決めなかったのだからと諦めることはできない。自分で決めなかったことを棚に上げて、他の人が決めたことを不満に思ったり、怒ったりするだろう。そうであれば、決断を誰かに任せてはいけないのだ。
自分で決断するとしても問題を解決するためにできることは限られている。選択の余地がなければ、するかしないかだけを考えればいい。
何をするかを選ぶことができるとしても、どれも選びたくない、あるいは選べないこともある。決断をためらうのは、決断の結末は自分に降りかかり、決断に伴う責任を引き受けなければならないからである。
問題は、自分の決断が、他者にも何らかの仕方で影響を及ぼすことである。誰もが自分の人生を生きる権利を持っているが、一人で生きているわけではないからである。
さらには、決断の結果、自分だけが苦痛を受けるのならまだしも、他者を苦しめ、時にその生命をも脅かすこともありうる。そのような時、決断は苦渋に満ちたものになる。
『トンネル』という韓国映画がある。その中で、夫がトンネルの崩落事故で埋められ、生死がわからないまま救出作業を中断し、トンネルの近くにある第二トンネルの工事を再開することに同意してしまった妻が、その決断をしたために苦悩する場面が出てくる。中止を拒めば夫を救助する人に新しい犠牲者が出るかもしれない。加えて、建設が滞ると経済的に大きな損失がある。国民の多くが救助を中止することを求めているといわれ、妻は同意しないわけにいかなかったのである。
妻は自分の決断によって、夫の生命が失われる、もしくは、もう既に生命が失われていることを前提に決断しなければならない。このような決断を強いられた時に、はたして正しい決断ができるかといえば難しい。このようなことになる前にどうするかを決めておいたらよかったと思っても、誰も事故に巻き込まれることなど考えないだろう。
決断を下すべき本人に代わって他の誰かが決断しなければならないことは、この映画のような特別の場合でなくても起こる。
例えば、自分では意思決定ができない認知症の親の代わりに、家族が延命治療を継続するか中止するか決断しなければならないことがある。家族が延命治療を望んでいても、医師が中止することを勧めることもある。
父が入院した時、延命治療をどうするかと医師に問われたことがあった。私は父がまたすぐに退院できると思っていたので、不意打ちのような医師の問いに戸惑った。父はその時もはや自分では意思決定ができない状態だった。「穏やかに着地させてほしい」と私は答え、延命治療を断ったのだが、その決断が正しかったのか長く悩まなければならなかった。
このような場合、親の代わりに家族が下す決断を親が望んでいるかわからないので、どんな決断をしても必ず後悔することになる。決断したその時には正しい決断をしたと思えても、時間が経てば間違っていたかもしれないと思うかもしれない。
『トンネル』の場合、夫が生きているという一縷の望みを捨てることができなかったからこそ、救命作業中止の決断ができなかったのである。
親も生きたいと願っているかもしれないと思うから、たとえ元気だった時に、延命治療はいらないといっていたとしても、延命治療を中止する決断ができないのだ。反対のこともある。元気だった時に、延命治療をしてほしいといっていた親が実際延命治療が必要な状態になった時、延命治療をしたくないと思っているかもしれない。そうであれば、延命治療の決断は親のためにならない。
決断できるために
どうしたら決断できるだろう。
まず、どんな決断をしても必ず後悔する、そう思っておけば、決断することができる。絶対的に正しい決断をすることはできないとしても、その時々に最善の決断をすることはできる。後悔しなくても、状況は変わっていくので、最初の決断に固執しなくていい。最初決断した時には選択肢になかったことを選べるようになることもある。必要があれば修正していいのであり、修正しなければならない。一度決めたからと最初の決断に固執することは、事態を悪化させる。
他者に代わって決断する場合は、どんな決断をしても、必ず非難する人がいることを知っておかなければならない。だから、決断する時に、他者からどう思われるかは気にしてはいけない。顔色を窺ってばかりいれば何も決められない。決断する時には、孤独でなければならない。
次に、意思決定ができない親に代わって決断する場合には、どんな決断をしても許してもらえるという信頼感が必要である。
大地震があった時、夫と妻が瓦礫に埋もれてしまった。妻はその後瓦礫から抜け出すことができたが、夫は足を挟まれ身動きが取れなかった。そのうち、火の手が迫ってきた。夫は「この足を切ってくれ」と妻に懇願した。
そんなことをいわれても、妻が夫の足を切断することなどできない。いよいよ火の手が迫ってきた時、妻は夫をその場に置いたまま逃げた。妻は助かったが、夫は焼死した。誰もこの妻の決断を責めることはできない。
夫はどう思っただろう。二人の関係次第である。関係がよかったら、妻だけでも逃げおおせたことを喜んだだろう。誰もが納得できる合理的な決断をするのは不可能に近い。事故に遭ったり、病気で倒れるのは突然だが、よい関係を築くことは普段からできる。