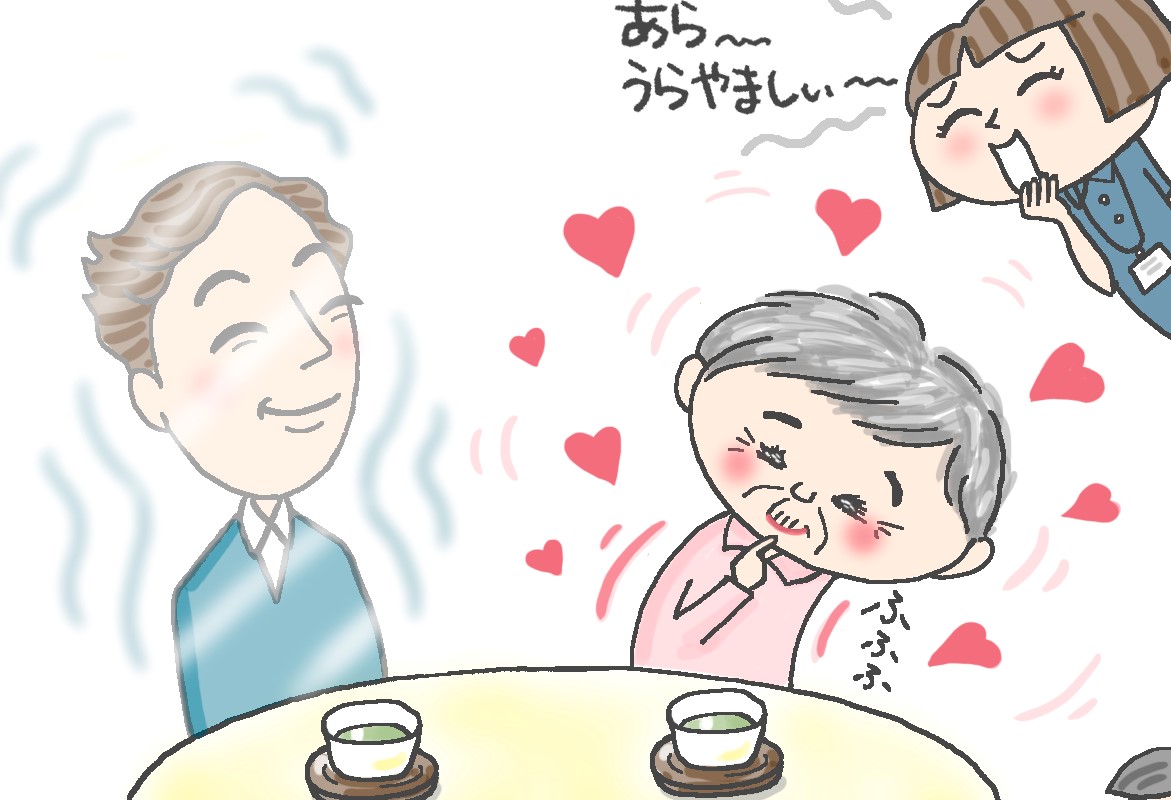『毎日が発見』本誌で連載中の哲学者・岸見一郎さんの「老後に備えない生き方」。今回のテーマは「他者の死をどう受け止めるか」です。
 前の記事「「命にかかわる病気をどう告げるか」/岸見一郎「老後に備えない生き方」(1)」はこちら。
前の記事「「命にかかわる病気をどう告げるか」/岸見一郎「老後に備えない生き方」(1)」はこちら。
今できること
今も時折、多くの人が亡くなった阪神淡路大震災のことを思い出すことがある。こんな話を聞いたことがある。
「あの日、私は息子が受験勉強に疲れ、居間の炬燵で居眠りをしているのを見て、起こすのはかわいそうだと思い、そのまま炬燵で寝させた。いつもは『そんなところで寝たら風邪を引くよ』と二階の部屋へ無理矢理連れて上がっていたのに。翌朝、あの地震。二階は崩れ落ち、子どもは階下で押しつぶされた」
この話をした人は「あの子は私のせいで死んだ」と自分を責めた。
もちろん、その人のせいなどではない。しかし、人生には、こんなことが起こるのだ。こんなことを経験すれば、誰もが自分を責めるだろうし、悲しみから立ち直ることは難しいだろう。
それでも何ができるかといえば、このような形で別れることがわかっていたら、あの時あんなひどいことをいわなかったのにという後悔をすることがないように、共にいる時に諍(いさか)いをせず、仲良く生きることである。
悲しみが癒えるまで
読者からの相談を見てみよう。
「主人と長男を一年のうちに亡くし、失意に陥りました。それから十年余りが過ぎましたが、まだまだ悲しみは癒えません。亡くなった人への思いを整理できない自分がいます」
「五月中旬、夫が亡くなりました。夜淋しくなるのをどうしたら紛らわすことができるのでしょうか?」
悲しみはなかなか癒えない。
私の母が亡くなったのは私が二十五歳の時だったが、当時、四十九歳の母の死を受け入れることはすぐにはできなかった。
母が死んでまもなく結婚したが、妻と二人でいる時、私のものでも妻のものでもない息の音が聞こえてくることがあった。今もそれが亡くなった母の息だったと信じている。
本当にそうだったかはわからない。
幻聴といわれるかと思って誰にもいわなかった。その後も長らく母は度々私の夢に現れた。母の夢を見なくなったのは、母が死んでから十年も経ってからのことだった。それほど私は母への思いを断ち切ることができなかったのである。
死んだ人の夢を見るというのは、死んだ人との関係の中でやり残したことがあるということである。それがすべて清算できた時に、死んだ人はもはや夢の中に現れてこなくなる。それはそれとしてまた悲しいことではあるが、いつか死んだ人から自由にならなければならないのである。
死んだ人をもはや知覚的に知ることはできない。身体に触れたり、姿を見たり、声を聞いたりすることはできないということである。
生きている人の場合でも、知覚だけで知るだけではない。例えば、その人の書いた文章を読んで、その人を知るということがある。遠く離れた友を思い出す時、その人を知覚的に知るわけではない。亡くなった人を思い出す時も同じである。
亡くなった人のことを思い出す時、その人は「ここ」にいる。記憶の片隅に残された、今となってはセピア色に変色した古ぼけた面影が蘇ってくるのではない。その人が「今」まさに「ここ」にいるのである。亡くなった人が今も私の心の中に生きているというのは比喩ではないのである。
今ここを生きる
「私は二人姉妹ですが、妹が今入院中で、残り少ない余命。どう声をかけたらいいのか、私も無念で顔を合わせてもつらい。何だか、どうしたらいいかわからないです」
このような時、どんな言葉をかけたらいいかは誰にもわからないが、今のこの状況でどんな言葉をかけていいかわからないということを率直にいうことはできるだろう。
誰しもいつまでも一緒に居られるわけではない。できることはその別れを最善のものにすることである。今日一緒に過ごせるのであれば、これからのことを思って不安にならず、共に笑い、時には泣いて過ごしてほしい。
「夫は食道癌ステージ3と診断されました。抗がん剤と放射線治療が終わり、現在はこれまで通りの生活をしています。三度の食事を取り、晩酌に清酒二合を飲みます。囲碁を楽しみ、普通車の運転もします。本人は後三年も生きれば本望だと達観しているように思いますが、時々ヒステリックになる場面もあります。私は今後どのように接していけばよいか不安です」
病気の前と変わらない生活をすることについては心配もあるが、本人がそうすることで時に感情的になることはあっても大半は機嫌よく過ごされているのであればそれでよしとしていいと私は思う。今日という日を共に過ごせることを喜び、毎日を丁寧に生きれば起こることは起こり、起こらないことは起こらない。
今後、食事が今のようにはできなくなることがあっても、あの時、節制をしなかったからこうなったというようなことをいわないことが必要である。これも過去を手放すということである。
生き残ったことの受け止め
「九年前に胃癌の手術、胃の3分の2を切りましたが、生きている自分と同じ病での友人、知人の死...その違いは何だろうと思う時があります。この九年の間に両親、親戚、友人が癌などで亡くなりその度に、フッと私は生きていていいのと思います。そして...生きていて幸せ、よかった、大切に過ごそうと思っています」
50歳で心筋梗塞で倒れた時、主治医がなぜ自分がこの病気になったのかという思いが出てくるだろうと私にいったことがあった。たしかに、生還して少し落ち着くと、自分は酒も嗜(たしな)まず、喫煙もしないのに、また、こんなに若いのに、なぜ自分が心筋梗塞にならなければいけなかったのかと思ったことがあった。
しかし、このようなことをどれほど考えてみても、今病気になってしまったのだから仕方ないということに思い当たった。
なぜ私は助かったのかと思う時も同じである。なぜ同じ病気なのに自分は助かり、他の人は助からなかったのかといえば、誰にもわからない。事故や災害の時も同じである。そうであれば、助かったという現実から考えるしかない。
マルクス・アウレリウスというローマ皇帝が『自省録』の中で次のように書いている。
「既に死んでしまった者のように、今までに生を終えてしまった者のように、今後の人生を自然に即し、余得として生きなければならない」
あの時、死んでいたかもしれない。しかし、今こうして生き長らえたのであれば、これは「余得」なのだ。たしかに、私もアウレリウスがいっているのと同じように考えたことがあった。
回復の兆しが見え始めた頃、私の主治医は「本は書きなさい。本は残るから」といった。私はこれからは本を書いて生きていこうと思った。そう思うことが生きる励みになっている。
「私は震災で母を亡くし、故郷もなくしました。これから一体、どのように考えて私は生きていけばいいのでしょうか」
私の講演を聞いた後でこのようにたずねた男性に私は先に引用した小説の中の言葉を紹介した。
「あの世とは、いいところらしい。逝ったきり、誰も帰って来ない」
それを聞いて彼は答えた。
「きっと母もいいところへ行ったのでしょうね。それなら、私も早く母の元へ行きます」
「いえ、それはまだ早すぎます。あなたには仕事が残っています。それからでいいのです。お母様はいつまでも待っておられます」