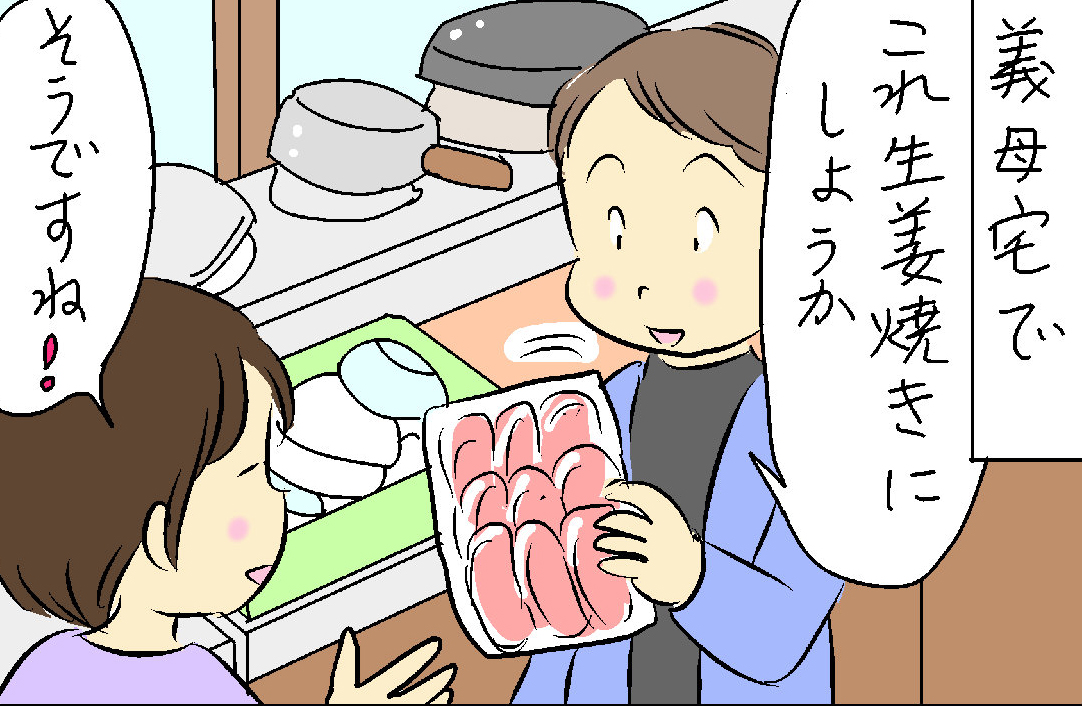『魔女の宅急便』をはじめ、多くの児童文学作品を手がけてきた角野栄子さんに、自伝的新刊『イコ トラベリング 1948―』についてお話を伺いました。

結婚後にブラジル移住
不安よりワクワク感
――代表作『魔女の宅急便』をはじめ、多くの作品を手がけてきた児童文学作家の角野栄子さん。新刊『イコ トラベリング 1948―』は『トンネルの森 1945』(2015年)に続く自伝的物語。前作では母を亡くした10歳のイコのまなざしを通して戦争が描かれましたが、新作の舞台は終戦後。押し寄せる欧米文化にカルチャーショックを受ける13 歳に始まり、夢を追いかける26歳まで。まさに青春真っ只中のイコが輝いています。
比較的、イコと自分が重なる部分が多いのでちょっと恥ずかしい(笑)。
昔といまでは違うから、若い方が読んでどう思われるかも、少し心配でした。
――進路への迷いや淡い恋など、誰もが経験することが書かれていて共感しました。
私としては、ただ読んで楽しんでくださればいいなと思っています。
10代の少女が不安を感じたり、失敗したり、思わぬ方向に自分のやりたいことを発見したりして、成長していく物語です。
主人公のイコがブラジルに旅立つ経験は、私自身の経験でもあって、24歳で自費移民という大きな決断をしました。
"女は結婚するのが当たり前"という時代で、私の父もしょっちゅうそう言ってました。
でも、いざ結婚したら意外と親は自由にさせてくれるものです。
相手に責任転嫁できますからね(笑)。
デザイナーの夫が、建設中だった「新しい都市ブラジリアが見たい」というので、私も大賛成。
私もどこかへいきたがり屋だったので心配や不安より、ワクワク感の方が強かったですね。
ブラジルでの生活は、働いてまず当座の生活費を稼ぐことを考えなくてはなりません。
英語は少しできても公用語のポルトガル語はぜんぜんダメ。
最初は外資系の会社に英文を打つタイピストとして雇われたのですが、すぐにクビになりました。
そんなときに、短波放送の関係者からお話があり、日本人向けの番組を作ることになって、私がそのスポンサーを探してくれば、その広告料の25%を払うというのです。
若い頃って、何も怖いものがないですよね。
スポンサーを探すために、大きな会社にアポなしで飛び込んで、「ポルトガル語はできないから、英語のできる人と会いたい」と直談判しました。
そんなこと日本だったら、まず門前払いでしょ?
でも、ちゃんと英語の話せるそこそこの肩書の方が出てきて話を聞いてくれて、契約してくれたんです。
ブラジルは移民の国だから、言葉ができないことに関しては寛容、オープンマインドですね。
ただし相手から信頼されたら、こちらもそれを裏切らないようにしなきゃ。
とにかく一生懸命やりました。

「来年に開館する文学館(江戸川区角野栄子児童文学館)の準備もいろいろあって大変。講演に出かけることもありますから。でも、仕事で外出をする日以外は、毎日、机に向かって何かを書くことは続けています。やはり、一番好きなことですから」
家事と子育てに専念した日々
――ブラジルに2年滞在後、帰国。日本でのお仕事は?
海外に輸出する日本映画の翻訳などをアルバイト程度にしていましたが、数年後、娘が生まれたので、彼女が4歳ぐらいになるまでは、家事と子育てに専念しました。
子どもを育てる喜びは、もちろんありました。
でも、小さい子と2人でずっと家にいると、ひとりの人間として孤独を感じることもありました。
当時は高度経済成長期で、夫は仕事に忙しく、留守がちでしたから、いま言われている「イクメン」(積極的に子育てに関与する男性を表す)とはほど遠い毎日でした。
そんなときに大学のゼミでお世話になった先生から「ブラジルでの経験を児童書にしてみないか?」とお誘いを受け、恐る恐る書き始めました。
これが最初の執筆作業でした。
それまで自分が書くなんて、思ってもいませんでした。
――『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』で作家デビューしてから、次作『ビルにきえたきつね』まで7年間のブランクがありますが?
その間もずっと書いてはいました。
デビュー作を一生懸命に書いているうちに"私は書くのが好きだ"と分かったから。
プロになるとかではなく、ずっと書き続けようと思いました。
自分が楽しいと思うものを書いていれば、世界は広がる。
そうすれば"一生、退屈しないでいられる"と思いました。
でももし、自分で納得いくものが書けたなら出版社の方に読んでもらおうとも思っていました。
ですが結局、7年間は誰にも見せませんでした。
せっかく"面白さ"を獲得して楽しく書いているのに、誰かに何かを言われて気分が萎えるのが怖かった。
ひとりで書いている分には、自分が基準ですから。
でも2作目の『ビルにきえたきつね』が出版されると、7年間に書きためたものに少し手を入れて、本にしていただきました。
作品を書くリズムというものが、自分の中にできあがるまでに、7年かかったというこということだと思います。
『魔女の宅急便』のアニメ映画化で、作品が世界中に知れ渡ることに
――『魔女の宅急便』がアニメ映画化。世界的に注目を集めたことは転機に?
宮崎駿監督にはとても感謝しています。
映画のブレイクによって『魔女の宅急便』というタイトルが世界中に知れ渡りましたから。
それによって原作を読みたいという方も増えて、ラッキーな出会いだったと思っています。
ただ、映画『魔女の宅急便』は宮崎さんの作品ですし、舞台化されたミュージカルは演出家・蜷川幸雄さんの作品なの。
私はそう考えています。
――ご自分の生活や、周囲の変化はありましたか?
成功って、とかくお金に結びつけたがるでしょ。
作家も印税がたくさん入るとかって(笑)。
でもお金や地位より、自分の楽しみを見つけて、いろんなことを想像して心を広げていく方が私には大切。
もちろん経済的に自立すれば、仕事も心も充実する。
それはそれで素晴らしい、自由になれていいと思います。
それでも、デビューから50年以上たって、新作に向き合う度に、壁にぶつかって書けなくなり、乗り越えなきゃ、ということはしょっちゅうありますよ。
物を創るということは、そういう苦労も含まれているものだと思っています。
ですが私はそこで書くことをやめようとは思いません。
書くことが好きですから。
必ず机に向かって、手紙だけでもとか、心に浮かんだこととか、書くことをやめないでいるうちに、だんだん執筆の方に移っていく。
私は、コツコツやる職人タイプなのかしらね。
何かがひらめいてパッと書くタイプじゃないんです。
――同じく児童文学作家になられた娘のくぼしまりおさんが"専属スタイリスト"とか。とても仲良しですね。
互いに思い合っていますが、絶えず話し合ったりはしません。
まあまあの関係です。
一緒に台所に入るとケンカになるし(笑)。
でも、洋服のことは彼女のセンスに助けられています。
彼女も、"これなら親孝行ができる"と思ったんじゃないでしょうか。
私の体形や好みに合わせてワンピースを考えてくれています。
とても動きやすくて歩くのも楽。
洋服のおかげで、私の元気の源である大好きな散歩も、無理なく続けています。
物語をあてもなく書くのが好きなように、あてもなく歩くことが好き。
なんでも決めてかかると、それしか見えない。
でも、決めなければ、ふっと現れたものが心の隙間みたいなところに入ってきて、驚いたりワクワクしたり。
今後もそういうことを見逃したくはないですね。
取材・文/金子裕子 撮影/馬場わかな(「角野栄子の毎日いろいろ」「魔法のクローゼット」より)