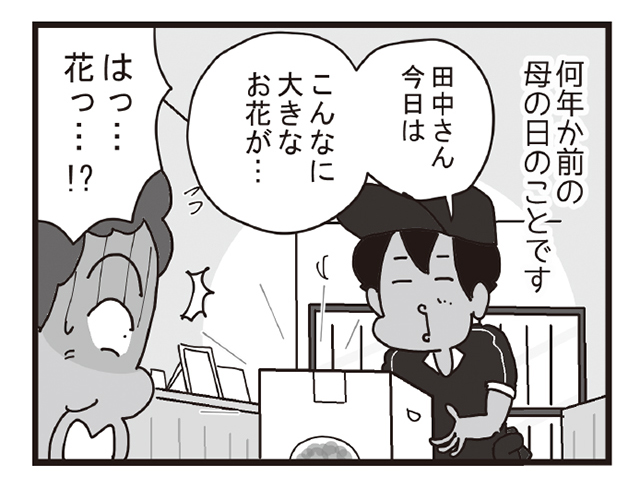沢田研二さん主演の映画『土を喰らう十二ヵ月』で、初めて映画の料理監修を務めた料理研究家の土井善晴さんにお話を伺いました。
季節にある本当の食材はそのままでおいしい
――沢田研二さん主演の映画『土を喰らう十二ヵ月』で、初めて映画の料理監修を務めた土井善晴さん。料理研究家として日本の食を知り尽くす土井さんの手による料理の数々からは、素材を生かしシンプルながらも「土を喰らう」つまり「山で暮らし季節にあるものを食べる」ことの豊かさが、スクリーン越しにも感じられます。
ツトム役の沢田研二さんも相手役の松たか子さんも、普通のものをきちんと料理して食べている方だなって、お会いしてすぐに分かりました。
私はフードスタイリストではないし、映画に関わることもこれが初めて。
そもそも食べるシーンはあっても料理をする暮らしを取り上げることはあまりなかったと思います。
ですから監督がどういったことを求めているのか、そして原案の水上勉さんの『土を喰う日々 ―わが精進十二ヵ月―』の料理をどのように捉えられているのか、全く分からなかったんです。
そこでまず私が料理について思うことを中江裕司監督に時間を使ってお話しさせていただきました。
現代のあれがうまい、これがうまいという話とは、全く違うことで、人間はどんな思いで生きているのかを、料理を通してよく考えるということです。
料理は人間の背骨そのものなんです。
人間は料理する動物です。
動物は食べるだけですが、人間は料理して食べる。
人間であるためには食べることより、料理することの方が大切だと思うのです。
結局料理する人が地球と人間をつなげているんです。
そんな当たり前のことですが、いまでは料理する人を大切にしていないでしょう。
だから、多くの人は料理なんてしなくてもいいと思っている。
ツトムのように料理することは自分を見つめ大切にすることですが、同時に地球を大切にしています。
みんなつながっているんです。
中江監督もそのような考えを持たれていたと思うんですが、話すことで共有できました。
――そのような料理観は土井先生が一貫して持っていたものですか?
フランス料理をやっていたときはフランス料理が世界一やと思っていましたし、日本料理をやっていたときも、もちろん誇りを持ってやっていました。
でも、いま考えるとフランス料理も懐石料理も架空の自然を作り上げる世界です。
プロの仕事をしているうちは考えたこともありませんでした。
プロの仕事に対するものとして"家庭料理"と言っているわけですが、本来全ての「料理」は家庭料理です。
人間が生きていくための原初の純粋な料理を考えるようになったのです。
そのきっかけは、父(料理研究家の土井勝氏)がやっていた料理学校に戻らないといけなくなったことなんですが、最初は「なんで私が家庭料理やねん」と葛藤がありました。
ですが、家庭料理と向き合い、折々の季節に地元の人たちと山に入る経験を重ねて、だんだん分かってくるんです。
日本料理では、縁起の良い「はしりもの」を使います。
初ものを喜ぶのですが、日本の旧暦では4、5、6月が夏ですから、それを新暦(6、7、8月)でやるわけです。
そんなことでしたから、本当の旬を知らない。
山で会ったおじいさんから山うどを食べさせてもらったとき「こんなおいしいものがあるのか」と衝撃を受けました。
おいしさというのは技術の先にあるものではなくて、自然と深く接して、自然を知るところにあるとだんだん分かっていくんです。
おばあちゃんは煮物が上手だってよく言いますが、いつ何を料理するかを知っていたということなんですね。
それと深く料理を考えるようになったのは、毎日の料理に女性が苦しんでいることを知ってからですね。
料理人でも献立を考えるのは大変なのに、女性は仕事をしながら、子育てしながら毎日「今晩何作ろう」と家族を思って考えて料理するのです。
それに食卓におかずをいっぱい並べるのがいいお母さんだと思い込まされてきたのだから、大変なことでしょ。
――その背景があって「一汁一菜でよい」という提案をされたわけですね。
プロが料理するのは厳しいものでいいのですが、家庭料理が苦しみになったらいけません。
毎日のことだから楽しみであり休息であり体を整えるもので、家族の安らぎがないといけません。
フランス人だったらフランスパンとチーズと温かい野菜スープ、大人だったらそれにワインがあれば十分。
そういう料理の基本スタイルが世界中どの民族にも必ずあります。
日本人の場合はそれが一汁一菜で、ごはんと味噌汁と漬物、それだけで栄養がとれるようになっているんです。
気持ちにお金に時間に余裕があれば、何かおかずを作ればいい。
余裕もないのに作らなくても良い、一汁一菜でノルマ達成。
一生懸命やる、それで家族は文句は何もないはずです。
料理して食べることが暮らし、それを持続可能にするものが一汁一菜。
季節に沿って生きれば変化があり、自然が折々にご褒美を用意してくれます。
もののあはれを知っている人の映画
――映画では、旬のものを盛り付ける器にも目を奪われました。
器一つ決めるのもぎりぎりまで監督と考えました。
あらゆる意味を重ねて、場にふさわしいものを一つ選ぶんです。
最後にえいやと選んだ器は中江監督も私も、これしかないという感じです。
映画が中心になって、映画に関わる人たち全員の心が一つになってゆく、できることのベストを尽くす現場、そこにいられたことは本当に幸せでした。
使っている器なんかは民藝(みんげい)、つまり暮らしの道具。
家庭料理と民藝は兄弟みたいなものです。
民藝というのは、つまり美しいものは人間の暮らしの中から生まれてくるものだということ。
当たり前の暮らしの中に、美しいものが身近にあります。
パックに入る前の豆腐を半分に切ったら真四角になった、それをまあるいなます鉢に盛ったら、丸に四角、ネギと生姜をのせたらいい景色ができるんです。
それを見て「ああ、いいな」と感じることを、私たちは喜べるはずなんです。
なんでもない日常の人の気持ちを受け取ってうれしくなることを「ものよろこびする」って関西ではよく言います。
それは水上勉さんの生活も一緒で、風が吹いても幸せになれることを知っておられたと思いますよ。
自然を受け取るところに本当の幸せがあるんです。
人間は自然の一部。
山で暮らすツトムは自然と一つになっていくんですね。
それが生きるいうことです。
そのへんが、えらいうまいこと描かれていて感動しました。
都会に住む私たちの暮らしは、生きづらいこともあるし、それを紛らわそうと思ったら、余計に大変になっていく気がします。
本来の生き方というか、普通はこんなんやったなあと、映画を見て感じていただいたら、ちょっと料理してみようという気になってもらえるかもしれません。
そんなきっかけ、気付きになれば本当にうれしいと思います。
日本には季節があり時々においしいものがたくさんありますから、スーパーで見つけて料理してください。
冬になったら根のもの、春になったら芽のもの、そんなことを意識してみてください。
それは自分の心にくさびを打つこと。
また一年経ったって分かるんです。
それが「もののあはれ」という言葉です。
難しいことやなしに、ええなあと思ってくれはったら、そんでいいと思います。
取材・文/鷲頭紀子 撮影/吉原朱美