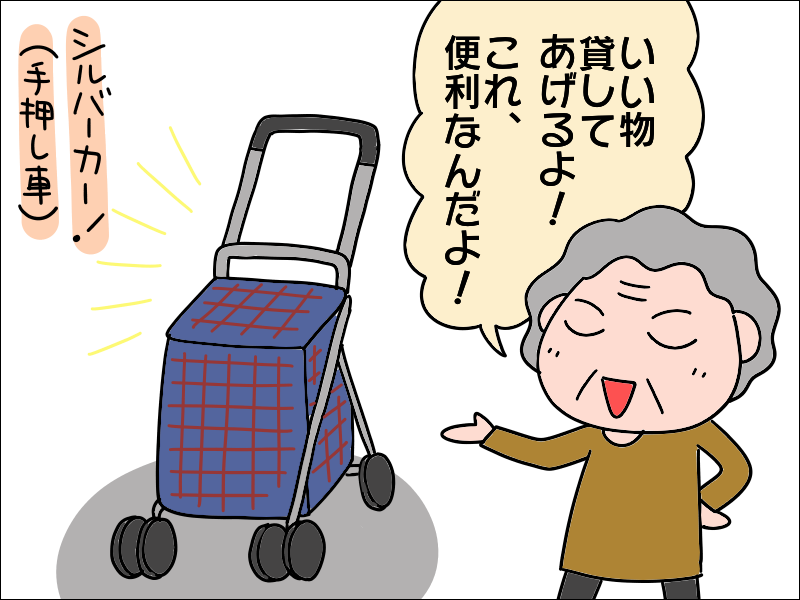沢木耕太郎が89歳の時に脳出血で倒れた父親の介護をした時のことを書いています。
沢木は、病床の父親のそばにいた時、自分がひどく疲れていることに気づきました。
何もしないでただベッドの脇で椅子にすわっているだけなのに、原稿書きなどで徹夜した時よりもはるかに疲れるというのです。
「深くて重い、鈍痛のような疲労」(沢木耕太郎『無名』)。
それはただ待つということからくる疲労感であり、何を待つのかわからず、ただ待つことができないことからくる疲労感です。
沢木は、朝がくるのを、時が過ぎていくことをただ待つといっていますが、ただ時を待っているのではなかったのを知っていたことでしょう。
「私の思いは複雑だった」(沢木、前掲書)
父はこのままただ死を待つことになるのか。
なんとか生かしたい。
しかし人には死すべき時というのがあるだろう。
「漠たるものではあったが」今が父の死すべき時なのではないか。
そう沢木は思いました。
私の父の場合はこのように出口が間近に見えているわけではありませんが、「死を待つ」という点においては、沢木の場合と同じです。
介護は父の時が初めてではありません。
母が脳梗塞で亡くなったのは、私がまだ大学院生の時でした。
当時、妹は既に結婚し、父は仕事があったので、時間が自由になる私が病院に行き、母の病床にいるという日が続きました。
休みの日は代わってもらいましたが、平日は毎日16時間母の側にいました。
「いた」のであって、介護をしていたわけではありません。
これは今から四半世紀も前のことなので、その頃介護という言葉が一般的だったかもわかりません。
私がしていたのは、看病というわけでもありません。
なぜなら母は入院していたのであり、しかもICUにいて、すべてのことは医師と看護師がしていたからです。
当時は完全看護ではない病院があったということなのでしようが、毎日病院にいるようにいわれたのは、母がいつ何時死ぬかわからず、もしもの時に家族が近くにいることを病院から求められていたのでしょう。
実際、病気は予断を許さず、三カ月の闘病のうち後の二カ月は意識がまったくありませんでした。
このように実質的には何をするわけでもなかったのに、母の病床に居続けることで私は疲れ果て、ある日、こんな状態が後一週間続いたら私が倒れてしまうと思いました。
この時期、私は、自分では認めたくはなかったのですが、母の死をずっと待っていたのです。
そんなふうに思ってしまったということです。
そんなことを少しでも思った途端、ひどい罪悪感にとらわれたのも本当で、結果的には、私がこんなことを思ってほどなく母は死に、病院での暮らしには終止符が打たれたのでした。
もちろん、私が後一週間この状況が続けば倒れてしまうと思ったことと、母の死には何の因果関係もありません。
しかし、そんなことを考えるほど追い詰められていました。
母が死ななくても、もしもその後も病院に居続けていたら、自分も他の人も私が母の近くにはいられないと納得できるような、例えば何かの神経症になっていたかもしれないと思います。
結果的には、母の時の介護はすぐに終わりましたが、介護はたしかに先が見えません。
もしも、その先にある出口が親の死で、親の死を待っているというふうにしか考えられなければ、介護はつらいものになるでしょう。
しかし、私はただ待っていたわけではないのです。
これといってすることがないままに父のところにいることがあります。
じっと待っているといっても、長い目で見れば、ただ何もしないで待っているはずもありません。
いつのまにか、しかも本当はもっと長く親の元にいてほしかったのに親が思っているよりも早く子どもが自立してしまうように、親も思いがけず早く逝くことになるのだろうと今は想像しています。
【次回】「忘れたことはしかたがない・・・」親の老化の捉え方/先に亡くなる親とアドラー心理学
【まとめ読み】『先に亡くなる親といい関係を築くためのアドラー心理学』記事リスト
 アドラーが親の介護をしたら、どうするだろうか? 介護全般に通じるさまざまな問題を取り上げ、全6章にわたって考察しています
アドラーが親の介護をしたら、どうするだろうか? 介護全般に通じるさまざまな問題を取り上げ、全6章にわたって考察しています