「あの人は間違っている」「あんなことをするなんて許せない」...と強く思ったことはありませんか? 脳科学者の中野信子さんは「人間の脳は仕組みとして他人に正義の制裁を加えることに快感を覚えるようにできています」と語ります。その中野さんの著書『人は、なぜ他人を許せないのか?』(アスコム)では、脳科学的観点から見た「ネット社会にはびこる正義中毒」や「日本特有の社会的な仕組み」などを解説しています。今連載では、「心穏やかに過ごすため」のヒントにつながる5つの記事をご紹介していきます。
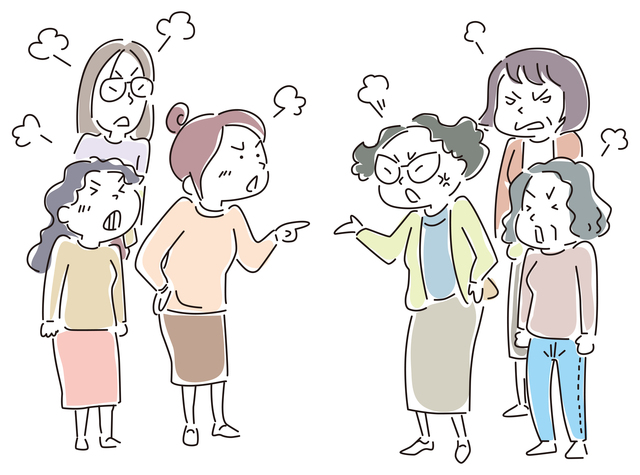
正義中毒のエクスタシー
人は、本来は自分の所属している集団以外を受け入れられず、攻撃するようにできています。
そのために重要な役割を果たしている神経伝達物質のうちの一つが、ドーパミンです。
私たちが正義中毒になるとき、脳内ではドーパミンが分泌されています。
ドーパミンは、快楽や意欲などを司っていて、脳を興奮させる神経伝達物質です。
端的に言えば、気持ちいい状態を作り出しています。
自分の属する集団を守るために、他の集団を叩く行為は正義であり、社会性を保つために必要な行為と認知されます。
攻撃すればするほど、ドーパミンによる快楽が得られるので、やめられなくなります。
自分たちの正義の基準にそぐわない人を、正義を壊す「悪人」として叩く行為に、快感が生まれるようになっているのです。
自分はそんな愚かしい行為からは無縁だ、と考える方もいるでしょう。
しかし、本当にそうでしょうか?
例えば、テレビを見ていたら、どこかのある親が自分の子どもを虐待しているような、ひどいニュースが流れていたとします。
食べ物を与えない、暴言を浴びせる、殴る、放置する、その様子を動画で撮影する......そして傷つき、命を落とす子ども。
ひどい話で、およそ子を持つ親の所業とは思えないような事件です。
マスコミは連日詳細を報じます。
この親は他にもこんなひどいことをしていた、周囲からこんな証言が得られた、子どもがSOSを出していたのに、なぜ行政はうまく活かせなかったのか。
このような人間に親の資格があるのか、地域は、学校は、児童相談所は何をしていたのか......。
さまざまな思いが去来することでしょう。
このようなとき、こうした出来事とは全く無関係な一人の視聴者としての私たちは、無関係ゆえに絶対的な正義を確保している立場にいます。
自分は、こんな風に子どもを虐待しないと思っています。
そして、正義の基準からはみ出して注目を浴びてしまっている人に対して、いくら攻撃を加えようとも、自らに火の粉がふりかかることはありません。
「ひどいやつだ、許せない! こんなやつはひどい目に遭うべきだ、社会から排除されるべきだ」と心の内でつぶやきながら、テレビやネットニュースを見て、自分には直接の関係はないのに、さらなる情報を求めたり、ネットやSNSに過激な意見を書き込んだりする行為。
これこそ、正義中毒と言えるものです。
このとき人は、誰かを叩けば叩くほど気持ちがよくなり、その行為をやめられなくなっているのです。
正義と同調圧力の関係
こうした正義中毒による対立は、他のどのような集団同士でも起こり得ます。
与党と野党でも、会社の営業部門と製作部門でも、ドイツ人とフランス人でも、男性と女性でも同じことです。
○○党だから、営業だから、○○人だから、男だから起こるのではなく、人間である以上必ず起こるのです。
不思議なことに、互いの正義中毒が、双方の需給をうまくバランスさせているケースもあります。
ヘイトスピーチまがいの主張をしている集団がいる一方で、その集団に「ヘイトスピーチをするな!」と糾弾している集団がいます。
もしも何らかの解決が図られて、双方、あるいはいずれかの存在がなくなってしまったら、そこに所属していた人々は、おそらくずいぶん張り合いのない毎日だと感じ始めてしまうことでしょう。
目の前にいる集団に対して「我こそは正義、お前は不正義」と言えることが快感なのですから、「ヘイトだ」「ヘイトじゃない、お前こそヘイトだ」と言い合っている状態は、いわば互いにドーパミンを出し合う状況を提供し合っている関係とも言えるわけです。
「つぶしてやる」と言いながら、本当につぶれられたら困ってしまうのです。
はたから見ているとほとんどコントのようで滑稽ですが、本人たちは大真面目にやっているのです。
スポーツの因縁対決にも同じような構図が見られることでしょう。
日本のプロ野球では、読売ジャイアンツと阪神タイガースの戦いが、積年のライバル同士の伝統の一戦と捉えられているようです。
阪神だけには負けたくない、他チームに負けても読売にだけは勝ちたい、というファン心理は、試合の勝ち負けだけでなく、チームの運営手法やファンの態度まで含め、互いに激しくけなし合いながらも、実はその対立そのものを楽しんでいるという側面があります。
こうしたスポーツ等における長年のライバル関係と、そこに付随している集団心理は、世界中で見られるものです。
ただ、あくまでスポーツですから、ライバル関係もそれに伴う批判合戦も、ある種の様式美と多くの人はどこかで理解もしているはずです。
もしも、巨人のいないリーグになってしまったら、一番残念なのはもしかしたら当の巨人ファンではなく、阪神ファンかもしれません。
その逆もまた同じでしょう。
ライバルとして認め合っている、というと美しいのですが、相互にとって「快感の素」「ドーパミンの湧き出る泉」として、麻薬的に依存している関係でもあるのです。
また、この対立構造のなかには、もう一つ根の深い問題が潜んでいます。
東京ドームで、みんなが巨人のユニフォームを着て応援しているなかに、阪神のユニフォームを着て入っていくのはなかなか勇気のいることです。
逆のパターンもまた同様でしょう。
なかには喧嘩をふっかけてくる人もいるでしょうし、マナーをあれこれ言われてしまうかもしれません。
トラブル防止のために、特定のエリアでは他チームのユニフォームの着用自体が制限されている例もあります。
いくら心の中で敵対心を持っているとしても、実際に対立する相手集団のなかにあって、一人だけ違う行動をとるというのは、なかなか心理的に負担の大きいことです。
周囲の行動に合わせなければいけない(逆らうと恐ろしいことが起きるかもしれない)と感じさせる環境要因のことを「同調圧力」と言います。
いわば、集団のなかで少数意見を持つ人に対して、多数派の考えに従うよう暗黙のうちに強制してしまうことです。
例えば、ちょっと極端な例かもしれませんが、少し前のような、同性愛者があまり自分のことを公にすることのなかった時代には、自分が同性愛者だとカミングアウトすることには恐怖が伴いました。
現在も、いまだに性的マイノリティに対する心ない言葉や態度を露わにする人がいます。
これは、当人だけでなく擁護しようとする人の行動をも制限してしまいます。
「自分には偏見はない」と公言する人たちであっても、同性愛者が冷遇されている状況で、自分自身も嘲笑されるかもしれないという思いを振り切って擁護できるかというと、正直なかなか勇気のいるところではないでしょうか。
欧米人がアジア人を見分けられない理由
人の脳が持つ、集団を作る機能は、自分にとってのよそ者、異質者を排除する仕組みと一体です。
日本国内やアジア圏などにいる分にはあまり感じることはないかもしれませんが、欧米諸国を訪れてみて、実感したという人もいると思います。
私の体験したケースをお話しましょう。
アメリカで、とある国内線の飛行機に乗っていたときのことです。
前の座席の下に入れていた自分のバッグから必要なものを取り出そうと手を伸ばしたとき、隣席のいかにもエリート然とした白人男性が、とっさに彼自身の荷物に手を伸ばし、私をチラリと見て荷物を遠ざけようとしたのです。
「このアジア人は、もしかしたら物取りかもしれない」などと思われたのでしょう。
ショックでなかったと言えば嘘になりますが、一方、私たちも人のことは言えないのではないかという疑念もまた頭をよぎりました。
例えばいかにも身なりの汚い、あるいは信用ならない雰囲気の外国人が自分の横で同じことをしたら?とっさに身構えてしまわないと言い切れる人は少ないと思います。
「人種や肌の色で差別するのはおかしい」とか、「多様な文化を理解すべき」という主張は確かにポリティカリー・コレクト(人種・宗教などの違いによる偏見・差別を含まない表現・用語を用いること。ポリティカル・コレクトネス)ではあるのですが、自分の身や財産を守るという機能はそれよりも優先されてしまうのが常です。
特に、自分の属している集団の仲間内の行動であればそこまで警戒しないのに、そうではない人たちに対しては、一定の警戒心を抱いてしまいがちです。
これは、安全装置のようなものでもあるのですが、自分を対象にその機構が働いているのを目の当たりにすると、動揺してしまいますよね。
しかし、脳にはその安全装置があらかじめ組み込まれているわけです。
これを心理学では、イングループ(内集団)バイアスと呼びます。
イングループ、つまり自分の所属する集団(内集団)に対しては、自分が所属しない集団(アウトグループ=外集団)よりも好意的・協力的に行動する傾向のことです。
私たちが、差別した/されたと感じ合う現象は、このイングループ、アウトグループに対するバイアスによるもので、したがって一概に悪いことだ、愚かだと非難するだけでは決して解決には結びつかないのです。
第二次大戦中、ある連合国側の白人の軍人は、同じ白人であるドイツ人を殺すことには心が痛むが、日本人を殺すことには痛みを感じない、と言ったといいます。
自分たちと同じ白人には共感が働いて良心が痛むのに、有色人種の日本人にはアウトグループに対するバイアスが働いて、同じ人間であるとは感じにくくなっているわけです。
白人社会で暮らしている人は、東アジアの人──例えば、日本人、中国人、韓国人を見かけだけではほとんど判別できないでしょう。
逆もまた同じで、私たちがフランス人とドイツ人、イギリス人を見分けるのは慣れている人でなければ難しいでしょう。
自分が見慣れていないグループの人間は、みんな同じに見えてしまうというのが、外集団同質性バイアスです。
見慣れていない人たちに対しては、その人の外見的な特徴にまず注目してしまうため、人格や感情の動きに注意が向かなくなる、という現象が起きます。
残念なことですが、人間同士としての共感も生まれにくい状況になります。
これは人種に限りません。
男女でも、あるいは異なる服飾文化を持つ人たちの間でも同じことです。
男性にとって、女性は一人の人間としてよりも「女性」という外集団に属している者として認識されます。
女性にとっての男性も同じです。
何か議論になった際に、そこに個々の人格を認めにくいため、議論の内容よりも「議論を挑まれたこと」に反感を抱くという現象が起きやすくなるのは、このためです。
バイアス(偏見)のズレが友情を引き裂く
サッカーワールドカップにおける韓国人たちの話も、集団バイアスが、いかにやすやすと人間の心に生じるかを示しています。
このような異なる集団同士が互いに罵り合う状況について、集団同士の振る舞いの差を調査した有名な心理学の実験があります。
1954年に、ムザファ・シェリフとキャロリン・シェリフ夫妻が行った実験です。
ロバーズ・ケーブ州立公園で行われたキャンプにおける研究で、泥棒洞窟(ロバーズ・ケーブ)実験という名で知られているものです。
被験者となったのは、白人・アングロサクソン、プロテスタントの中産階級出身の10~11歳の22人の少年たち。
彼らを二つの集団に分け、それぞれキャンプを張ってもらいます。
その上で偶然を装い出会わせます。
二つの集団の間には、スポーツなどで競争心が生じるような状況に仕向けます。
例えば、競争に勝ったグループは賞品を獲得できるなどという設定をするのです。
すると、双方の集団の間にはいとも簡単に対立感情が生まれ、激しく争うようになっていきます。
さらに相手集団の旗を燃やしたり、殴り合いに発展したり、相手のキャビンに夜襲をかけて盗みを働いたり、一緒に食事をする食堂で残飯を投げ合ったりするなど荒れ放題の状況が生じました。
これは、隣の学区の学校同士や、隣り合っていてよく似ている二つの町同士などの間でも、ささいなきっかけが元で争いが起こりかねない可能性を示しています。
「○○県ではA市とB市の仲が悪い」「南米の国同士は、サッカーの試合になると殺し合う勢いで戦う」というような事例は、同根であると言えるのです。
見た目に大きな違いがなくとも、人種も宗教も年代も性別も同じ集団同士でも、きっかけさえあれば容易に境界線が引かれてしまうのです。

ネットの影響で増中の「自分が正しい!」という「正義中毒者」に陥らないための考え方を4章に渡って解説





