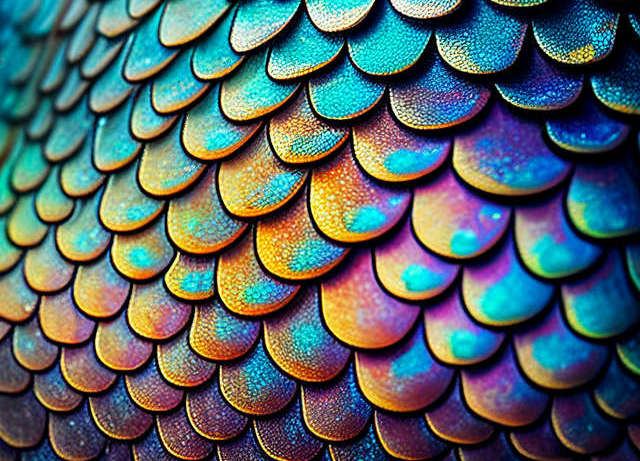月刊誌『毎日が発見』の人気連載、哲学者の岸見一郎さんの「生活の哲学」。今回のテーマは「悲しみからの脱却」です。
この記事は月刊誌『毎日が発見』2023年11月号に掲載の情報です。

信頼して見守る
ある日、街を歩いていたら、声をかけられた。最初すぐには誰かわからなかった。最後に会ったのが十年以上も前のことだったからだが、しばらく世間話をした後、実は、子どもが前年急死したと話し出されたので、私は驚き、子どものことで心を痛めておられたことを思い出した。急死という言葉を聞いて、一体どうされたのかたずねることができなかった。
別れてからその人の心中を想像した。亡くなった娘さんは私の息子と同い年だった。さぞかし無念だっただろうと思った。
私はそれまでも子どもを早く亡くした親と話す機会はたびたびあったが、つらく悲しい経験をし苦しみの渦中にある人のためにできることはあまりない。
理不尽にしか思えない子どもの死のために深い悲しみに打ちひしがれる人と悲しみを共有することしかできなかった。
いつまでも続くように見える暑さも寒さもやがて季節がめぐると消えていくように、苦しみ、悲しみもいつかは消える。しかし、そんなことをいってみても、悲しみの渦中にある人には届かない。
まわりの人は、苦しみ、悲しみの渦中にある人が、決して不幸に押し潰されることなく、必ず回復すると信頼して見守るしかない。
悲しんでいる人は、あなたの気持ちはわかるというような安直な言葉を期待していないだろう。自分の悲しみは他の人に完全には理解されないことを知っている。悲しみからは自力で脱却するしかない。しかし、自分の悲しみを誰にも理解されたくないと思っているわけではない。
むしろ、誰にも理解されず孤立することを恐れているので、まわりの人は何かできることがあったらいってほしいと言葉をかけることができる。
悲しみとの融和
それでは、悲しみの渦中にある人はどうすればいいか。神谷美恵子(※1)は、パール・バック(※2)の「悲しみとの融和」という言葉を引きながら、次のようにいっている。
「自分のかなしみ、またはかなしむ自分に注意を集中している間は、かなしみからぬけ出られない」(『生きがいについて』)
神谷美恵子は若い日に恋人を亡くした。交際したわけでもなく、恋人同士として会ったこともなかったが、恋人の死に痛手を受けた神谷は、彼の影を何十年も引きずることになった。
悲しみと融和するためには、まず、起きたことを受け入れなければならない。神谷にとっても容易なことではなかったであろう。起きてしまったことについて、「なぜ」と問うことをやめなければならない。
次に、悲しむ自分から注意を逸(そ)らし、悲しみを意識の視野の中心から外へと少しずつ押しやらなければならない。悲しみや苦しみがなくなるわけではないが、そこから脱却するためには、本を読んだり、音楽を聴いたりすることで悲しみや苦しみの中心を少しでも自分から逸らすことから始めることが必要である。
悲しむ人はどうしても自分中心にものごとを考えてしまう。そのことがまわりの人を遠ざけることになる。アドラー(※3)は、悲しみは人間の本性として自然なものであるというが、次のような問題を指摘している。
「[悲しみは]他者の共同体感覚を自分に向けることを大いに求めるので、例えば、悲しみの段階から出たくない人がいる。なぜなら、多くの人が友情や同情を示すので、自尊感情が並外れて高められることを体験するからである」(『性格の心理学』)
まわりの人は悲しんでいる人の力になりたいと思う。「共同体感覚」というのは人と人が結びついていると感じられるということだが、そのように感じている人は、悲しんでいる人の力になりたいと思う。
「悲しむ人が、誰かの奉仕や同情や支え、あるいは何かを与えられたり話しかけられることなどによって、しばしば楽になることは知られている」(前掲書)
悲しんでいる人はまわりの人に支えられることで楽になり、自分のことを心配して気遣ってくれる人がいると自尊感情が高められる。悲しみの段階から出たくないのは、悲しまなくなったら誰も自分に注目しなくなると思うからである。このように悲しむと注目されることを学んでしまうと、いつまでも悲しみから脱却できなくなる。
※1 1914〜1979年。精神科医。エッセイなどの著作があり、『自省録』(マルクス・アウレリウス)などの翻訳も手掛けた。
※2 1892〜1973年。アメリカの作家。『大地』などの著作がある。
※3 アルフレッド・アドラー(1870〜1937年)。オーストリアの精神科医、心理学者。