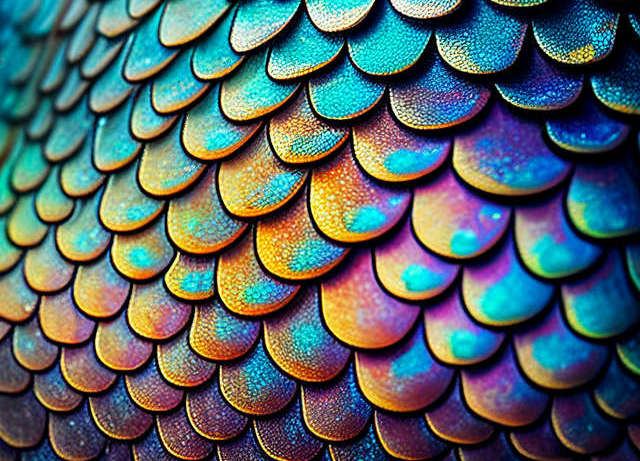月刊誌『毎日が発見』の人気連載、哲学者の岸見一郎さんの「生活の哲学」。今回のテーマは「寛容であること」です。
この記事は月刊誌『毎日が発見』2023年9月号に掲載の情報です。

不寛容な人の説得
伊坂幸太郎(※1)の『死神の浮力』には、登場人物の一人である小説家の父親が愛読していたという「渡辺先生」の本から多くの言葉が引用されている。
「渡辺先生」は仏文学者の渡辺一夫(※2)であり、もっぱら引用されているのは「寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか」(『狂気について』所収)である。渡辺のこの問いに「寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容たるべきでない」と答えている。伊坂の小説の中の言葉を借りると、優しい人間は、ひどい人間に対しても優しくすべきかという問いに、渡辺は不寛容であってはならないと結論づけている。
このような渡辺の結論を知って、伊坂の小説の登場人物は、少し落胆したような顔を見せるが、「どんなことをされても我慢しなさい」と渡辺は主張しているわけではない。
切羽詰まった場合に、寛容な人といえども不寛容にならざるをえないことはあるだろうが、これを原則として肯定する気持ちはないと渡辺はいう。優しい人がひどい人にキレてしまい、そうなることを仕方ないと感じることはあるだろうが、このような「人間的事実」(前掲書)の発生を阻止するよう全力を尽くさなければならないと考える。
たしかに、人間は噓をつき逆上して殺人もする。しかし、そのような「悲しく呪わしい現実」(前掲書)を人間的事実として認めても、それを当然の事実と認める人はいないだろう。寛容が不寛容に対して不寛容になってはならないという原則も、噓をついてはいけない、人を殺してはいけないという契約と同様、新しい契約として獲得されなければならない、これが本当の倫理として、しっかりと守られていけば不寛容も必ず薄れていくと渡辺はいう。
不寛容と寛容が相対峙した時、何ができるだろうか。寛容は常に無力であり敗れ去るものであるが、ジャングルの中で人間が猛獣に襲われるようなものである。しかし、猛獣を説得することはできないが、不寛容な人に対しては、説得のチャンスが皆無ではない。そこに「若干の光明」(前掲書)がある。『死神の浮力』の登場人物は、「悲観的なことを書きつつも、『だけどね』と小さな希望を滲(にじ)ませる部分に、励まされた」(『死神の浮力』)といっている。
とはいえ、説得は難しい。渡辺は、寛容と不寛容との問題は「理性とか人間性とか言うものを、お互いに想定できる人間同士の間のこと」であり、「普通人間の場に置いて、まず考えられなければならない」(渡辺、前掲書)といっている。
※1 小説家。1971年〜。著書に『重力ピエロ』などがある。
※2 フランス文学者、評論家。1901〜1975年。
教え、示せ
渡辺がいう「猛獣的な人間」や「有毒菌的天災的な人物」でなくても、理屈が通じない人、理不尽な怒りをぶつけてくる人は多い。ローマ皇帝のマルクス・アウレリウスも宮廷で多くの不寛容な人と日々接していたのだろう。次のようにいっている。
「もっともよい復讐の方法は、自分まで同じような者にならないこと」(『自省録』)
アウレリウスは復讐することを勧めているわけではない。相手が怒りをぶつけてきたとしても、相手と同じように不寛容であってはいけないという意味である。挑発に乗ってしまっては、争いはエスカレートするばかりで、問題の解決にはつながらない。
「できるならば、教え改めさせよ。しかしできないならば、これ(他者の過ち)に対して寛容がお前に与えられていることを覚えておけ」(前掲書)
怒りをぶつけてくる人に対しても不寛容にならず、寛容でなければならない。しかし、このことは我慢することではない。
「人間は互いのために生まれた。だから、教えよ。さもなくば耐えよ」(前掲書)
「怒らずに、教え、そして示せ」(前掲書)
「さもなくば耐えよ」というのは、怒らずに耐えよ、我慢せよという意味ではなく、誤りを教える(渡辺の言葉では「説得」する)ことができないのなら、怒らないで耐えよという意味である。