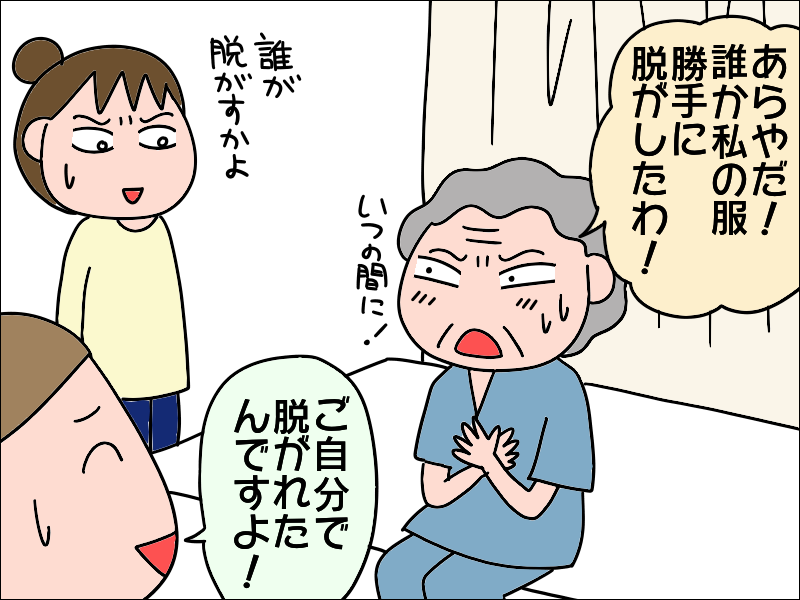親の本当の姿を理解できるのは家族
一番、驚き、正直ショックを受けたのは、父が亡くなった母のことをすっかり忘れてしまっていたことでした。
この家で、一緒に住んだではないかといってみても、淋しそうに首を振るばかりでした。
父がこのようないわば自分の存在の根幹に関わることについての理解を欠いていることを知って、実家に戻ってくる前に同じものを何度も買ったことも、外出先から帰れなくなってたまたま通りかかった近所の人が車で連れ帰ったことも、また、主治医や大家さんと喧嘩したことも、振り返れば病気のせいだったのかもしれないとようやく思い当たったのでした。
記憶障害については簡単な検査でもすぐにわかるでしょうが、このような感情や性格の変化は、父と少しの間話すだけではわかりません。
共に生活して初めてわかります。
父の場合、人とのコミュニケーションは十分できますから、父の病気に気づかない人もあります。
入院中、父は夜中に部屋の外に出ていって迷ってしまうというようなことがありました。
病院は生活の場ではなく、非日常的な経験を強いられますから、父ならずとも誰もが多かれ少なかれ混乱します。
しかし、父にとって入院という急激な環境の変化がかなりの混乱を引き起こしたようです。
退院して再び生活の場に戻ってきた時、父がもはや入院前の状態に戻れなくなったことを目の当たりにした時、認知症という診断が下されたことの意味が具体的にどういうことなのかはっきりとわかったのでした。
しかし、親の様子が以前とは違うことを目の当たりにして、医師から認知症と診断されても、私はなお親が認知症であることを認めたくはありませんでした。
病院などでの検査の時とは違って、日常の生活においては親が検査の時にはできないことも難なくこなしていることを見ていたからです。
医師は「今は季節は何ですか」とか「100から3を引いて」というようなことをたずねる検査をしたのですが、そのことで父を正しく診ることができるとは思えませんでした。
「今の季節は何ですか」という質問も、外は寒くても暖房の効いた病院の中に長くいればわからないかもしれません。
その後も父は何度もいろいろな機会に「今日は何月何日ですか」という質問を受けることになりますが、今日が何日かというようなことは、仕事をしていない父には必ず知っていなければならない情報ではありません。
そもそも父は、何のためにそんなことを問われるか理解できなかったようでした。
医師が父と十分信頼関係を築ける前に、認知症の検査を受けても、父はただ困惑するだけで、普段の力を出すことはできませんでした。
そんな状態で得られた結果を見るだけでは正しい診察ができるとは思えませんでした。
ですから、親の本当の姿を理解できるのは家族だといいたくなります。
本やインターネット、あるいは医師による説明などによって認知症とはどんな病気なのかという一般的な知識を得ることはできます。
検査結果を踏まえて親の様子を見ることで、他ならぬ〈この〉親の認知症を知ることができるからです。
他方、家族は親の状態を軽く、あるいはよく見る傾向がありますから、家族もまたその意味では親を正しく見ていないといえます。
感情移入をしない第三者のほうが、病気を正しく見極めることができるともいえるからです。
認知症を専門にし、多くの人に認知症の診断をしてきた医師が、自分の妻が認知症と診断されて初めて介護がいかに大変なものかがわかったと書いている本を読んだことがあります。
認知症といってもその現れ方は人によって違いますから、この医師が認知症の専門家であっても、妻の認知症に一般化できない面があることを知ったということもあるかもしれませんが、認知症であると診断されることは、家族にとっては終わりでなく、これからいつまで続くか予想ができない介護の始まりであることを、その医師が十分認識していなかったともいえます。
【次回】介護の審査で罪悪感。「何でもわかる言うたらアカンのやな」って言ってたのに.../先に亡くなる親とアドラー心理学
【まとめ読み】『先に亡くなる親といい関係を築くためのアドラー心理学 』記事リスト
 アドラーが親の介護をしたら、どうするだろうか? 介護全般に通じるさまざまな問題を取り上げ、全6章にわたって考察しています
アドラーが親の介護をしたら、どうするだろうか? 介護全般に通じるさまざまな問題を取り上げ、全6章にわたって考察しています