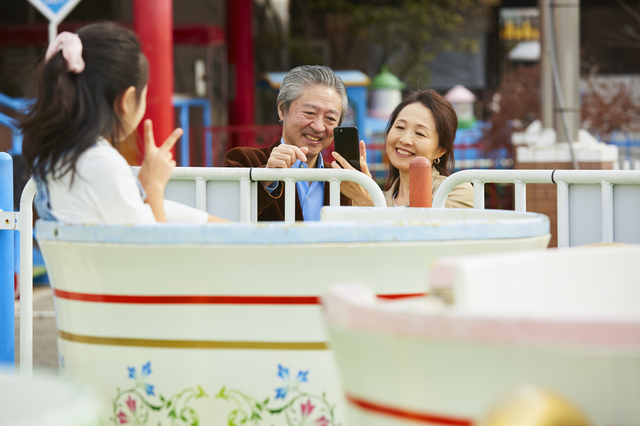<この体験記を書いた人>
ペンネーム:文月奈津
性別:女
年齢:63
プロフィール:長男、次男、主人の4人家族。長男は近所で一人暮らし。主人共々体力が落ち、毎晩9時半には寝てしまう毎日です。

チェストの引き出しを整理していたら、入院中だった母が書いたメモがでてきました。
メモの内容は、渡さないまま終わった父へ宛てた手紙です。
母が末期の胃がんで余命半年を宣告されたのは、忘れもしない昭和54年12月20日でした。
そのとき母は、48歳。
1年半位前から、胸の痛みを訴えていた母はいくつかの病院で検査を受けました。
肋間神経痛か更年期障害ではないかなどと言われ、結局原因がわからないまま母はどんどん痩せていきました。
そのころ、父がまたもや愛人をつくり、家に帰ってこないことが増えました。
母に元気をだしてもらいたいと思い、私は3泊4日の北九州旅行をプレゼントすることにしました。
「元気にならないと旅行に行けないわよ。飛行機だって初めて乗るのでしょ」
何度も母に声をかけました。
福岡、大分、長崎を母と一緒に旅をする中、時折楽しそうな笑顔を見せましたが、母は旅行中はほとんど暗い顔ばかりしていました。
旅行から帰った母は、床につく日が多くなっていきました。
そんな母を見兼ねた私は、家族会議を開き、父に詰め寄りました。
「きっぱり、別れなさいよ。何度女性問題を起こせば気が済むの」
具合の悪い母の前で「あの人は大切な人だ。別れない」という父にあきれはてた私は、家を出たいという母の希望を聞き入れることにしました。
母と共に引っ越したのは暑い夏の日、私の23歳の誕生日でした。
娘と2人の気楽さからか、少しは元気になった母の具合がまた悪くなったのはその年の12月。
入院して2日後に手術になりました。
「がんは胃の裏側にあったので今まで発見されなかったのだろう。もう手の施しようがないから、食事ができるようにバイパスだけ通した。どんなにもっても、あと半年」
手術を終えた主治医は言いました。
一度は落ち込んだ私ですが、母の病と闘う決意をしました。
母は1月の中旬に退院すると、余命宣告の半年が過ぎた頃には小康状態になり、私の勤務先が所有する箱根の保養所に行くことができました。
しかし、昭和55年の冬には、30㎏をきるほどやせ衰えてしまいました。
そしてとうとう昭和56年の年頭に再度入院。
メモは母が亡くなる一月位前に書かれたものです。
簿記1級の資格を持ち経理の仕事をしていた母は、私がするからと言うのを聞かず、入院費の計算と支払いをしていました。
父からの仕送りが遅れがちなことが心配で、ペンをとったようです。
前半にはこまごまとかかった医療費の説明が書かれていました。
「3月に入ってやっと歩けるようになり、3月の22日に退院したいと先生にお願いしどうにか許可がでました。(一時帰りですが)もうすぐ4月で季節もよくなり、もう1年?位寿命が延ばせそうです。
○○と○○の結婚の相手がはっきりするまで生きていたいと思います。
○○には青春時代の一番楽しい時期をがんの母親のために犠牲させたお礼に、赤ちゃんの世話ぐらいしてあげねばと欲が出てきます。
何の役にも立たない身体なのに生き永らえ、お金ばかりかかり申し訳なく思います。
3月13日 PM1:00」
昭和56年4月30日、母は私に看取られ50歳で亡くなりました。
その日、母の容体が悪くなり病院に泊まっていた私は、入浴のため一旦帰宅しました。
病院に戻って兄や父と交代した私に「せっかく家に帰ったのだからゆっくりしてくればよかったのに」と母は言ってくれました。
「明日からゴールデンウィークだから、ずっとそばにいるからね」
その後、母の足をさすったり、胸をさすったりしているうちに、弱くなっていた母の心臓が止まったのでした。
私は、その後2人の子供を授かりました。
それは、母の亡くなった月と同じ4月。
長男と次男、二つの命をこの世に生み出しました。
同じ月であったことが、せめてもの、最後の親孝行になったのではと思っています。
毎年4月を迎えるたびに、一度でいいから主人や長男、次男に会ってほしかったと、涙がこみあげてくるのです。
関連の体験記:「お姉ちゃん、あのさ...」報告を受けボロボロ泣いた。母の面倒を見てきた40歳の妹の結婚
関連の体験記:すべての会話に「うるせー」「バカ」。結婚15年、仲が良かった主人が豹変した哀しい理由
関連の体験記:恥ずかしながら涙ぐんだ60歳の私。2浪した上に大学院に進んだ一人息子が27歳で社会に出た意外な経緯
- ※
- 健康法や医療制度、介護制度、金融制度等を参考にされる場合は、必ず事前に公的機関による最新の情報をご確認ください。
- ※
- 記事に使用している画像はイメージです。