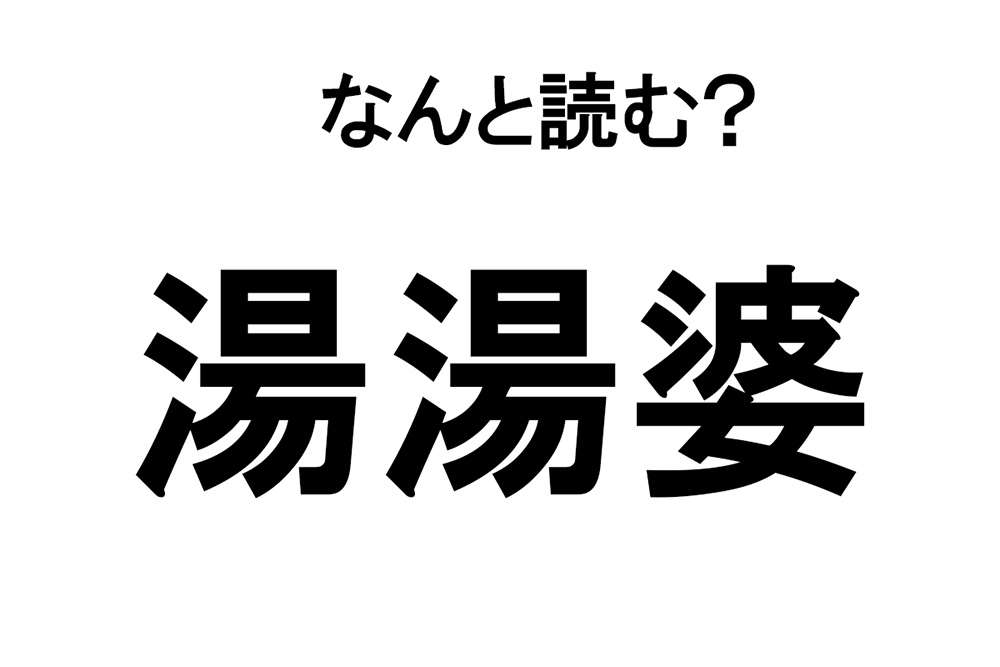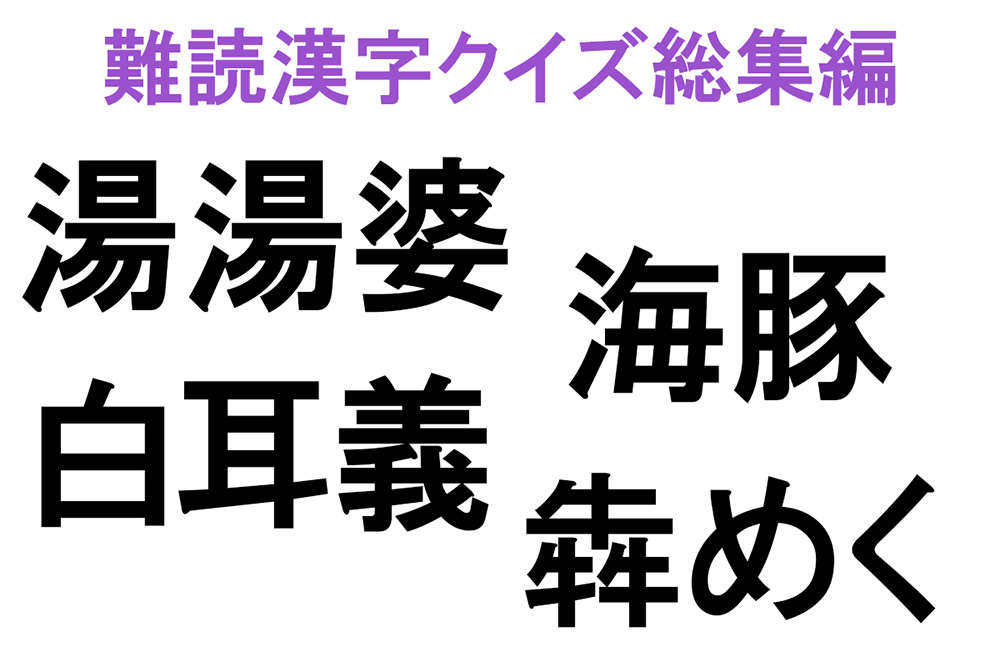"坂のまち小樽に暮らす人々が人生という坂の途中で本を読み、大いに語り合う会"。略して、「坂の途中で本を読む会」――この小さな読書会のメンバーが、朝倉かすみ氏による長編『よむよむかたる』(文藝春秋)の主な登場人物である。毎月1回開催されていた読書会が、コロナ禍で休会を余儀なくされ、3年ぶりにメンバーが集まる場面から物語がはじまる。
※この記事はダ・ヴィンチWebからの転載です。

本書は、喫茶シトロンの店長である安田松生の語りで進んでいく。喫茶シトロンは、「坂の途中で本を読む会」の会合場所だ。叔母の美智留から喫茶シトロンの店長を引き継いだ安田は、サークルメンバーが全員参加できるかどうかを危惧していた。会員のほぼ全員が高齢者で、最高齢は92歳のまちゃえさん(増田正枝)。会の発足から会長を務める大槻克己さんは、御年88だ。何らかの不調が起きても不思議ではない年齢に加えて、高齢者ほど重症化しやすいといわれるコロナ禍明けとあっては、安田の心配は当然であろう。しかし、彼の懸念は杞憂に終わった。3年ぶりの会合は、奇跡的に全員が集合したのである。
読書会のメンバーは、元人気アナウンサーだった会長をはじめとして、まちゃえさんの夫であるシンちゃん(増田晋平)、会計を務めるエネルギッシュなマンマ(加藤竜子)など、個性あふれる面々が揃う。各々をあだ名で呼び合い、自由気ままにしゃべり倒す会員のパワーに、安田は終始圧倒される。やがて、なりゆきでサークルに加入した安田は、名誉顧問と書記に任命されたほか、「坂の途中で本を読む会」発足20周年の記念事業を任されることとなる。その背景には、安田が持つ"作家"の肩書があった。
安田は、とある新人賞の受賞を機に作家デビューしたものの、初の書籍刊行後、長いスランプに陥っていた。自分は「もの書く者」であると自負しながら、どうしても書けない。その理由は、出版社に届いた一通の手紙であった。
"ほんとうに、あなただけのお話ですか?
あなたひとりでつくりましたか?"
剽窃を疑う内容の手紙に、安田は一切心当たりがなかった。しかし、この手紙を目にして以降、安田の中にもとよりあった怖れが浮上した。
"アイディアたちの餌の主な成分は先行作品だ。文芸、映画、コミック、アニメ、伝統芸能などなど、あらゆる表現の既出作品。ゆえにそもそも安田の胸には先行作品への畏れと、これすらパクリになるかもとの怖れと、なんとなくバレたらヤバいという虞(おそれ)が沈殿していた。"
自分が生み出したと思っていた表現が、繰り返し摂取してきたコンテンツの中にあるかもしれない。この怖れは、おそらくクリエイティブに携わる多くの人がひそやかに抱いている。そういったものがまとわりついた結果、安田は小説を書けなくなった。しかし、そんな安田の心情などお構いなしで、読書会メンバーは安田のことを「やっくん」なる愛称で呼び、ある意味では気持ちのいい無神経さで安田を仲間の輪に引き込んでいく。その後、サークルでの活動を通して安田は新たな人物と出会うのだが、その人物は、サークル内のとあるメンバーと深い縁があった。
"「よくあるじゃないですか。本を読んでいると、特にどうということのないシーンや描写でも、それがきっかけでごく個人的な思い出が連想されること。記憶に埋もれていたこども時代のある瞬間や、家族とのなんでもない会話なんかが、渡り鳥みたいにはるばるとやってきて、ここに留まるというような」"
「坂の途中で本を読む会」会長の言葉である。この感覚は、本を愛する者の多くが共感するであろう。本書は、一貫してこの感覚を仔細に描いた物語のように思えてならない。みんなで集まって本を読む。音読の素晴らしさを称え合い、感想を述べる。各々の自由な解釈を話し合う。その中で気づく真理や揺れ動く感情の機微を味わう。本を読み、人生を語り、仲間との時間を慈しむ登場人物たちの姿は、実にいきいきとしていた。
読書の魅力、人同士の縁、命の儚さと尊さ。ある謎解きをスパイスとして、人同士のつながりを色濃く描いた本書は、読みすすめるごとに"生きていること"への感謝がじわりと胸にあふれる。老後の楽しみとして、若い時分の生きがいとして、人生の坂の途中、誰かと本を読み合う時間を持てたなら。そんな希望を胸に抱かせる本書の魅力を、まずは誰かと語り合いたい。その時間は、物語で描かれる景色と同様に、きっとかけがえのないものとなるだろう。
文=碧月はる