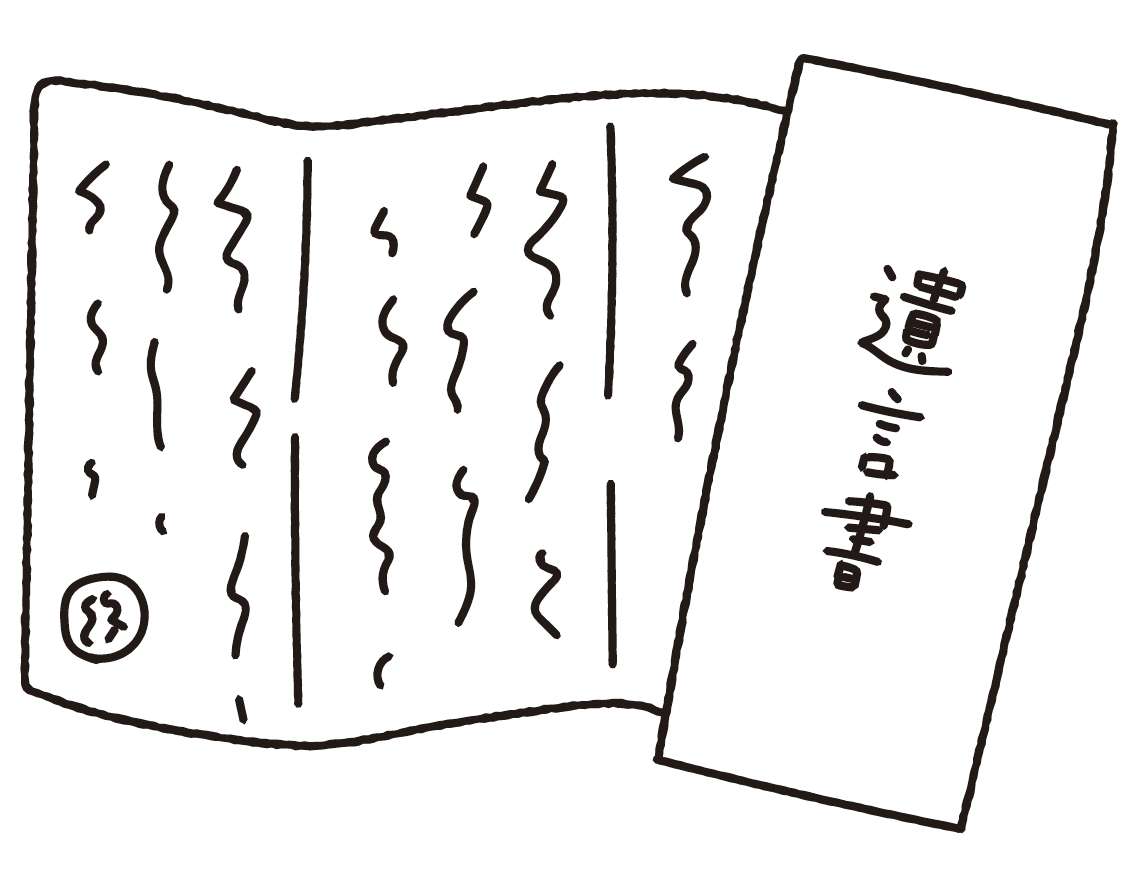なぜ、男性は放火自殺を選んだのか
男は、若い頃から仕事に誇りをもって働きつづけていました。
中学校を卒業して、すぐに国鉄(現:JR九州)に就職し、現場でキャリアを重ねていきます。
その後、異業種である不動産販売会社へ転職し、60歳の定年後もなお、会社で働きつづけました。
ただ、70歳の頃に狭心症を患い、仕事人生に別れを告げて、療養せざるをえませんでした。
やがて、ほかの病気も併発するようになり、自宅で寝たきりの状態がつづきます。
奥さんがずっと看病や身のまわりの世話をしていましたが、そのことが、男の心を苦しめつづけていたのでしょう。
病気やけがなどで仕事ができなくなったとたん、「稼いできてナンボ」という価値観に基づくプライドがへし折られた男性は、精神的にやられやすいのです。
一方的に世話をされるだけで、自分は何も返してやれない。
その申しわけなさが、日々積み重なり、じわじわと自尊心がむしばまれていくのでしょう。
ほとんどの自殺者が、「できるだけ痛みや苦しみが少ない方法」を選択しようとします。
そんななか、あえて焼身自殺を選ぼうとする人には、自分に厳しい罰を与えたい、あるいは社会に対して何かを伝えたい覚悟が強いといわれます。
自分の犠牲になる妻に申しわけが立たない
実際に住居として使われている建物に火を放つ「現住建造物等放火罪」は最高刑が死刑
で、裁判員裁判が開かれるほどの重大犯罪です。
放火にいたるまでの経緯を説明する被告人を、3人の裁判官のほか、一般から選ばれた6名の裁判員が、法廷の壇上から見つめます。
事件の直前、出かける妻に対して、被告人は「さよなら」と別れを告げていました。
妻は、その言葉の奥にある意図に気づいていたそうです。
狭心症などを患って寝たきり状態の被告人は、これ以上、最愛の妻に迷惑をかけるのがどうしても耐えられなかったのでしょう。
いくら介護をつづけても自分の状態がよくならないのなら、いっそ過去をリセットして「これからは、妻にもっと自由に生きてほしい」という思いから、自宅に火を放ち、全焼させるにいたりました。
本稿の「名裁判」の情報は、著者自身の裁判傍聴記録のほか、読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞・共同通信・時事通信・北海道新聞・東京新聞・北國新聞・中日新聞・西日本新聞・佐賀新聞による各取材記事を参照しております。
また、各事件の事実関係において、裁判の証拠などで断片的にしか判明していない部分につき、説明を円滑に進める便宜上、その間隙の一部を脚色によって埋めて均している箇所もあります。ご了承ください。裁判記録を基にしたノンフィクションとして、幅ひろい層の皆さまに親しんでいただけますことを希望いたします。