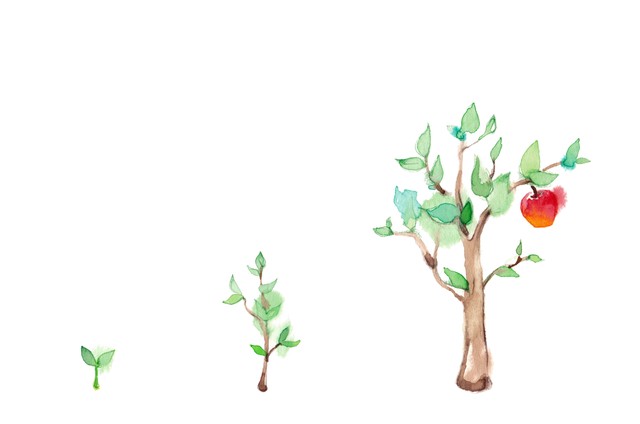 『毎日が発見』本誌で連載中の哲学者・岸見一郎さんの「老後に備えない生き方」。今回はその12回目を掲載します。テーマは「生きていることがありがたい」。
『毎日が発見』本誌で連載中の哲学者・岸見一郎さんの「老後に備えない生き方」。今回はその12回目を掲載します。テーマは「生きていることがありがたい」。
◇◇◇
前の記事「「ありがとう」を期待してはいけない/岸見一郎「老後に備えない生き方」」はこちら。
できることに注目する
それでは、どうすれば現実の親を受け入れることができるか。
まず、できなくなったことではなく、できることに注目することである。前にも書いたが、人生には「するべきこと」「したいこと」「できること」しかない。このうちできることは「できること」だけである。
北(編集部注:作家の北杜夫)は父親(編集部注:北杜夫の父で歌人の斎藤茂吉)にまだ旺盛な創作意欲があることを知れば安堵したと書いている。そのことだけに目を向ければいいのである。「まだ」あると思う必要もない。「今」旺盛な創作意欲があることを知ればいいのである。
拙い歌があることには目を向けなくてよい。親が衰えたので拙い歌を詠んだと思う必要はない。若い時でも詠んだすべての歌が優れたものであったはずはないからである。それなのに、拙い歌があれば、それを老いと結びつけてしまう。親が子どもの問題行動にばかり目を向けてしまうのと似ている。
自分についても、できなくなったことではなく、できることに注目したい。歳を重ねるといろいろなことができなくなるが、できることも多いはずだ。
古代ローマの政治家、哲学者であるキケローが次のようにいっている。
「今、青年の体力が欲しいなどとは思わないのは、ちょうど、若い時に牛や象の力が欲しいと思わなかったのと同じだ。在るものを使う、そして何をするにしても体力に応じて行うのが良いのだ」(キケロー『老年について』)
たしかに、青年の体力はいらないが、これとて私が若い頃から運動に馴染んでこなかったからこう思うだけで、歳を重ねてもマラソンをする人はいる。
知力については、若い時のような記憶力はないという人は多いが、実際に知力が衰えるというよりも、そう思い込んでいるだけのことが多い。もしも高校生や大学生の頃のように熱心に学べば、大抵のことは身につくはずなのに、初めからできないと思い込んでいることが多いように思う。
作家の野上弥生子(やえこ)と哲学者の田辺元(はじめ)がともに六十五歳から十年の間に交わした手紙が収められている往復書簡(『田辺元・野上弥生子往復書簡』)を読むと、老いても知力は衰えないことがわかる。私が初めて二人の書簡を読んだ時はまだ四十代の半ばだったので、二人が高齢なのに知的な内容のやりとりをしていることに驚いたが、私自身が二人の年に近づいた今はそれほど驚かなくなった。
生きていることに注目する
次に、できることだけではなく、今、生きていることに注目することである。事実、できることがなくなることがあるからである。
いつか桜を見にきていた人の言葉が耳に飛び込んできた。
「朝、目が覚めた時、身体が動かせると本当に幸せ」
私も心筋梗塞で倒れる前は歩けることが当たり前だったが、絶対安静を強いられ、歩けなくなった。しかし、リハビリをして少しずつ歩けるようになると歩けるだけで嬉しかった。
だが、できることに注目するだけでは、できないことが増えると、自分に価値があるとは思えなくなるかもしれない。親についても自分についても、理想から引き算しないで、現実を受け入れるためには、生きていることがありがたい、生きていることそれ自体に価値があると考えたい。
元気な時はなかなかこのようには思えないが、病気になれば、あるいは、病気にならなくても老いを意識し始めれば、生きていることがありがたいと思えるようになる。
父の介護をしていた時、朝、父の家に行って玄関の鍵を開けようとすると、いつも大音量のテレビの音が聞こえた。もう起きているのだとわかって安堵したが、ある日、いつもと違ってテレビの音が聞こえなかった。
「死んだかな」と思った。寝室の戸を恐る恐る開けたら、父は穏やかな寝息を立てて寝ていた。生きていることがありがたいと思った瞬間である。
作家、瀬戸内寂聴の秘書である瀬尾まなほの『おちゃめに100歳! 寂聴さん』に、先生が寝ている部屋のふすまを開ける時、「耳を澄ませる」ことから一日が始まると書いてある。
「いびきが聞こえると、『良かった。死んでなかった』とホッとする」
生きていることがありがたいと思うことを原点にして加点していけば、どんなこともありがたいと思える。そのように思えれば、自分がしたことに「ありがとう」といわれなくても自足できる。
以上のことは、自分についてもいえる。
「朝、目が覚めた時、生きていると本当に幸せ」
変わらないことと変わること
「夫婦二人の生活。耳も聞こえづらくなり、どこにも出かけないので、変化のない生活、だんだん会話も少なくなってきました。老後を楽しく生きる方法を教えてください」
変化がないのはありがたい。会話が多ければいいわけではない。夫はテレビを見て、妻は編み物をする。見るともなく、ついているテレビに時折注意を向け、一言二言話す。そうこうするうちに昼時になる。こんな生活こそ至福である。
しかし、本当は生活にまったく変化がないわけではない。哲学者の森有正(ありまさ)が、パリのノートル・ダム寺院の裏手の公園に植えられたマロニエの若木が成長していく様子を次のように書いている。
「ノートル・ダムの苗木は知らぬ間に数倍に成長している。つい今しがた眺めていたのろのろと遡(さかのぼ)る伝馬船(てんません)は、気のつかないうちに上流の視界の彼方に消えてしまう。それは実に深い印象を私に残す。それはまことに見れども飽かぬ眺めである。私の内部の何かがそれに呼応するからである」(森有正『旅の空の下で』)
毎日見ていると目には木の成長は見えないが、不断に成長しいつの間にか大きくなっていく。セーヌ川を遡る伝馬船も同じである。
森は「飽かぬ眺め」といっているが、毎日慌ただしく生きている人であれば、自分の内部にゆっくりと変化していくものと呼応するものがないので、ゆっくり動くものには注意が向かないかもしれない。ゆっくりと変わっていくものに目を向けることができるようになれば、老後を楽しく生きることができる。
「毎日を流され過ごしています。自分の気持ち次第とわかっていても、なかなかできない自分がいます。有意義な一日を送るにはどうしたらいいですか」
何かするべきことがあるのに、それができないで毎日を流されて過ごすというのも、理想から現実を引き算しているのである。するべきことはできるに越したことはない。しかし、できないのならできないということを認めるところから始めるしかない。
できないからと自分を責めても結局流されてしまうことになる。
有意義な一日を送れなくてもいいと割り切るか、何を以て「意義」があると見なすか、その考え方を変えることができる。前回の最後に見たように、生産性、つまり何かができることに価値があると思えば、何もできずに毎日を流されるような過ごし方は認められないことになるが、何もできなくてもいいと割り切ればいい。
この相談者も何もしていないのではない。フランスの彫刻家であるロダンは、Bon jour(こんにちは)といった後、必ず、Avez-vous bien travaille?(よく働きましたか?)といった。
ロダンが「絶えず仕事をしなければならない」という時、それは、ロダンがほとんど休むことなく制作に励んだという意味である。
しかし、働くということの意味を拡大していいだろう。本を読んだり、手紙を書いたり、散歩したり、ぼんやりしたり、眠っていたり...何をしても、していなくても生きているのであり、気がつけば木が成長するように成熟している。それが人生だ。



