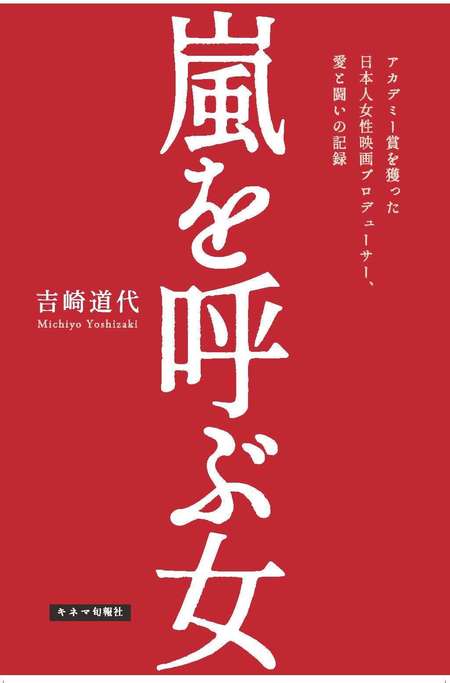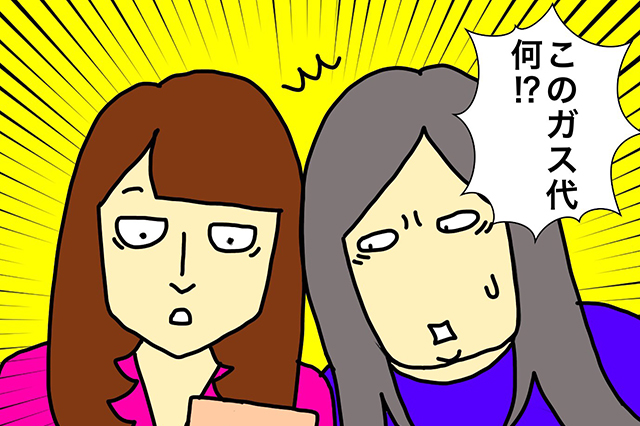40年にわたりヨーロッパを拠点に、映画界で国際的な活躍をしている吉崎道代さん。『ハワーズ・エンド』(92年)や『クライング・ゲーム』(92年)など、アカデミー賞受賞作を含む多くの名作を手がけてきた女性プロデューサーのパイオニアとして知られている。そんな吉崎さんが人生を綴った『嵐を呼ぶ女』は、映画の仕事で成功したいと願う人たちにとっては格好の手引書であり、バイタリティーあふれる女性の"闘いの物語"でもある。その不屈の闘志に、圧倒されます。

撮影/吉原朱美
イタリア留学は、結婚資金の前借りで
――出版された感想は?
私の人生の軌跡を息子や孫に知ってもらいたいと思って書き始めましたが、人生を2倍生きたような幸せな時を過ごしました。
うれしいことも悔しいこともありましたが、いま思い返しても悔いはない。
もう一度人生をやり直すとしても、やはり映画の仕事をするでしょうね。
――始まりは、田舎の女子高生がローマの映画学校に留学するところからですね。
子どもの頃からイタリア映画に憧れていましたから。
大学受験に失敗したときに留学したいと両親に言いました。
父は高校教師で7人も子どもがいましたから裕福な家庭ではありません。
当然「お金は?」となったのですが、1年がかりで父を口説きまくって、結局、結婚資金の前借りということで、なんとかお金を出してもらいました。
――言葉の壁や、差別などはありましたか?
学校の外では厳然とありました。
でも学内はとても自由で、人種差別も男女差別もなく、かえって外国人の方がモテたりして。
自分を鼻が低いブスだと思っていたのですが「僕たちは鼻が高過ぎるから、低い鼻に憧れる」なんてお世辞を言われて、コンプレックスも吹き飛んで。
イイ女になった気分でした(笑)。
――卒業後に帰国し日本ヘラルド映画社に勤務。数年後にはヨーロッパ代表として再びローマに赴任されました。
実は、その前に映画会社の仕事に行き詰まりを感じて離職を決意。
休暇を利用してイタリアに就職活動に行っています。
でも、そのときは日本人女性なんて、まったく相手にされなくて門前払いでした。
で、すごすごと帰国したら、ヨーロッパ代表としてローマに赴任することに。
これはラッキーでした。
就活で行ったときは嫌な思いもしましたが、今度はスポンサー付きで映画買い付けの権限を持っていますから、日本人女性といってもヨーロッパの映画業界も表立っては粗略には扱えないでしょ。
私としても男性優位社会の中で見下されたり、侮られたりしないように心がけました。
ビジネスのノウハウはもとより、肩書に見合うようにセンスも磨いて。
イタリアは芸術もモードもトップの国です。
そこで対等に仕事をするにはそれなりのファッションに身を包み、それなりの見栄えを保たなければと思ったのです。
ショッピングなんてぜんぜん興味がないですが、適当にブランド物の服を選んで、それがマッチするようなプロポーションにも気を付けていました。
そう、最近は外見で判断はしない風潮ですが、それでも自分がどう見えるかに気を配ることは大切です。
身じまいは、仕事相手に対する敬意の表れでもありますから。
シングルマザーで子育てと仕事をこなす
――そこでシングルマザーで出産されていますね。
私の困ったところは、物事をよく考えないで突っ走ることですねぇ(笑)。
なんとなく30歳を過ぎた頃に、女性として生まれたからには子どもを産みたいと思いました。
男性は子どもを産めないけど、女性は産めるでしょ。
極端に言えば、出産は女性だけが持てる武器。
それを持ちたくなりました。
当然相手が必要になってくるのですが、まず父親になる男性の条件をリストアップしました。
"優しい人"とか"頭がいい人"とか"ハンサム"とか。
10カ条くらい作って、それに合う男性をいままでお付き合いのあった人の中から選んだんです。
相手だけでなく、私自身の状態も整えましたよ。
産婦人科のお医者さんのアドバイスに従って妊娠しやすい体の条件を整えて、息子が授かりました。
息子の父親は、結婚と離婚を繰り返している人で、私が息子を出産したときも何度目かの結婚をしていましたが、あくまで"私の子ども"です。
もちろん養育費など金銭的には迷惑をかけたことはありません。
――ヨーロッパでは、婚姻関係は日本と比べて比較的自由だとしても、仕事と子育ての両立は大変だったのでは。
出張が多いのでベビーシッターをつねに2人雇ってましたし、息子の友達のお母さんたちにもたくさん助けてもらいました。
父親が週末にはパリから通ってきていましたが、息子が反抗期を迎える頃にがんで亡くなってしまいました。
まぁ、その騒ぎのおかげで反抗期も自然消滅して、私の仕事をサポートしてくれるようになりました。
いまも映画の資金集めに奔走してくれています。
――製作会社NDF ジャパンを設立してからは?
国際的なプロデューサーになることが夢であり最終目標でしたから、思い切って独立しました。
思うに、プロデューサーという仕事は女性に向いていると思います。
出産もおなかの中で9カ月間育てるわけでしょ。
映画もシナリオを書いて監督を選んで、いろんな作業を経て誕生する。
同じプロセスですよね。
そのコツコツとやっていく時期が面白くて、どんな苦労があっても、やめられないですね(笑)。

撮影/吉原朱美
緑のワンピースにカラフルなポンポンが付いた衣装で。
「このワンピースは、チュニジアで買ったもの。300円よ」
第六感だけを頼りに、ここまで突っ走りました
――何度も自宅を抵当に入れたり、巨額な負債を抱えたり。その度胸の良さに驚きます。
「悪魔のリズム」(2014年)製作では120万ドルの負債を抱え大変でした。しかし「タイタス」(2000年)では120万ドルをマイクロソフトから得たのです。「タイタス」でマイクロソフトが映画への投資を決定した途端に、極小プロダクションの極小女性プロデューサーの私を排除しようとしたことからバトルが開始。マイクロソフトと、名を捨て実を取るゲリラ策略を駆使して、最終的には120万ドルのフィーを勝ち取りました。
世界一の企業マイクロソフトを相手に闘ったというプライドは、いまも私の中にしっかり根付いています。
さまざまな挫折を乗り越えながら培った映画界の縁とシックスセンス(第六感)を頼りにして、ここまで来ました。
映画の仕事をしている人間は、みんなドリーマー(夢見る人)なんですよ。
一般的な世界では見られない夢が、もしかしたら叶う可能性があるのが映画の世界。
例えば、以前の私にとってアカデミー賞受賞は夢物語でしたが、奇跡が起こった。
こういうふうに"夢が正夢になる"ことが、映画界で働く醍醐味だと思います。
――映画以外の趣味は?
ないですねぇ(笑)。
でも人間観察は好きです。
カフェで通り過ぎる人を見て「こんな主人公の映画はどうかしら?」とか考えています。
そうそう、30年ぐらい前からジム通いは続けています。
ちょっと運動をしてから泳ぐと、体全体が浄化されたようで頭も体もスッキリ。
そのまま家に帰ってゆっくりお酒を飲みながらクラシック映画を観る。
そういう時間を"my own party(私だけのパーティー)"と名付けて、楽しんでいます。
ジョギングも思考の活性化になるようで、走りながらいろんな映画のアイデアが生まれます。
いまも準備中の作品が何本もありますから、それで頭がいっぱい。
映画作りは、本当に面白いんですよ。
取材・文/金子裕子 撮影/吉原朱美、谷岡康則