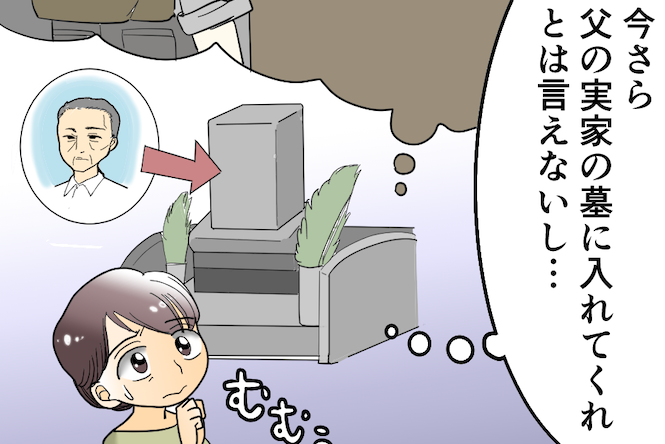卒寿を迎えた山折哲雄さん。若いころの病を経て、ある理想の最期を思い続けることになったと言います。その考えとは? 山折さんの本『生老病死』から抜粋して掲載します。

何とも捨てがたい老いの特権
八十歳の坂をこえたあたりから昼寝を貪るようになった。
朝食をとったあとや昼めしをすますと眠くなる。
ゆっくり嚙んで食べているから、半分眠っているようなときもある。
つい小一時間ほどベッドにもぐりこむ。
気分が落ち着く。
昼寝三昧である。
楽しむようになってずい分になる。
後期老人の仲間入りをしてからこんな特権を享受しようとは思いもしなかった。
もっとも老人早起き症のためか、明け方前の三時には目が覚める。
すぐには起きあがらない。
ふとんのなかでぐずぐずしている。
そのうち妄想がわいてくる。
千切れ雲の断片のようなものばかりだが、ときにそれが寄り合って奇妙な夢想のようなものをつむぎだす。
面白いことに、それがほとんど不快な気分をもたらすことがない。
ふとんのなかでぐずぐずしているのは、この妄想三昧が何とも捨てがたいからだ。
それが一段落してから、起き上がる。
頭のなかが異界の闇をはらって日常にもどっている。
軽い自己流の体操をはじめる。
両手両腕を上げたり下げたり、首を回す。
スクワットを二十回ほど。
以前は、線香を立て、脚を組んで座っていたが、左脚を痛めてからはそれは中止して、お茶をのんで呼吸をととのえることに専念している。
それが終われば、原稿用紙をひろげて、あれこれよしなきことを書きはじめる。
それもあまり長くはつづかない。
体力の衰えから気力も体力も追いつかないからだが、ふと、さきほどの妄想の断片をつなぎ合わせていることに気づく。
それはほとんど行雲流水のような作業で、なかなかちゃんとした物語の形にはならない。
それが二~三時間ほどつづき、ペンをおく。
少々口はばったいが、それがこの後期老人における執筆三昧の時間である。
私は七十代から、できもしないのにわが人生の三原則と称していっていたことがある。
食べすぎない、飲みすぎない、人に会いすぎない、と。
ところがこのごろはいつのまにか、
昼寝三昧
妄想三昧
執筆三昧
と口ずさんでいる。
幽明境をこえるときのパスポートのようなもの、と思うようになった。
絶食の病床
研ぎすまされる五感
二十代の学生のころ、十二指腸潰瘍を病んで患部と胃の三分の一ほどを切った。
けれども三十代の後半になって再発し、出先で学生と飲んでいて突然吐血し、気を失って救急病院に運ばれた。
ベッドに横たわったまま、絶食と点滴の生活に入った。
二日、三日と経つうちに耐えられない飢餓感がやってきた。
周辺にただよう食べものの匂いが針のように鼻孔を襲ってくる。
目の前で細い管を落ちていく小さなしずくをみつめているほかはなかったが、四日目、五日目あたりから変化があらわれた。
耐えがたい飢餓感がいつのまにか引いていくようだった。
それに代わって思いもしなかった清澄感のようなものが自分のからだの内部にもどっていたのである。
全身の五感が研ぎすまされていくようだった。
主要な栄養を絶たれ、枯れ木のようになっているはずのからだがにわかに生き返ったような気分だった。
いままで奥の方に眠っていた生命力が急に息を吹き返してきたのである。
私は自分自身を別の生きもののように新鮮な感覚で眺めていたが、そのことがきのうのように蘇る。
わが肉体こそまさに研究の対象になると気がついたのだ。
少々大げさないい方にはなるが、それが人生における大きな転機になった。
そのころ知ったことでもあるのだが、中世の時代、比叡山や高野山には単独で修行する行者たちがたくさんいて、体力や気力が衰えて自分の寿命を悟ると、多くが精進や断食、断水の行に入り、一週間か十日ほどのちに霊的な幻聴や幻覚をえてこの世を去っていた。
臨終のときの神秘体験といってもいいが、その振る舞いや様子が当時書かれた「往生伝」や「高僧伝」のなかに出てくる。
もちろんそのなかには、覚悟の上の往生だけがあらわれてくるわけではない。
わずかながら地獄の業火に包まれ断末魔の叫びをあげて死んでいく者の記録も出てくる。
どちらに転ぶかは誰にもわからない。
ベッドの上で退屈していた私は、いずれ自分の身の上にも最期のときがやってくるだろう、そんなときは山の行者たちがやっていたような断食往生死でいこうと、ひそかに思い定めるようになったのである。