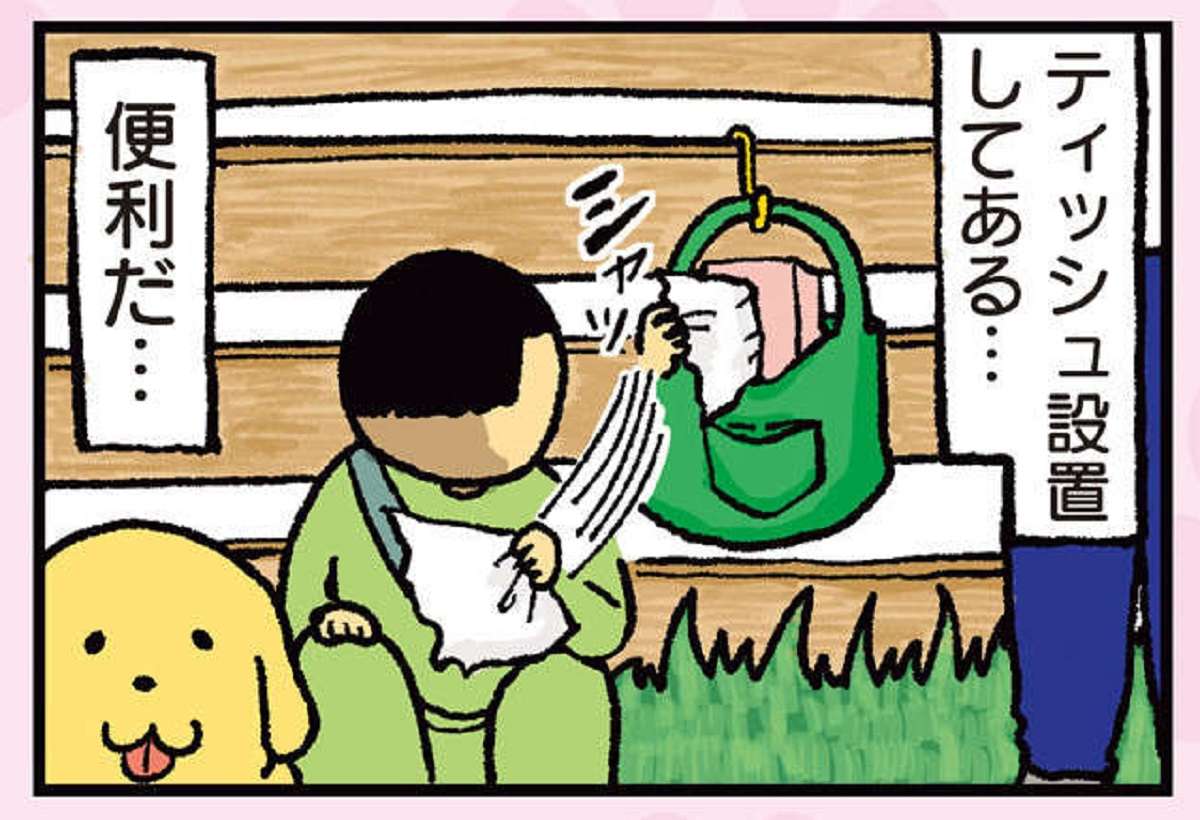江戸の裏長屋暮らしだった少年・弐吉は、直参の侍が働いた狼藉により両親を亡くし天涯孤独に。以来、弐吉は家族を奪った武家への強い恨みを胸に持ちながら、札差・笠倉屋で小僧奉公している。切米の日、米俵運びに忙殺されていた弐吉ら小僧たち。そんななか弐吉は、荷運びの指図をしていた猪作から意地悪され奔走し、空腹で疲弊しきっていた。その帰り道、商家の主人が斬られた現場に出くわし――。『成り上がり弐吉札差帖』(KADOKAWA)は、知恵と根性を武器に、札差の世界でのし上がっていく若者の出世奮闘記です。
※本記事は千野隆司:著の書籍『成り上がり弐吉札差帖』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。

『成り上がり弐吉札差帖』(千野隆司/KADOKAWA)
前章 切米の夜
一
雨は、夜のうちに止んだ。東の空が白んできたが、晴れるわけではなさそうだった。少し蒸し暑い。
浅草森田町の札差笠倉屋の店には、もう一刻(約二時間)前から明かりが灯されている。主人や若旦那、奉公人のすべてが目を覚まし、朝飯も食べ終えていた。
戦場のような一日が始まる。この日のために、何日も前から遺漏のないように支度を調えてきた。
店の戸は、まだ閉じたままだ。それなのに、店の前にはすでに数人の侍の姿があった。
「今日という日を、待ち焦がれていたのだろうな」
「まったく。二月に春の切米があって、三月待たされてようやく夏の切米が来たわけですからね」
「ああ、指折り数えていたことだろう」
「これからどんどん集まってきますね」
手代の丑松と猪作が話している。
笠倉屋にはこの他に佐吉と桑造という手代がいて、この四人はこれから店の前の蔵前通りの向こう側にある御米蔵へ出向く。皆、出入りの直参から預かった切米手形を懐にしている。
切米とは、将軍家の直参に与えられる禄米(給与)のことをいった。武家の給与は現金ではなく、米で与えられる。
家禄百俵の者は、その数量の米俵を受け取るが、それは年に三度に分けて支給された。春二月に四分の一の二十五俵、夏五月に四分の一の二十五俵、そして冬十月は残り二分の一の五十俵が支給された。
今日五月十日が、この年の夏切米の支給日となっていた。
「では、行ってまいります」
四人の手代の中で一番年嵩の丑松が、見送りに出た主人の金左衛門、若旦那の貞太郎、それに番頭の清蔵に告げた。同時に四人は頭を下げている。
「手抜かりのないようにおやり」
金左衛門が声をかけた。
「へい」
四人は返事をすると店の潜り戸の傍へ寄った。小僧の弐吉が、心張棒を外して潜り戸を開けた。中背だが奉公以来米俵を担ってきたので、肩幅があり胸厚な体だ。濃い眉で、意志のある眼差しが外に向けられた。
「おおっ」
「しっかりやってこい」
外にいた笠倉屋出入りの直参が、声を上げた。歓迎の声だ。普段仏頂面で店にやって来る者も、今日ばかりは上機嫌だった。
札差に出入りする直参を、店の者は札旦那と呼ぶ。直参は出入りする札差を、蔵宿と呼んだ。
直参の侍とはいっても、家禄の得方には二通りあった。知行地を与えられて土地の百姓から直に年貢を得る地方取りと、土地は与えられず米の現物を支給される蔵米取りとに分けられた。
直参で蔵米を得るのは、おおむね禄高の低い小旗本や御家人たちである。
丑松らが御米蔵に駆けてゆくのを見届けた弐吉は、いったん潜り戸をしめた。弐吉を含めた五人の小僧は、土間に待機する札旦那のための縁台を用意する。そこには煙草盆も置いた。
外の軒下には、昨日のうちから空の荷車が並べられている。小僧たちは、臨時雇いの荷運び人足たちと共に、この荷車で支給された米俵を札旦那の屋敷に運ぶ。
札差の仕事の中心は、札旦那から依頼を受け、御米蔵から禄米を代理受領して換金をすることだった。札旦那たちは、支給された禄米の中から自家消費用の米を差し引いて換金し、それを現金の収入とした。
本来禄米の受領と換金は、蔵米取りが自らおこなうものだった。支給日には、受領する米の量やお役目、氏名などが記された切米手形を御蔵役所に提出して順番を待った。そのときには、入口に立ててある大きな藁苞に手形を挟んだ竹串を差した。これが差し札と呼ばれるもので、蔵米取りは自分の番がくるのを長い行列を作って待たなくてはならなかった。
受け取った米は、自ら米問屋へ運んで換金する。武家には慣れない手間のかかる仕事だった。
そこで登場したのが「札差」という商いだった。
札差は、蔵米取りに代わって差し札を行い、米を代理受領して米問屋に売却するまでの煩瑣な手間を請け負った。代金を渡し、売らなかった自家用の米を屋敷へ届けるまでを役目とした。
これらの一切を引き受けて、手数料を得る。蔵前通りには、多数の札差が軒を並べていた。どの店も、重厚な建物だ。
弐吉は十歳のときに笠倉屋へ奉公し、八年がたった。切米は何度も経験している。段取りなどはすべて頭に入っていた。そろそろ御蔵屋敷での代理受領の手続きや受け取りなどの仕事もしてみたいが、それは小僧にはできない。
早く手代になって、そういう仕事もしてみたいと思うこの頃だ。他の店では、同い歳で手代になる者も現れてきた。負けない働きをしてきたつもりだが、そういう声は一切かからなかった。
明け六つ(午前六時頃)の鐘が鳴って、蔵前通りが明るくなる。この頃には、荷を運ぶために移動する荷車や、売った禄米の代金を受け取ろうとする直参の姿が多くなった。
「お待たせいたしました」
笠倉屋でも、店を開けた。外にいた札旦那たちが、店に入ってくる。お文や下働きの女中が茶を運んだ。この日小僧は、米俵の運びに忙殺される。
札旦那の屋敷は、一か所に集中してあるわけではない。江戸は広く、直参の屋敷はお城を中心に四方八方に散らばっていた。
笠倉屋を蔵宿とする札旦那は、百二十一家あった。このすべての屋敷に、今日を含めて三日から四日の間に、すべての自家用の米俵を運ぶのは、なかなかにたいへんだった。米俵はかさばる上に重い。また多くの家が、早い配達を望む。
蔵宿は、それに応えなくてはならない。
今日中に運ぶのは八十家ほど。地域ごとにまとめて運び、一家ずつ降ろしてゆく。誰がどこを、どう廻るかは事前に決めていた。札旦那は代々変わらないから、道順はきっちりと弐吉の頭の中に入っていた。無駄な動きにならないように、注意をした。
手代たちは、この日までに札旦那から切米手形を受け取り、換金する米の量を聞いておく。毎年、大きな変化はないから、買い手の米問屋とはすぐに話がついた。
「うむ賑わっておるな」
身なりのいい四十年配の侍が、用人を伴ってやって来た。
「これはこれは、黒崎様」
帳場の奥にいた、金左衛門が上がり框のところまで出てきて迎えた。
「お陰様で、滞りなく進んでおります」
黒崎家も札旦那だが、他の旦那たちとは対応が別だった。黒崎禧三郎は、家禄四百俵で御納戸組頭を務める旗本だ。笠倉屋出入りの直参の中で、一番に高禄なのがこの黒崎だった。
副収入もあるらしく、金に困ってはいない。札差は禄米の換金の他に、金融もおこなうが、黒崎家は一文の借り入れもしていなかった。
「米の搬入は明日でよい。待っている家が多かろう」
「ははっ。番頭がついて伺います」
一口に札旦那とはいっても、黒崎のような高禄の御目見もいれば、微禄の下役や無役の者もいる。ただ二百俵を超える御目見でも、苦しいところは苦しい。黒崎は、例外といってよかった。
「では、邪魔をした」
黒崎は、様子を見に来たのだ。長居はせずに引き上げた。
その直後、二十人余りの荷運び人足が現れた。大きさの異なる十台の荷車が店先に並んでいる。これは自家用米輸送のために、笠倉屋が借り受けたものだ。店の荷車は、弐吉ら小僧が使う。
「では行きますぜ」
人足たちが、荷車を引き出した。御米蔵にいる丑松や猪作らから、受け取った米を問屋や笠倉屋へ運ぶ。笠倉屋へ運ばれた自家用の米は、各札旦那の屋敷に運ばれる段取りだ。
この頃には、米俵を積んだ荷車が、次から次へと蔵前の幅広の道を行き過ぎるようになった。車軸の擦れ合う音が響く。
雨上がりで水溜まりが各所にあるが、人足たちは気にしない。泥水を撥ね飛ばして進んでいった。
泥濘に、新しい轍を作って行く。
最初の米俵が、店についた。いよいよ弐吉ら小僧による荷運びが始まる。すぐに積み替えをおこなった。
「気をつけろ」
清蔵に言われた。早く荷運びを終えたい人足たちが急いでいる。無茶な運び方をする者がいるから、それに気をつけろという意味だ。通行人に怪我をさせてもいけない。
弐吉は雇いの人足二人と共に、まずは四谷方面の直参の屋敷を四家廻った。雨上がりの泥濘で、重い荷車を引くのは骨が折れる。
「おお、よく来た。よく来た」
声をかける前に、向こうから飛び出してきた。おおむね歓迎される。これは気分がよかった。
米俵の受取証を貰うと、次の屋敷へ向かった。
廻り終えて店に戻ると、丑松や猪作らの手代たちが戻って、売った米の代金を札旦那たちに渡していた。こちらから持って行ってもいいが、待ち切れず受け取りに来る札旦那が多かった。
「そこいらで、いっぱいやろうか」
「うむ。そうだな」
などと話をしている札旦那もいる。通りには、それを見越して酒を飲ませたり団子や饅頭を食べさせたりする屋台店が出ていた。
何回か店と札旦那の屋敷を往復した。休む暇もない。戻ればすぐに、次の屋敷へ向かわなくてはならなかった。
昼飯は、作り置かれている握り飯を頰張った。
急いでいた弐吉が店の前で出会ったのは、梶谷五郎兵衛という札旦那だった。袂の裾が擦り切れた着物で、袴は薄汚れている。一月ほど前に金を借りに来て、対談をした猪作に断られた札旦那だ。弐吉は慌てて頭を下げた。
「金子を受け取ったならば、これから支払いに廻らねばならぬ」
梶谷は気取らない。そんなことを弐吉に漏らした。
「すべて支払いを終えたら、どれほど残るかのう」
と続けた。出入りする札旦那は、黒崎のような者はごく少なくて、あらかたが梶谷のような懐に余裕のない侍たちだった。
弐吉が芝の札旦那の屋敷を廻って店に戻って来ると、すでに夕暮れどきになっていた。この頃になると、店にいる札旦那の姿が減ってきた。金子を受け取った者たちは、すぐに引き上げる。
「ふう」
とため息を吐いた。休む間もなく荷車を引いたり押したりしたが、ようやく初めに決まっていた分については運び終えることができた。小用を足す暇も惜しみながら動いた。ただまだ運び終えていないところもあるから、それがあれば手伝いの仕事となる。
骨惜しみをするつもりはなかっが、腹は減り始めていた。
このとき荷運びの指図をしていたのは、猪作だった。近くには、大福帳を手にした貞太郎が立っていた。
「おい」
目が合うと、猪作が声をかけてきた。倉庫の前だ。他にも小僧はいたが、猪作は弐吉に顔を向けていた。
「へい」
「この四俵を、本郷御弓町の村田豊之助様の屋敷へ運べ」
にこりともしない顔で言った。誰かをつけるとは言わない。一人で行けという意味だった。
「下谷龍泉寺町ではありませんね」
すぐにこの場を離れようとする猪作の背中に、弐吉は念を押すように言った。村田姓の札旦那は、二家あった。
「そうだ」
猪作は、振り向きもしないで答えた。
嫌な予感があった。猪作は面倒な仕事や厄介な役目を、弐吉に押し付けてくることが少なくない。理由は分からないが、嫌われているのは感じていた。
ただ今日中に運ばなくてはならないのならば、行かなくてはならなかった。
弐吉は、一人で荷車に四俵を積んだ。本郷御弓町は、蔵前から近いとはいえない。荷車が屋敷前に着いたときには、だいぶ薄暗くなっていた。
「何だ、米か。しかし笠倉屋からは受け取っているぞ」
出てきた当主からそう告げられた。寄こすならば受け取るが、と続けられた。
「さ、さようで」
慌てた。そしてすぐに、「やられた」と胸の内で叫んだ。猪作の意地悪だと察したのである。
「すみません」
弐吉は荷車を引いた。おそらく、下谷龍泉寺町の村田家だったのだろうと察した。
店に戻って確かめてもよかったが、ここは間違いないと感じた。戻るとなると手間だ。
「くそっ」
腹は立ったが、とにかく急いだ。札旦那の屋敷では、待っているはずだった。
猪作は若旦那の貞太郎に気に入られている。それを良いことにして、年下の手代や小僧たちには、偉そうな態度を取っていた。
「貞太郎に媚を売っている」
と思うが、それを口に出すことはできない。他の小僧からも嫌われているが、特に弐吉には厳しく当たってきた。
下谷龍泉寺町の村田家へ辿り着いた。急いだので、汗びっしょりだ。
「ごめんくださいまし」
笠倉屋から来たと告げると、当主が飛び出してきた。
「遅い。何をしておった」
とどやされた。
腹を立てるのは当然だと思うから、弐吉はただ頭を下げた。さんざん苦情を言われた。猪作の意地悪だとは言えないから、弐吉は謝るしかない。
そして空腹に耐えながら空の荷車を引いて蔵前通りへ戻った。腹の虫が、しきりに鳴く。体力や膂力には自信があったが、空腹には勝てない。
道の途中で、暮れ六つ(午後六時頃)の鐘が鳴った。
まっすぐに延びる蔵前通りに出たときには、すっかり暗くなっていた。米俵を積んだ荷車で賑わった通りも、すでにしんとしている。
明かりが灯っているのは居酒屋など、飲食をさせる店だけだった。提灯を手にした通行人の姿が多少ある程度だ。
「おや」
ここで弐吉は、足を止めた。天王町のあたりだ。離れたところに提灯の明かりがあり、そこで人が縺れる姿を目にしたからだ。
「あれは」
刀を抜いて町人に襲い掛かる侍の姿が見えた。町人が手にしていた提灯が、地べたに落ちた。
「うわっ」
という叫び声。斬りつけた侍は、すぐに闇に消えた。
もう一人、刀を抜かない侍がいて、その者が屈んで倒れた町人の体に触れた。それからすぐに立ち上がると、その場から離れた。
二人とも頭巾を被っていた気がしたが、自信はない。
弐吉は荷車をそのままにすると、事の起こった場に駆け寄った。人が斬られたのならば、そのままにはしておけない。
そこで新たな悲鳴が上がった。女の声で、近くの者らしい。倒れている者に気が付いたからか。
弐吉がその場に駆け寄ると、濃い血のにおいが鼻を衝いてきた。商家の主人ふうが、斬られて倒れていた。事件に気づいた近所の者も、姿を現した。提灯を手にしていて、倒れた体を照らしている。
「あっちへ逃げたぞ」
そういう声があって、弐吉を交えた数人が追いかけた。相手が侍でも、怖いとは感じなかった。こちらは一人ではない。
また喧嘩となれば、そこら辺にあるものを武器にする。子どもの頃から負けたことはなかった。少しは役に立てると思った。
けれども通りは、すでに闇に覆われている。逃げる人影は見当たらない。賊を追うことはできなかった。