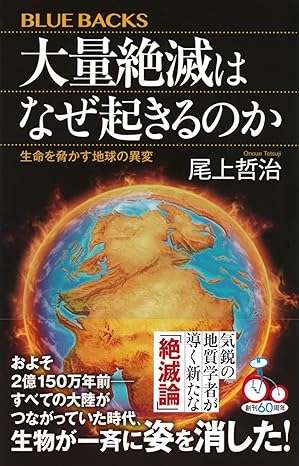第一章 鬼っ子さま
今朝はえらく朝靄が立ち込めていた。
夏場でもこの滝の周辺は爽涼としている。さほど大きな滝ではないが、深い森から生まれた水の流れは豊かで、岩肌を伝って落ち、涼やかな飛沫を上げ続ける。
鋒国はいつものように、滝行を済ませると、濡れた衣と晒を脱ぎ、素早く乾いた布で身体を拭き、晒で胸を巻き始めた。
さほど膨らんだとも思わないが、近頃、胸を締め付けるのが少し辛い。
質素な筒袖の上衣に袴を身に着け、濡髪を若衆髷風にまとめ上げると、傍目には少年にしか見えない。とはいえ、鋒国はれっきとした女である。
本名は美禰という。
正直、いつからこの恰好をしているか、鋒国は覚えていない。一緒に住んでいる大叔母のおつかによれば、十年前、月国は六歳の美禰に鋒国の名を与え、これからは男として過ごせと命じたらしい。
月国というのは美禰の祖父の名で、家はこの地で代々刀匠をしている。日本刀の祖とされる「天国」の流れを汲み、その高い技は唯一無二、一子相伝とされる。
しかし、後継者となるべき息子が死んでしまい、その代わりに孫の美禰が選ばれたというわけだ。
本来、鍛冶場は女人禁制とされる。女が鍛冶場に入るのを、鉄を司る神が嫉妬するからとか、月経を血の穢れとみなすからとか、色々言われるが、実際、火花の舞う中、女が大きな槌を振るうのは体力的にも精神的にもかなりきつい。
だから、女が刀匠を継ぐことはできない。それが定めのはずだ。しかしなぜか、祖父は美禰に継がせると決めたらしい。
そこにどういう思いがあったのか、きちんと聞いたことはないが、ともかく美禰は「男となり鍛冶場に入る」という厳命を守っている。
朝の滝行もその一環で、ここの清流で身を清め、水を汲んで鍛冶場に持ち帰るのが、彼女の役目の一つなのだ。
おつかは鋒国が不憫だと言うが、鋒国自身は自分が可哀そうだとも男装が嫌だとも感じたことはない。幼い頃から、祖父が作る刀の美しさに心惹かれていたし、鍛冶場に入る祖父の側にいられることが、嬉しかったからだ。
紀伊半島のほぼ中心に位置する奈良大峯山――修験道の祖・役行者が開山し女人禁制で知られるこの霊峰を仰ぎ見る場所に、鋒国は祖父・月国、大叔母おつかの三人で暮らしている。屋敷と呼べるほど大きな家ではないが、茅葺の大屋根のある母家とは別に鍛冶場、畑も少しあり、暮らしていくのに困ることはない。
見渡す限り山また山、人よりは獣の方が多い山里だが、南は熊野詣で有名な熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)、西は弘法大師開山の高野山、東には伊勢神宮と、いずれも聖地に繫がり、さらに北はひと目千本の桜で知られる吉野山を経て、京の都へ至るという自然豊かな場所である。
また、家のすぐ近くには熊野川を源流とする清流が流れていて、神刀を打つのに最適な清々しい氣が満ちているのだ。
このひと月、丹念に造り続けてきた刀が、ようやく焼き入れの最終段階を迎えていた。
鍛冶場の暗闇の中、赤く熾きた炭と炎に照らし出される祖父の横顔を見る度、鋒国は強い憧れと、身が引き締まるような畏れを同時に感じる。
額に深く刻まれた皺、白髪交じりの眉や窪んだ瞼に似合わぬ強い眼差し――。
月国の名を冠した刀は霊力を持つと、そう誉れ高い名匠の横顔だからだ。いや、名匠と呼ぶのも適当とは思えない。四方に張り巡らされた注連縄の中にいる月国は、神にその身を捧げた稀人と呼ぶ方がふさわしい。
「うむ」
炎の中を凝視していた月国は小さく頷くと、火床から取り出した刀身を、水の入った細長い桶に素早く移した。
ぶわっと水煙が立ち、刀身は清廉な水により洗われ、姿を現す。
「ふっ......」
小さな息遣いと共に月国の目元が緩んだ。
暗闇の中で、美しい反りと霞のような刃文を持った刀身が浮かび上がる。まるで、夜空に浮かぶ月のようだ。
満足のいく出来なのだろう。月国は目を閉じ、静かにゆっくりと息を吐いた。
稀人が人に戻っていく――。
それを見届けてから、鋒国もまた静かに息を吐き、頭を垂れた。