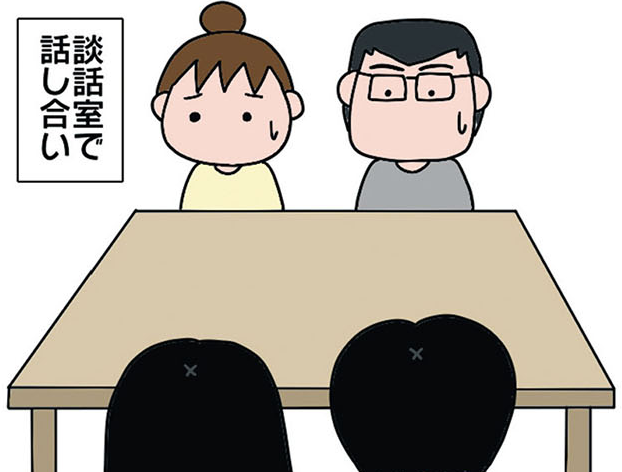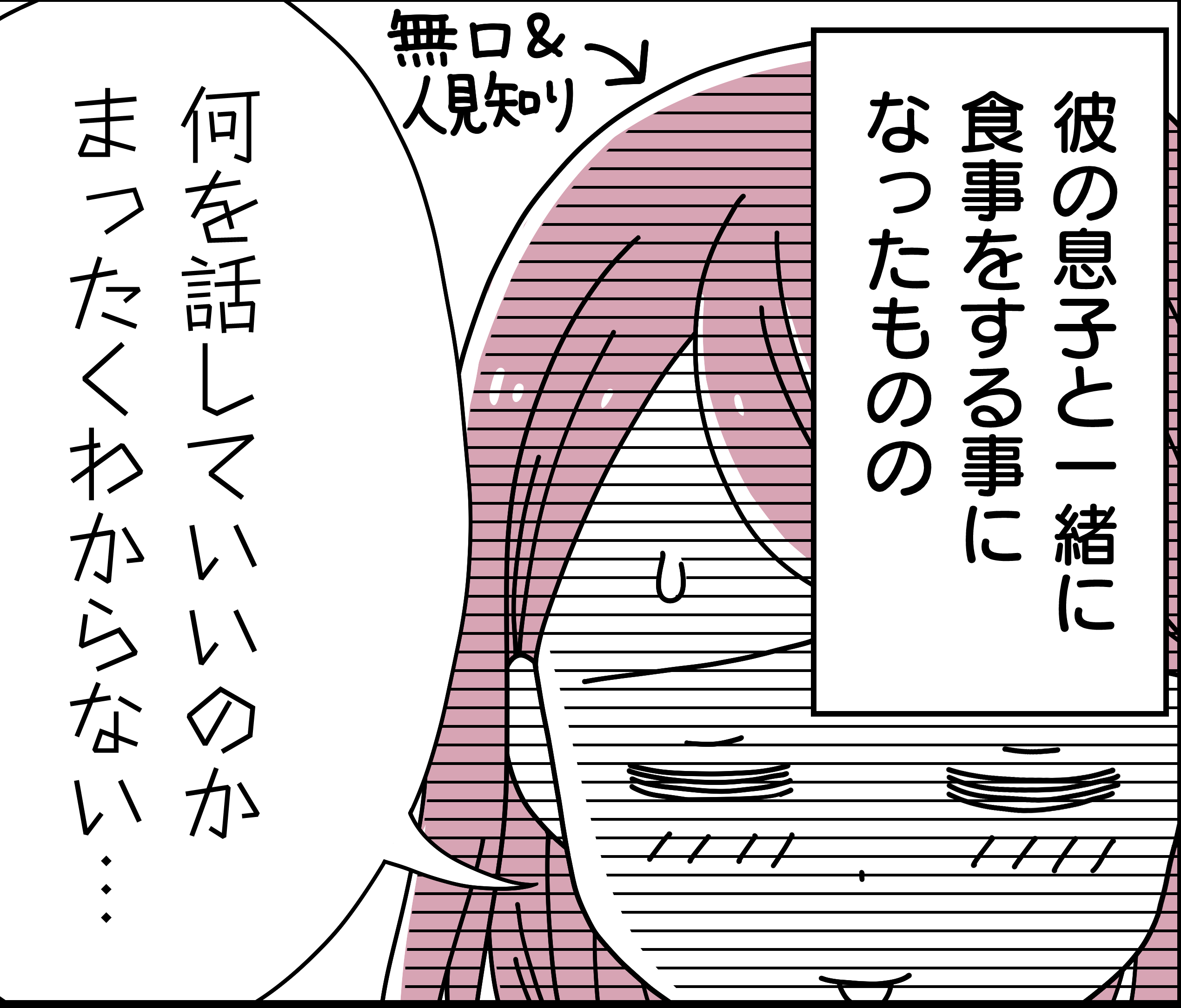(C)新潮社
年齢とともに気付く地方暮らしの幸福感
――最新刊『母の待つ里』には、60代を迎えた都会の男女3人が登場。あるきっかけから、3人は自然豊かな地方に暮らす"ちよさん"という高齢の女性に理想の故郷を求め、帰郷するようになります。
地方に住んでいる人は、それが当たり前のことだから、自分が暮らす自然環境の豊かさに気付いていないと思うんですよ。
僕は東京生まれの東京育ちで、これまで東京はいいところだと思ってきたけれど、60を過ぎてそれは幻想だと思うようになった。
それまで気付かなかった自然の良さがしみじみと感じられるようになって、都会暮らしというのは本当に幸せなのか、何か違うのではないかという疑問が生まれてきたんです。
この話に出てくる3人も皆、都会人。
三者三様、一生懸命やってきた成功者です。
ではいまが幸せかというと、やはり皆、疑問を感じている。
1人は大手食品会社で社長になった男性ですが、社長になるというのは当然、犠牲にしてきたものも多い。
家庭を築くことなく、ここまでやってきて、それは3人目に出てくる一途に医学を志してきた女性も同じ。
もう1人の男性は典型的なサラリーマンですが、定年を迎えて、熟年離婚を言い渡される。
しかも娘2人は冷たい。
これはよく聞く話で、僕らは親孝行が当然の世代ですが、子ども世代はまた意識が違う。
その違いにいまさら気付いて、こんなはずじゃなかったと思っている60代以降の方も多いのではないかと思います。
考えてみれば、いまの60代はアメリカナイズされた最初の世代。
よほど社会福祉が充実していないと年配者が孤立してしまう。
いまの日本は、まさにこの問題が残っていると感じます。
――作中の"ちよさん"も、地方で独り暮らしです。
いまの日本はどうしても若い世代が都会へ出て行くから、年配者が地方で独り暮らしをすることになる。
ただ、ここ数年、コロナもあって、その流れとは逆に都会から地方に移住する人も増えてきた。
この話も最後、都会で生きてきた3人が地方に移住して自然に回帰する人生を選ぶのではないかというところで終わらせています。
それがいまの状況を変える唯一の方法ではないかと思っているんですよ。
 (C)新潮社
(C)新潮社
「迷ったら、捨てるのが正解。スーツやジャケット、洋装は流行があるので、古くなったら捨てるようにしています。昔の手紙は全部捨てます。焼いてしまいます、ストーブで(笑)。誰かの目に触れたらイヤだもの」
婦人服業界に就職デビュー後も兼業して
――先生は10代の頃から作家を志していらしたのに、まず自衛隊に入られたのは?
それは三島由紀夫がきっかけです。
だって、おかしいでしょう、小説家が自衛隊であんなことをするなんて。
そのとき、自分は小説家になろうとしていたわけで、気持ち悪くてなりませんでした。
生前の三島さんを見たことがあるんです、後楽園ジムでガラス越しに。
これは大変なことが起きた、自分も入ってみないと分からないと自衛隊に入って、さぞ文学少年ばかりだろうと思ったら、僕だけでした(笑)。
その後、作家では食べていけないので婦人服業界に就職しました。
デビュー後もしばらくは兼業作家でした。
見てくれは大事ですね。
僕は両親も祖父母も典型的な東京人。
東京は江戸の昔から人口が過密で人間の距離が近い。
だから、人目を気にする文化が生まれたんだと思うんです。
要は世間体を気にして見栄っ張りなんですね。
例えば、うちのジイさんはとんでもないろくでなしのばくち打ちだったけれど、たばこ一つ買いに行くときもよそ行きに着替えていた。
おかしいでしょう?
でも、年をとると、そういう気概が大事だと思えてくるんです。
だって筋力は衰えてくるわけで、意識しなければ、背筋が丸くなるのは当たり前。
頭もボケボケなんだけど、ボケていないように見栄を張る。
多少の不調があっても、つまずいたら格好悪いもの。
いまは「よそ行き」という感覚がどのぐらい残っているか分からないけれど、年齢を経るということは、それだけ自分の「よそ行き」のファッションにキャリアがあるということ。
そう考えると、女性だって同じ、年齢を経るほどすてきになっていくのは、当然なんですよね。
60には60の、70には70の美しさがあると思います。
婦人服のプレタポルテをデパートに納品する仕事をしていて感じましたが、シンプルであり、かつナチュラルに着こなせるのは大人の女性だからこそ。
シンプルというのは、若い頃に足し算のおしゃれを経験している大人だからたどり着ける、引き算の境地だと思います。
60代以降の豊かさを支えるものとは?
――ご自身は介護のご経験がおありですね。
幼い頃に両親が離婚して、それぞれに家庭を持っていたから、介護する機会が人より多かったんですね。
そのときに支えになったのが、哲学者カントの「義理すなわち義務」という言葉です。
自分の利益を中心に考えるようになると、血縁のある親ならともかく、義理の親の介護というのをどう受け止めるのかが大切です。
「義理すなわち義務」という考えが自分のベースにあるかないかで、受け止め方が全然違ってくると思うんです。
少し気持ちが楽になるところもあるのではないかと。
するとまず、老いに対する意識が変わってきます。
失われるものばかりではなく、老いたればこそ見えてくるものが多くなってもくる。
だからこそ得られるものがある、そこに意識することです。
また心身の衰えは、回復させようとすると負担が大きいので、ここを"慣れていく"ことに意識を向けます。
これができれば無理がなくなり、仕事に支障をきたすこともなくなります。
ちなみに拙著『天国までの百マイル』は、会社が倒産、会社も金も、妻子までも失った男が、女手一つで4人の子どもを育てた母親のために、心臓病の名医のもとへ車を走らせていく物語。
実体験のエピソードが詰まった、ほぼ実話です。
各国で翻訳されているので、グローバルなテーマなんでしょうね。
そんな小説を書けたことを、義母に感謝しています。
それでもやはり、親の介護の末、看取った後に"やり切った"と思えないのは当たり前。
悔いは必ず残ります。
だから気持ちの整理はできないし、する必要もないと思っています。
――年齢を重ねることについては、どのように受け止めていらっしゃいますか?
『毎日が発見』っていいタイトルだなと思うんだけど、近頃、しみじみそう思うんです。
小さなことでもね。
例えば今朝、パンを切らしていたので、普段は外食なんてしないんだけど、思い立って某レストランのモーニングに行ってみたんですよ。
そうしたら、洋風のモーニングプレートなのに醤油が出てきた。
何か間違っていないか、本来は塩胡椒だろう、それとも俺が70のジジイだからか?と思ったけれど、これも毎日が発見。
結局、家でご飯を炊いた方がおいしいという結論に至りました。
もともと家事は好きなのですが、この前ふと気付いたら、ジイさんの話じゃないけれど、自分も1日に3回は着替えているんですよ。
書斎が座敷だから、原稿を書くときは着物が一番楽なんです。
だから、宅配便が来ると慌てて着替えるんですよ。
散歩に行くときも当然、着替えます。
そして杖も持つんです、見栄で(笑)。
取材・文/多賀谷浩子 撮影/新潮社 イラスト/小川温子