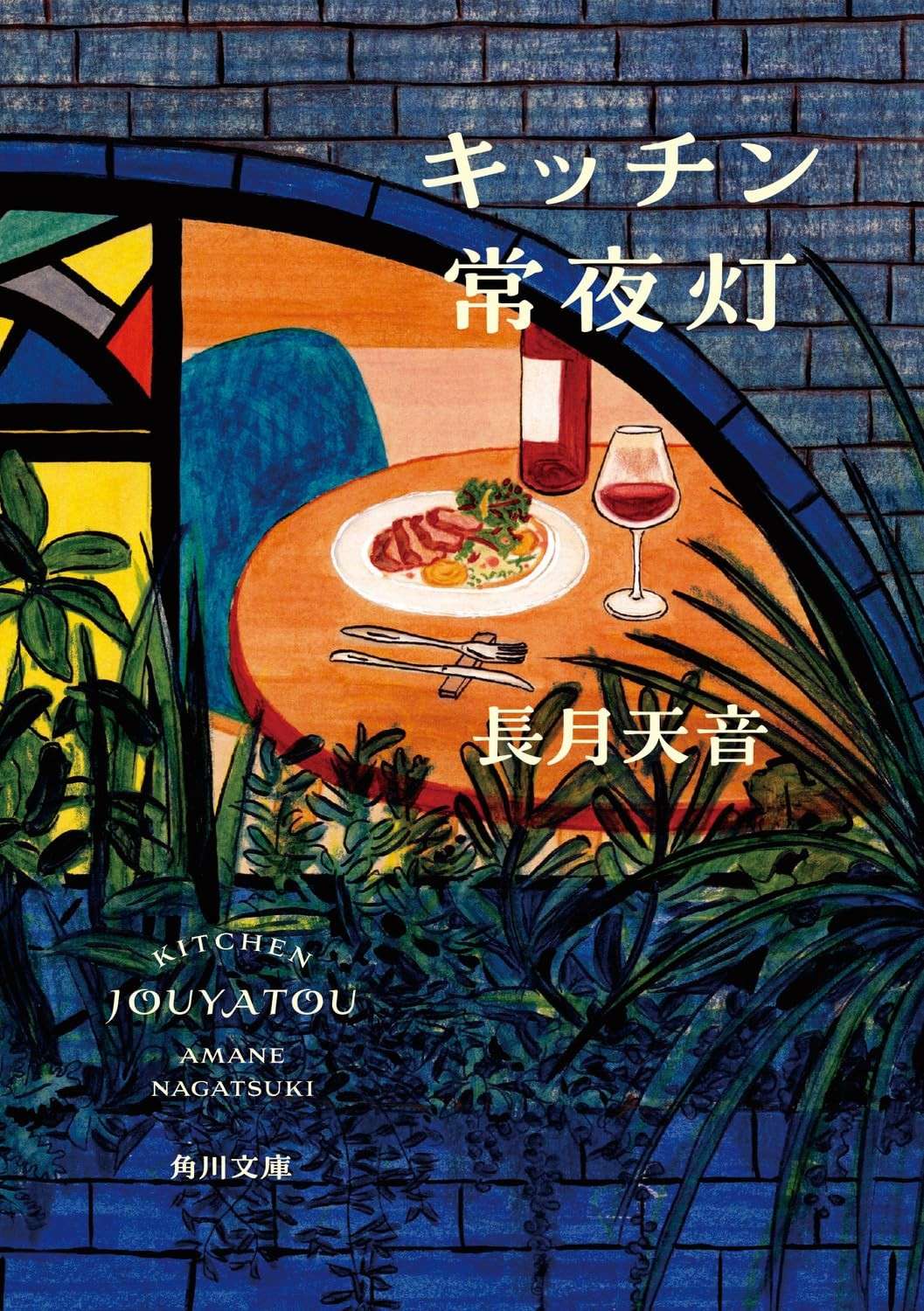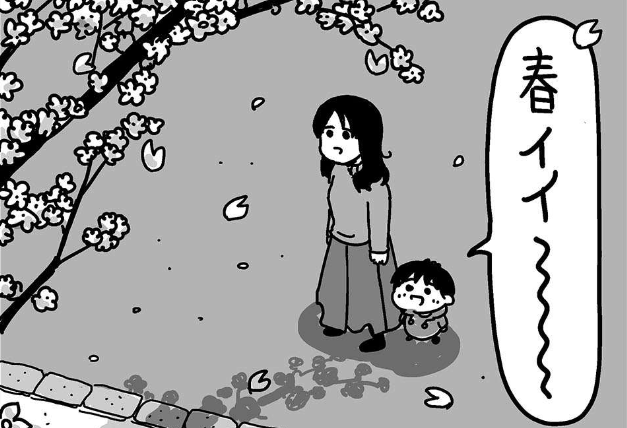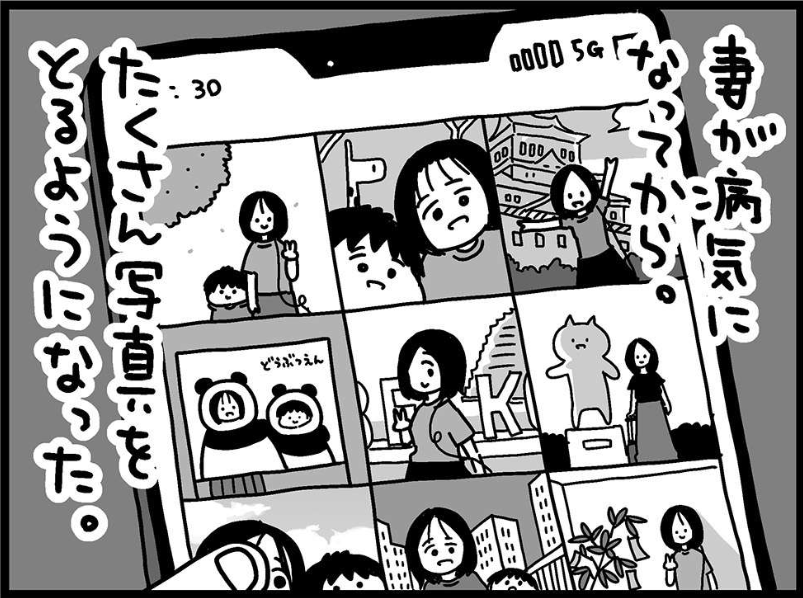目の前の東京ドームホテルや遊園地のアトラクションの明かりが、この時間でも街を暗闇にすることなく、夜空に浮かんでいるのが心強い。しかし、明るいのは駅の周辺だけで、白山通りを渡ってビルの間に入ったとたん、コンビニの一軒もなくひっそりと静まり返ってしまう。
お腹が減った。
考えてみれば、朝からほとんど何も口にしていない。
朝食を食べないのはいつものことだが、今日はバイトが二人も風邪で欠勤してしまい、休憩どころではなかったのだ。
賄いは食べそびれ、口に入れたものと言えば、大村さんが買ってきてくれたエナジードリンクのみ。我ながら燃費のいい体だ。
毎晩仕事を終えたとたん、麻痺していた空腹感に襲われる。すぐにでもどこかの店で食事をしたいが、何せその時間はどこもラストオーダーを過ぎている。空腹とはいえ、居酒屋は少し違う気がして、私は時に終電を気にしながら家に帰るしかない。これはきっと飲食業界で働く者の永遠の悩みに違いない。
私は今夜も空腹にふらつく足をやっとの思いで前へ進めていた。
ふと思う。「店長」という役職はまるで鎧だ。
勝手にずっしりと重い責任を押しつけられ、常に前線に立たされる。けれど鎧を着ているから大丈夫というわけではない。店長だからこそ向けられる言葉の刃に傷つき、スタッフとの意識の差が矢のように胸に突き刺さる。店を出て鎧を脱ぎ棄てれば、私の体は満身創痍だ。
ようやく倉庫にたどり着くと、金田さんに渡されている鍵でひっそりとビルに入った。
金田さんは私が帰宅した時にはたいてい眠っている。早朝から店舗の設備点検に出かけることも少なくなく、毎晩十時には布団に入るのが習慣だそうだ。
とりあえず何かをお腹に入れようと、金田さんの台所に直行した。
あるものは自由に使っていいと言われているけれど、職場が飲食店のせいか、家でまで料理をしたいとは思えない。これまではコンビニを冷蔵庫がわりに使い、休みの日の外食が唯一の楽しみという生活だった。
金田さんは几帳面な性格で、台所はいつもきれいに片づいている。毎日自炊をしているそうだが、買い置きの習慣がないらしく、余分な食材やインスタント食品はほとんどない。
やはりコンビニに寄ってくるのだったと後悔しながら、唯一見つけた魚肉ソーセージのフィルムをむいた。
「あれれ、みもざちゃん。おかえり」
突然、声をかけられて振り返ると金田さんが立っていた。
「すみません、起こしてしまいましたか」
「いやいや、明日は休みだから本を読んでいたら、すっかり夢中になってしまってね」
本社勤務の金田さんは、急なことがない限り週末が休日だ。一方の私は、週末は平日よりもずっと忙しい稼ぎ時である。
「ごめんね。冷蔵庫、空っぽだったでしょ。今夜は総務の涌井さんと一杯やってきちゃったんだ。明日、買い出ししてくるよ。夜中でも簡単に食べられそうなもの」
金田さんが心からすまなそうな顔をするので、私は慌てて両手を振った。
「あっ、自分で買いますから、お気遣いなく」
「みもざちゃんは料理しないの?」
「毎晩遅いですから。休みの日は気分転換に外に出たいですし」
「この仕事だとそうなっちゃうよね。寮の頃もみんなコンビニ弁当ばっかりだったもんなぁ。ゴミが溜まる溜まる」
金田さんは眉を下げて笑った。学生寮とは違い食事の世話はなく、寮夫の仕事は掃除やゴミの回収が中心だったようだ。
「このあたりって賑やかかと思ったら、意外とお店が少ないですよね。コンビニも駅を逃すとほとんどないし」
金田さんはう〜んと唸った。
「そうなんだよね。大通り沿いのお店も意外と早く閉店しちゃうし。ああ、でもね、前にすぐ近くで美味しい料理を食べたんだよ。真夜中だけど、そこだけやっていたんだ。ええと、なんていう名前だったかな」
「すぐ近くですか?」
「うん、一本横の細い通り。三年くらい前かな。横浜店で水漏れがあって、閉店間際に呼び出されたんだよ。色々と手配して、帰ってきたのがもう真夜中。お腹が空いちゃってさ、通りを一本間違えたんだよね」
金田さんは笑いながら頭をかいた。
「そしたら、ぼんやり明かりが点いた店があったの。嬉しくなって、誘われるように入ったんだよ。あの時のコキールグラタン、美味かったなぁ」
「コキールグラタン?」
「そう。ちゃんとした洋食屋だったんだ。帆立の殻に入ったグラタンだよ。まさか夜中にそんな料理食べられると思わないじゃない。グラタン、カミさんの得意料理だったんだよねぇ。何だかあの夜は夢を見ているような感じだったなぁ」
本当に夢を見たのではないかと思った。でも、実際にそんなお店があるのならぜひ行ってみたい。真夜中に本格的な洋食を食べさせてほしい。
「今もやっているのかな。あれ以来、行っていないから」
教えられた場所はここよりも一本外堀通りに近い路地で、横道を抜ければすぐの近さだった。
「さっそく明日、探してみます」
「うん。あるといいね」
金田さんは戸棚の奥をあさると、「僕の非常食」と言って、甘納豆を一袋くれた。
「ありがとうございます」
「おやすみ、みもざちゃん」
甘納豆なんて何年ぶりだろう。子供の頃、おばあちゃんがよく食べていたのを思い出す。何だか金田さんとの暮らしは温かい。
私は甘納豆で空腹を紛らわせ、シャワーを浴びてベッドにもぐり込んだ。
真冬のシャワーでは体は温まらず、布団の中でぎゅっと体を縮めて丸くなった。
倉庫に来てからはシャワーばかりで、一度もバスソルトを使っていない。前よりも通勤に時間がかかり、その分早く寝なくてはと気持ちが焦って、とてもお風呂になど浸かる気にならないのだ。
冷えた体はさらに意識を冴えさせる。遠くのほうで聞こえたサイレンに怯えながら、私はじっと息を殺して朝が来るのを待ち続けた。少しでも眠れることを願いながら。