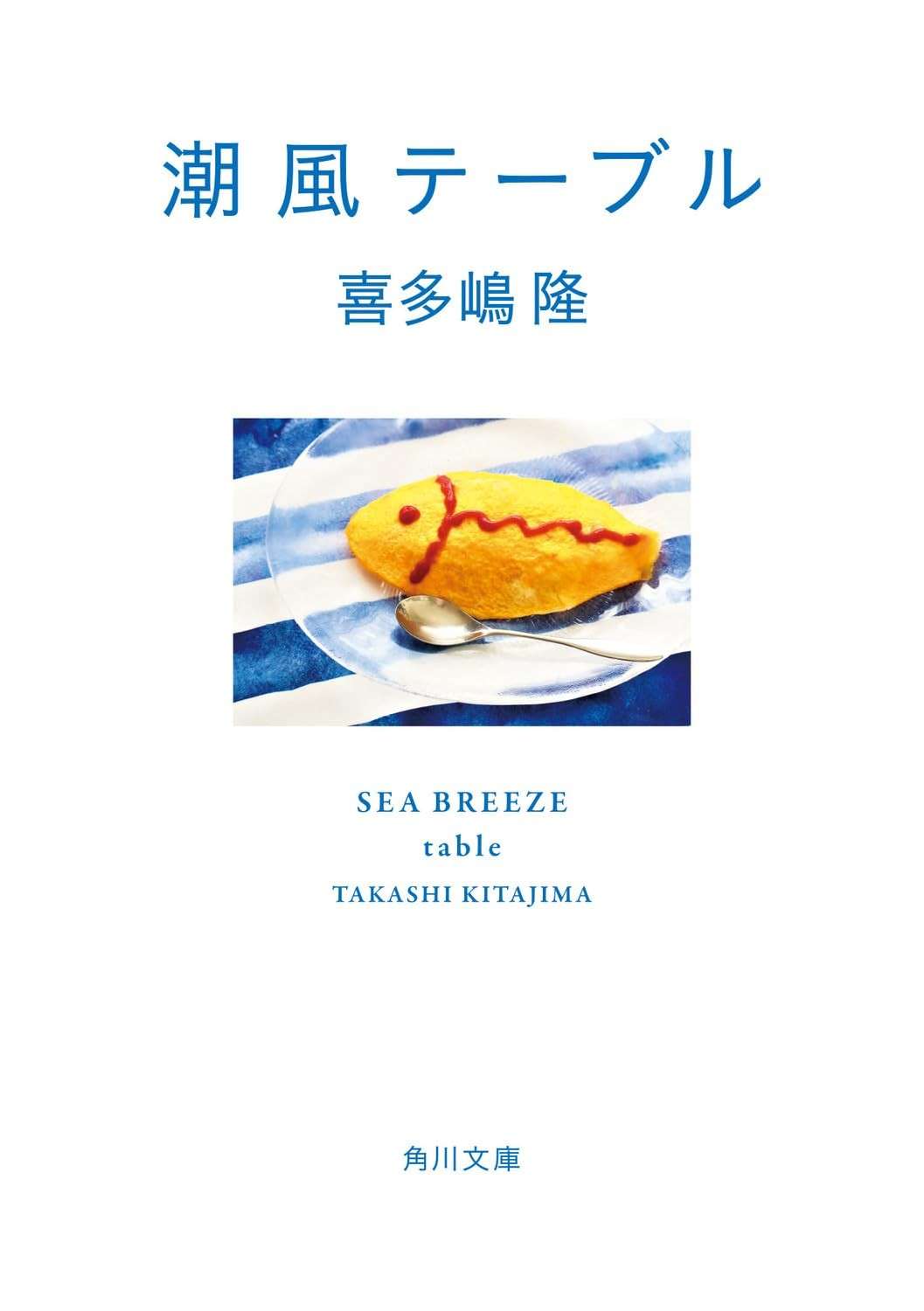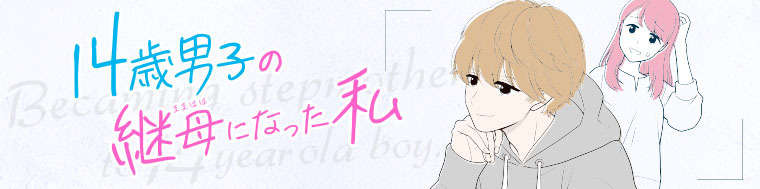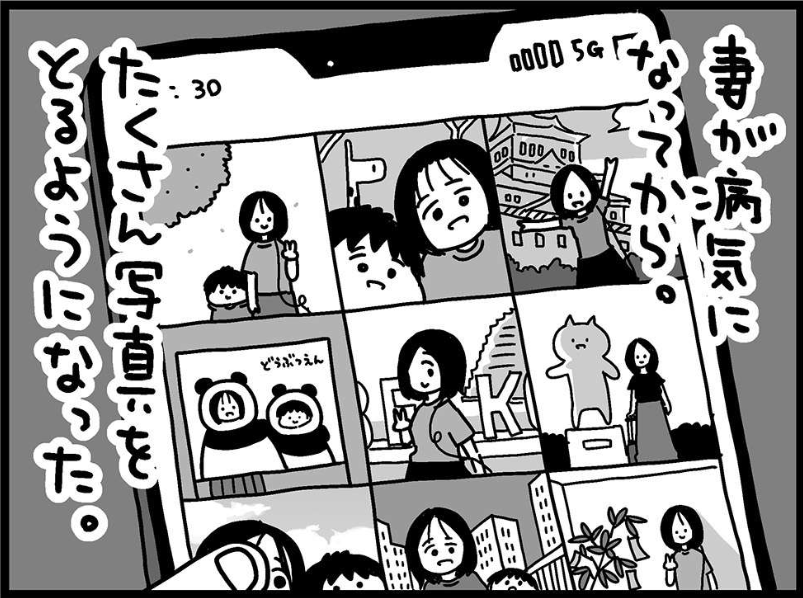「はいよ」
と一郎。まず愛の前に、焼いたハンバーグを置いた。
それを見たわたしは、思わず笑ってしまった。
丸いハンバーグ。そこに、ケチャップで愛の顔が描いてあった。
といっても、大きな丸い目が二つ。そして、ニッコリとした口。それだけだ。
でも、
「これ、わたしだ......」と愛。無邪気な笑顔で言い、食べはじめた。
一郎が、それを優しく見つめている。
愛の存在は、どこまで一郎の心の傷を癒す事ができるのだろうか......。
そうあって欲しいと思いながら、わたしも一郎が作ってくれたハンバーグを食べはじめた。
「でも......」と愛。
「あのオッサン、なんであんなところを歩いてたんだろう」と言った。ハンバーグを、食べ終わったところだった。
「そのオッサンって、たまたま風呂場を覗いちゃった酔っ払いか?」と一郎。愛はうなずいた。
「そのオッサン、大工みたいじゃなかったか?」と一郎。
「あ、そういえば」わたしは、つぶやいた。陽灼けして、はちまき。大工さんっぽかった。すると、
「やっぱりそうか。いま、近くで店を造ってるからなあ......」と一郎。
「店?」とわたし。
「知らなかったのか? お前たちの〈ツボ屋〉から、40メートルぐらいしか離れてないよ。なんか、食い物屋らしいぜ」と一郎。
「食い物屋?」とわたし。
「ああ、なんかレストランっぽいな。すごい突貫工事で造ってるぜ」
一郎が言った。その場所は、確かにうちに近い。
葉山の海岸に沿っているバス通り。そこから、森戸海岸の砂浜に向かっていく細いわき道がある。
うちの〈ツボ屋〉は、その細いわき道に面してるのだけれど......。
「バス通りから、そのわき道に入る角だよ、レストランらしいものを造ってるのは」
と一郎。わたしは、うなずいた。1カ月ほど前、そこで何かの基礎工事をしていた......。
「あれが、レストラン?」訊くと一郎は、うなずいた。
「そんな感じだったな。バス通りに面してる角で、立地条件はいいし」
「確かに......」と愛。
「けど、すごいスピードで造ってたな。かなりの人数の大工やペンキ職人を動員して、日が暮れても工事してたよ」と一郎。わたしは、うなずいた。
湘南でレストランを開こうとしたら、まずは夏が勝負。8月に、どれだけ客をつかむかで、勝負が決まると言ってもいい。
「もしかしたら、ブルーシートをめくったあのオッサン、そこの工事人かも......」
わたしは、つぶやいた。
そのレストランの現場で日暮れまで働いてた大工さんたちが、そのあと少し歩いた砂浜で大々的に酒盛りをやる。
オッサンの一人がひどく酔っ払って、うちの前を通りかかり、何気なくブルーシートをめくった......。そんな可能性は高い。
「いずれにしても、あそこのレストラン、そろそろできるんじゃないか?」
と一郎。もう8月が近い。いま開店しなければ、トップ・シーズンに間に合わない......。
「あの、一つ頼んでいい?」と愛。一郎に言った。
「何だい」
「あの......小さなハンバーグを一つ作ってくれない? サバティーニの晩ご飯に」と愛。
「あの猫か......」と一郎。微笑した。そして、小型のハンバーグを作りはじめた。
手を動かしながら、
「お前、優しいんだな」と愛に言った。そして、ハンバーグを焼きはじめた。
その帰り道。小さなハンバーグを胸にかかえ、
「いままで、がめついとかケチって言われた事はあるけど、優しいなんて言われたの初めてだ......」
愛がポツリとつぶやき、わたしは苦笑。その細い肩を抱いてゆっくりと店に戻る......。
その2日後。
「えぇ!」と愛。
「ありゃ......」とわたし。
二人とも、口を半開き。バス通りとわき道の角は、すごい事になっていた。