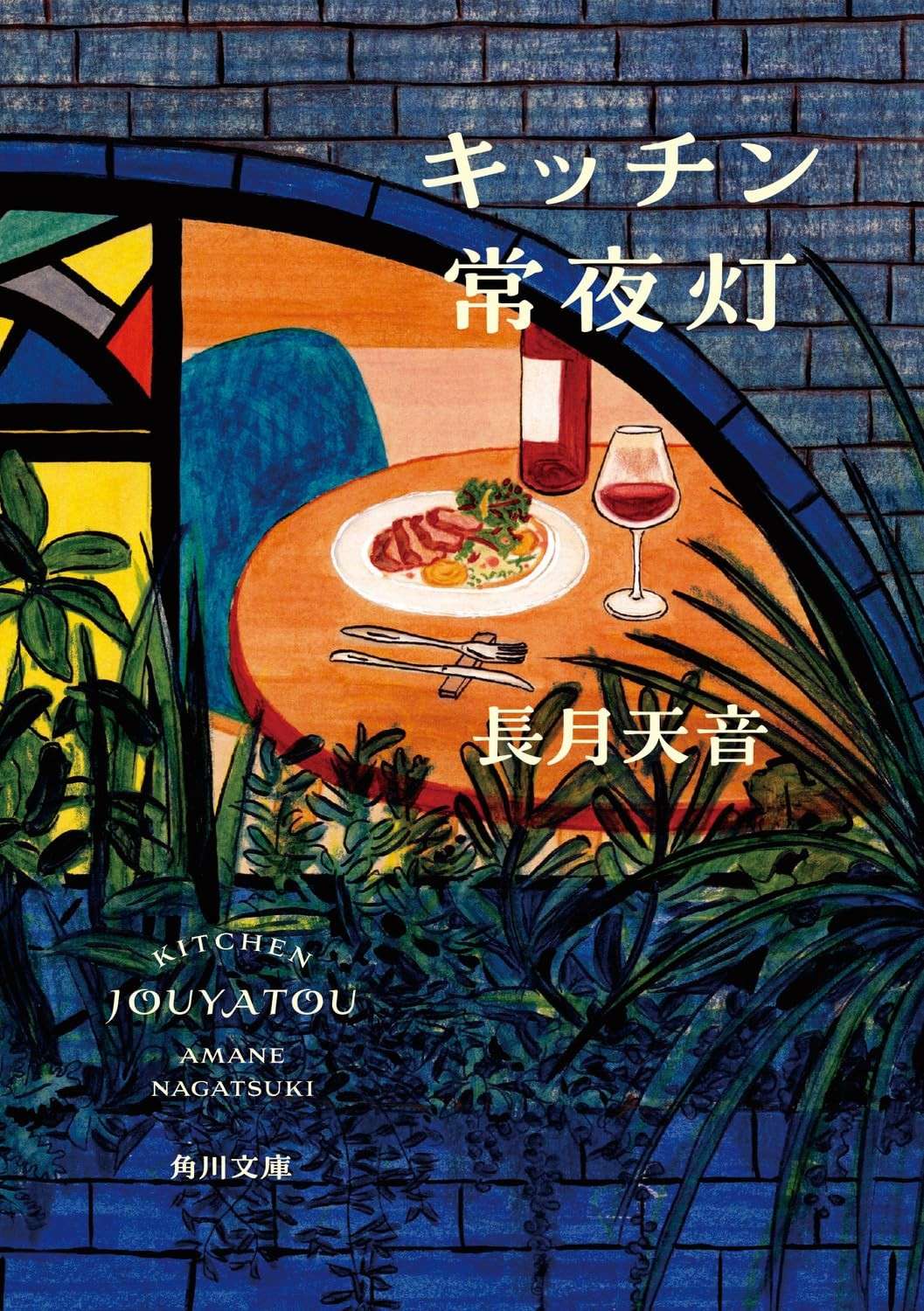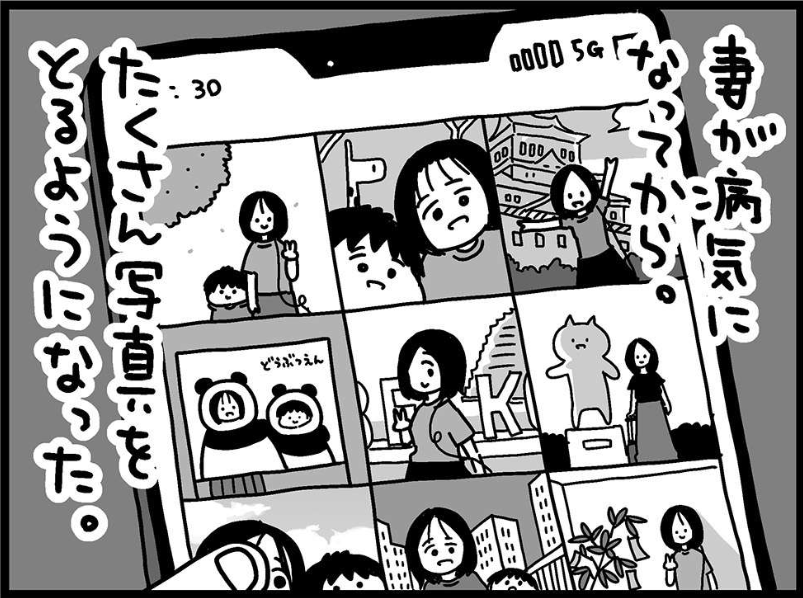堤さんに促され、大事にとっておいたリエットをすくい、薄くカットされたバゲットにのせた。バゲットも軽く焼いてあり、カリッとした食感と滑らかな味わいが口の中に広がった。
「美味しい!」
「でしょう! リエットやパテは特にシェフが得意としているんです。今度はぜひパテ・ド・カンパーニュも食べてみて下さいね!」
ふとシェフを見ると、手元の作業に集中しながらも、口元だけがわずかにほころんでいる。ああ、やっぱりここに来てよかった。ここがあってよかったと、私の体からゆるゆると力が抜け、そのとたん、久しぶりに飲んだアルコールで急に顔が火照ってきた。
でも、この気持ちのままでいたくて、私はもう一杯ワインを注文した。
「お客様は近くにお住まいなんですか?」
ワインを注ぎながら堤さんが訊ねた。
「ほら、このお店、わかりづらい場所にあるじゃないですか。お客さんは常連の方ばかりなの。この前も遅い時間にいらっしゃったでしょ?」
「はい、この一本裏の通りに住んでいます。と言っても、まだ十日くらいなんですけど」
火事でマンションを焼け出されたことは、すでに職場でもスタッフや常連客の何人かに話していた。同情してほしいわけでも、手を差し伸べてほしいわけでもないが、ただ聞いてほしかったのだ。
でも、笑い話にでもしないとやっていられなかった。だから、苦しいくせに平気な顔をして、へらへらと他人事のように語った。これからのことを考えると、途方に暮れて不安で仕方がないくせに、困っていると思われたくなかった。
今夜も、そんなふうにこれまでのことを話した。
堤さんの表情がみるみる曇っていく。
「そうだったの」
「そうなんです。ほら、今日もこの前と同じセーターでしょう。今のところ、これしかなくて」
私は自分のセーターをつまんで見せた。そう。本当に何もかも失ったのだ。
「大変でしたね」
いつの間にか城崎シェフが目の前に立っていた。
「さぞ途方に暮れたことでしょう。でも、行くべき場所があってよかった。本当によかったです」
シェフの言葉に私は頷いた。倉庫があった。会社と金田さんに救われた。
「でも、まだ落ち着かないでしょう。ちゃんと眠れますか。いつでもここに来るといい。ここはそういう場所なんです」
私はシェフの顔を見上げた。
眠れない。火事に遭ってから、ますます夜が怖くなった。
不意に熱いものがこみ上げてくる。
慌てて私は指先で目元をこすった。おかしい。涌井総務部長に電話した時も、金田さんに迎えに来てもらった時も、一度も涙など流さなかったというのに。
堤さんが「あらあら」と肩をさすってくれた。その手の温かさに、とうとうこらえきれず涙がこぼれた。
気を許すことができたのは、きっと、堤さんやシェフが私にとって他人だからだ。
涌井さんや金田さんの前では、私は「ファミリーグリル・シリウス浅草雷門通り店」の店長、南雲みもざでいるしかない。
昔から私は「真面目」だと言われてきたけれど、「店長」という鎧は、真面目な私にとっては本当に呪いでしかなかった。店では分不相応な責任感を与え、店を出ても緩やかに私を締めつづけて、少しの弱音も吐かせてくれないのだ。
堤さんの手があまりにも優しくて、私はこれまで誰にも打ち明けられなかったことまで話してしまった。おそらく彼女が同業者だから、理解してもらえると思ったのだろう。これまでため込んできたものをすべて、聞いてもらいたかったのだ。
「火事だけじゃないんです。私、洋食店の店長なんです。あっ、洋食店といっても、こんな素敵なお店ではなくて、はっきり言ってファミレスなんです。場所もシブい浅草だし」
「まぁ、若いのに店長なんてすごいじゃない。いくつ?」
「三十四、店長になったのは二年前です。店長なんてやりたくなかったのに、無理やり押し付けられたんです。社長がいきなり、女性が活躍する企業を目指すなんて言い出して、既存店の半分を女性店長にしたんです。中には張り切って引き受けた人もいるけど、私は昔から人前に立つタイプじゃない。自分が上に立つより、二番手として支えるほうがぴったりなんですよ。それなのに強引な人事で......」