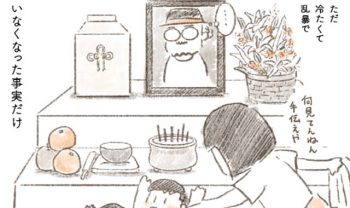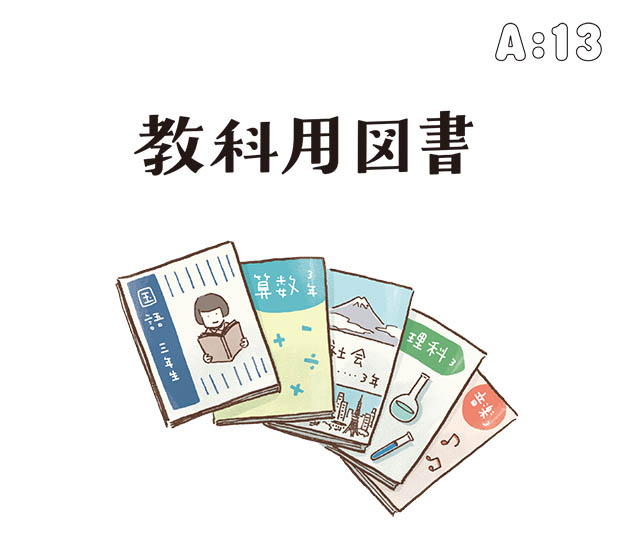
みんなが学校で使っている教科書。
正式には法律で「教科用図書」というんだ。
でも、それだとちょっと長いなまえなので、みんな「教科書」って呼んでいるんだ。
1872(明治5)年に小学校や中学校の制度ができた。
最初は学校によっていろんな本を授業で使っていたけれど、1886(明治19)年に、民間で作った本を国が検定(審査)して、合格した本を教科書として使うことが決まったんだ。
その後、1903(明治36)年から1945(昭和20)年まで、国が教科書を作っていたけど、今はまた民間で作って国が検定した教科書を使っているよ。
【次回】ベルトの長さを調節するアレの名前とは?/まだある!! アレにもコレにも! モノのなまえ事典(6)
【まとめ読み】『アレにもコレにも! モノのなまえ事典』記事リスト

ふだん見ている「アレ」、使っている「コレ」のなまえがクイズでわかる!